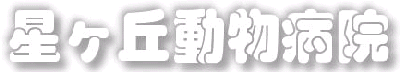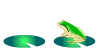愛する動物たちに関るいろいろな、お話・ことわざ・俗語・言葉・事物・由来等、20のお話。 2つのお話を入れ替えました。
2025/12/21  [ 話を入れ替えた際、削除した過去のお話はこちらです ]
[ 話を入れ替えた際、削除した過去のお話はこちらです ]
|
 犬の一時食い 犬の一時食い | ||
| 2025 12/21 |
 餌を与えられたイヌは、一心不乱にとにかく早く食べるます。 そこから、食事のマナーをわきまえないことをいいます。
餌を与えられたイヌは、一心不乱にとにかく早く食べるます。 そこから、食事のマナーをわきまえないことをいいます。
| |
 壁に馬を乗りかける 壁に馬を乗りかける | ||
| 2025 12/21 |

出し抜けにまたは無理押しに事を行うこと。 あるいは突然予期しないことに出会って困惑することのたとえです。 | |
| ドラ猫 | ||
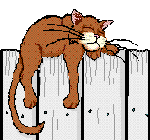 一般的に野良ネコをさす言葉として使われますが、特に「ずうずうしく、人のものを盗み食いするようなネコ」という意味合いで使われることが多いです。
一般的に野良ネコをさす言葉として使われますが、特に「ずうずうしく、人のものを盗み食いするようなネコ」という意味合いで使われることが多いです。
また、ドラは銅鑼を意味し、そこから「金になるものを盗む」という連想で使われるようになったという説もあります。? | ||
| 千石見晴しの田でないと鶴は下りぬ | ||
|
ツルのような立派な鳥は、広々として実り豊かな田でなければ下りたたない。つまらぬ地位には優れた人物はいないものだというたとえです。
| ||
 ウサギの逆立ち ウサギの逆立ち | ||
| 2025 10/26 |
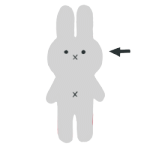 ウサギは逆立ちできませんが、もし逆立ちができたとしたら、長い耳が地面にこすれて、ただれたり傷ができて痛そうです。
ウサギは逆立ちできませんが、もし逆立ちができたとしたら、長い耳が地面にこすれて、ただれたり傷ができて痛そうです。ここから、耳が痛い、弱点をつかれて辛い、嫌味に聞こえて辛いという意味のことわざになりました。 | |
 ミルキングアクション ミルキングアクション | ||
| 2025 10/26 |
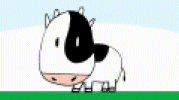 下半身の筋肉が収縮と弛緩を繰り返して血液を心臓へ送る働きです。
下半身の筋肉が収縮と弛緩を繰り返して血液を心臓へ送る働きです。ウシの乳しぼりに似ていることからこの名前が付けられました。 血液循環を良くし、足の冷えやむくみを改善して老化の予防になります。 | |
| 螻蛄(けら)才 | ||
|
そこから多芸多才でありながら、どれも中途半端であることをいいます。また、そのような役に立たない才能のことをいいます。 | ||
| 二頭の熊は同じ巣穴では暮らせない | ||

 ロシアに伝わることわざで、実力のある者が二者いるとき、争いは避けられないということです。
ロシアに伝わることわざで、実力のある者が二者いるとき、争いは避けられないということです。
社会の中で、実力のある者同士が同じ空間や組織の中にいた場合、それはライバル関係になり相容れない関係となります。 野生動物の世界にも見られる現象で、ボスは一頭しかおらず、争いに破れた者はボスの座を明け渡すか仲間から離れなければなりません。 | ||
| 骨をくわえた犬は吠えない | ||
|
いくら理屈をこねたり文句をいったりしていようとも、一旦利益にありつけることができた者は文句をいわないものだということです。 | ||
| さて、羊に戻るとしようか | ||
|
フランス語で話が脱線した時に「本題に戻ろう」という意味でいわれるそうです。 会議などで本題からずれてしまったり、おしゃべりの最中自分の話題がひどくずれてしまい、それに気づいて本題に戻ろうとする際に使われます。起源は古典喜劇にあるといいます。 | ||
| 弱虫 | ||
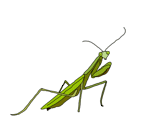 気の弱い人や臆病な人、いくじのない人に対して言われる言葉。
気の弱い人や臆病な人、いくじのない人に対して言われる言葉。また、精神的に弱い人物や非力な人物に対してののしっていう言葉です。 | ||
| 猫になっとる | ||
 ネコのようにおとなしくなっていること。
ネコのようにおとなしくなっていること。本心をかくして目立たないように、まるでネコのようにしていることをいいます。 | ||
| 啄(タク) | ||

「ついばむ」「鳥がくちばしで者をつつき食う」「たたくまたはその音」の意の漢字。
| ||
| 猿臂(えんぴ)を伸ばす | ||
  もともとサルの腕を指す言葉ですが、転じて長く腕を伸ばすことを意味するようになりました。特に物をつかもうとしたり、何かを求めて腕を長く伸ばす様子を表す場合に用いられます。
またはその腕を使った攻撃のことで、空手などの武道で用いられます。
もともとサルの腕を指す言葉ですが、転じて長く腕を伸ばすことを意味するようになりました。特に物をつかもうとしたり、何かを求めて腕を長く伸ばす様子を表す場合に用いられます。
またはその腕を使った攻撃のことで、空手などの武道で用いられます。
| ||
| カエル化現象 | ||
その相手に対して嫌悪感を抱いてしまう現象を表す心理学用語です。 これは、王女と魔法でカエルにされた王子のお話で、 王女は最初カエルを嫌っていますが、最後にカエルは王子に戻り 二人は幸せに結ばれる、というグリム童話の「カエルの王様」 というお話が由来といわれています。 | ||
| 噛む馬はしまいまで噛む | ||
|
| ||
| 影も無いのに犬は吠えぬ | ||
 何の気配もないのにイヌがいきなり吠えたりはしないということから、事実無根なのに噂が流れることはないということです。
何の気配もないのにイヌがいきなり吠えたりはしないということから、事実無根なのに噂が流れることはないということです。
| ||
| 鶏を殺して卵をとる | ||
 ニワトリが卵を産むのを待たないで、殺して中の卵を取れば確かに目先の利益は得られますが、それ以降ニワトリが卵を産むことはありません。
ニワトリが卵を産むのを待たないで、殺して中の卵を取れば確かに目先の利益は得られますが、それ以降ニワトリが卵を産むことはありません。
目先の利益に目がくらんで将来のより大きな利益を忘れることをいいます。 | ||
| 兎の罠に狐がかかる | ||
|
| ||
| 送り狼 | ||
 山中などで、人のあとをつけてきて、すきをみて害を加えると考えられていたオオカミのこと。
山中などで、人のあとをつけてきて、すきをみて害を加えると考えられていたオオカミのこと。
また 親切を装って女性を送っていき、途中ですきがあれば乱暴を働こうとする、危険な男のこともいいます。 | ||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |