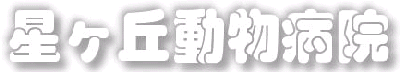|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 猫を嫌う人には気をつけろ | |||
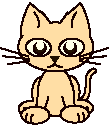 アイルランドのことわざです。
アイルランドのことわざです。ネコを嫌う人は、人を支配したり思い通りに動かしたりするのが好きなので、注意した方がよいという意味です。 自由を好むネコを支配しようとするのは間違いなのですね。 | |||
| 猫は魚を食べたいのに手を濡らしたがらない | |||
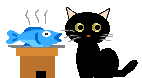 英語圏のことわざ
英語圏のことわざ欲しい物があるのに、自分で手に入れる 努力はしない者をたとえています。 | |||
| 猫の寒恋 | |||
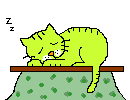 本来寒がりのネコでさえ、真夏の暑い盛りには寒い季節を恋しがるということ。
本来寒がりのネコでさえ、真夏の暑い盛りには寒い季節を恋しがるということ。寒がりの人でも、暑い夏には冬が恋しくなるということです。 | |||
| 魚を焼くと猫が来る | |||
| |||
| 結構毛だらけ猫灰だらけ | |||
 地口といわれる江戸時代の洒落言葉で「大いに結構だ」を意味する言葉遊びのことです。「け」の音と「だらけ」で語呂を合わせています。
地口といわれる江戸時代の洒落言葉で「大いに結構だ」を意味する言葉遊びのことです。「け」の音と「だらけ」で語呂を合わせています。
ネコと灰は、冬の間中火鉢の近くにいることが多いため関連づけられています。 | |||
| 女の尻と猫の鼻は土用三日暖かい | |||
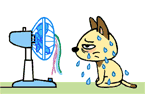 「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の前のそれぞれ 18日間の称ですが、ここでは夏の土用のことで、 7月20日前後から8月8日頃までの、1年中で一番暑い時期のことです。
「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の前のそれぞれ 18日間の称ですが、ここでは夏の土用のことで、 7月20日前後から8月8日頃までの、1年中で一番暑い時期のことです。ネコの鼻先は湿っているため、また、女性のお尻も皮下脂肪のせいで ほぼ1年中冷たいといわれていますが、ネコの鼻はその一番暑い時期に3日間だけさすがに熱くなるということです。 | |||
| 白猫であれ黒猫であれ、ねずみを捕るのが良い猫である | |||
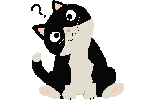 どんな方法であっても、望みの結果を出せればそれで良いという意味です。
どんな方法であっても、望みの結果を出せればそれで良いという意味です。もともとは四川省の古いことわざですが、中国の政治家、鄧小平が言ったことで有名になりました。 | |||
| 男猫一匹膝にも乗せぬ | |||
|
男性を一切寄せ付けず、貞操を堅持するたとえです。 | |||
| 好奇心は猫をも殺す | |||
 イギリスのことわざ Curiosity killed the cat.
イギリスのことわざ Curiosity killed the cat.
他人のことを必要以上にに詮索するとひどい目に遭いますよということです。過剰な好奇心は身を滅ぼすということを、戒めるためのことわざです。 | |||
| 猫間障子(ねこましょうじ) | |||
 下半分くらいにガラスがはまっていて、その上の障子が上げ下げできるものをいいます。
下半分くらいにガラスがはまっていて、その上の障子が上げ下げできるものをいいます。本来はネコが出入出来るぐらいの小窓が付けられたものをいいました。 | |||
| Look like the cat that ate the canary. | |||
|
ネコがカナリアに狙いを定めてうまく仕留めて食べててしまった様子。 そこから何かを達成したような得意げで満足な様子。 またやましいことを隠すかのように、 何ごともなかったのようにすましている様子を表します。 | |||
| 猫も茶を飲む | |||
 ネコでさえお茶を飲んで一休みするということ。
ネコでさえお茶を飲んで一休みするということ。 生意気に分相応なことをするというたとえです。 | |||
| 猫に粥餅 ねこにかゆもち | |||
 ネコはもともと熱いものを食べるのが苦手なものです。そのネコにフーフーやってもなかなか食べごろの温度ならない熱い粥餅を与えたようなものだということです。
ネコはもともと熱いものを食べるのが苦手なものです。そのネコにフーフーやってもなかなか食べごろの温度ならない熱い粥餅を与えたようなものだということです。
手も足も出ない、どーにもならないことのたとえです。 | |||
| 好奇心は猫を殺す | |||
 イギリスのことわざの Curiosity killed the cat. が元のことばです。
イギリスのことわざの Curiosity killed the cat. が元のことばです。
詮索好きが高じたり、好奇心が強すぎると危険だという戒めで、とくに知る必要のない他人のことなどにあれこれ首をつっこむのはトラブルのもとになるということです。 | |||
| 雪隠へ落ちた猫 | |||
 雪隠とは便所のことです。
雪隠とは便所のことです。便所に落ちたネコなどは、汚ないし、暴れるだろうしということで、とても手が付けられないところから、つかまえ所がないことをいうしゃれです。 | |||
| 末っ子は猫の尻尾 | |||
 家を継ぐこともない末っ子は何の役にも立たない
家を継ぐこともない末っ子は何の役にも立たないということで、ネコの尻尾のようなものだということです。 (全国の末っ子の皆さん、決してそんなことはありませんヨ!) | |||
| 描鼠同眠(びょうそどうみん) | |||
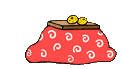 本来は捕まえるべきネズミとネコが一緒に寝ているということで、盗人を捕まえる者と盗人とが結託して悪事を働くことを表す熟語です。
本来は捕まえるべきネズミとネコが一緒に寝ているということで、盗人を捕まえる者と盗人とが結託して悪事を働くことを表す熟語です。
また、悪事を働く人とそれを取り締まる人が示し合わせて事を運ぶことや、上の立場の人と下の立場の人が共謀して悪事を働くことをいいます。 | |||
| 真猫(しんねこ) | |||
 「しんみりねっこり」の擬音のイメージに由来している言葉で、「真猫」と記述されるのは当て字だそうです。
「しんみりねっこり」の擬音のイメージに由来している言葉で、「真猫」と記述されるのは当て字だそうです。
意味は、気のある男女が人目を避けて仲睦まじく向き合って静かに語らうさま、といったことです。 また方言として仲の良い夫婦、といった意味で使われる地域もあるそうです。 | |||
| 猫瓶 | |||


 昔、駄菓子屋等で見られた、口が斜めについた透明の瓶のことで、その形がネコのように見えることからこう呼ばれているようです。
昔、駄菓子屋等で見られた、口が斜めについた透明の瓶のことで、その形がネコのように見えることからこう呼ばれているようです。
ガラス製あるいはプラスチック製があり、丸いものは丸猫瓶、角ばったものは角猫瓶といいます。 | |||
| Don’t let the cat out of the bag! | |||
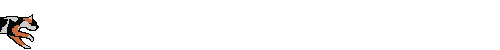
秘密を漏らす、うっかり秘密を話してしまう、という意味です。 “Don't let the cat out of the bag!”は 「秘密をバラすなよ!」ということになります。 | |||
| 公家の子と猫の子は何ぼあっても廃(すた)らぬ | |||
|
| |||
| 猫にサザエ | |||

大好物ですが手の出しようがないということのたとえです。 | |||
| 兄のものは猫の椀まで | |||
 長男は父の遺産を、ネコの椀のようなつまらないものも含め、すべて相続するということ。
長男は父の遺産を、ネコの椀のようなつまらないものも含め、すべて相続するということ。
長子の相続制度では兄にはとにかく権力があり、何から何まで全ての財産は兄に渡るということです。 | |||
| 猫が香箱を作る(香箱座り) | |||
 ネコの座法の一種で、両前脚を胸毛の奥(内側)へ折り曲げて、両後脚を小さく畳んで丸くなってる姿をいいます。
ネコの座法の一種で、両前脚を胸毛の奥(内側)へ折り曲げて、両後脚を小さく畳んで丸くなってる姿をいいます。香箱とは香を入れる箱のことでフタの中央が少し丸く膨らんでるものが多く、それに似ていることからつけられたようで、 「箱座り」「香箱を組む」「香箱を作る」などとも呼ばれます。 英語圏ではパンの塊に例えて「catloaf」と呼ぶそうです。 | |||
| 堪忍を猫に教える | |||
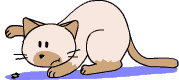 勝手気ままに生きるのがモットーの気まぐれなネコを相手に、堪え忍ぶことを教えるのはとても大変なことであるということです。
勝手気ままに生きるのがモットーの気まぐれなネコを相手に、堪え忍ぶことを教えるのはとても大変なことであるということです。
極めて忍耐力の必要なことのたとえです。 | |||
| 手袋をはめた猫は鼠を取らぬ | |||
|
おしゃれはいいけど爪まで隠していてはネズミをとることは出来ません。 恰好を気にしていては良い仕事が出来ない、 本気で取り組まなければ仕事は成し遂げられないという意味です。 | |||
| 猫馬鹿坊主に火吹き竹 | |||
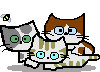 囲炉裏の奥正面の座は主人の席と決まっています。
囲炉裏の奥正面の座は主人の席と決まっています。そこに主人以外で坐るのは、ネコと愚か者と僧侶と火吹き竹ぐらいなものであるということで、家長以外の者が坐るべきではないということです。 | |||
| 猫が熾(おき)をいらうよう | |||
 「熾」は炭火、「いらう」はいじる、という意味。
「熾」は炭火、「いらう」はいじる、という意味。ネコが炭火に手を出しては、さっと引っ込めるように、ちょっかいを出すことをいいます。 | |||
| 鼠取らずが駆け歩く | |||
 ネズミを捕まえないネコは仕事もしないで騒ぐだけ、ということから、役に立たないもののことです。
ネズミを捕まえないネコは仕事もしないで騒ぐだけ、ということから、役に立たないもののことです。ろくな働きをしない者が忙しそうに走り回ることや、つまらない者に限って物事をするときに大騒ぎするものだということもいいます。 | |||
| 猟ある猫は爪をかくす ( りょうあるねこはつめをかくす ) | |||
|
| |||
| 猫と庄屋に取らぬは無い | |||
 この庄屋とは荘園の事務を司った荘司・荘官の総称。
この庄屋とは荘園の事務を司った荘司・荘官の総称。目の前のネズミを取らないネコがいないように、庄屋も機会があれば 必ず袖の下をとるものだということで、賄賂に手を出す役人を皮肉っていう言葉です。 | |||
| 猫の逆恨み | |||
|
| |||
| 猫は虎の心を知らず | |||
|
| |||
| 猫に唐傘 | |||
 猫の前でたたんだ傘を急に開いて
猫の前でたたんだ傘を急に開いてびっくりさせるということから、 驚くことや嫌がることなどのたとえです。 | |||
| 蚕を飼えば猫を飼え | |||
|
| |||
| 庄屋と赤猫に油断すな | |||
| |||
| 猫面(ねこおもて、ねこづら) | |||
|
| |||
| 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる | |||
|
秋は晴れの日は肌寒く、雨の日のほうがむしろ暖かいということから、秋に雨が降ると寒がりのネコは、顔を三尺(約90cm)に長くなるほど喜ぶということです。
| |||
| 猫の泣き食らい | |||
|
泣きながらものを食べることをいいます。 | |||
| 猫に憎まれれば引っ掻かれる | |||
|
人から恨みをかうと、いいことはないということです。 | |||
| 猫の精進 | |||
|
| |||
| 三年になる鼠を今年生まれの猫子が捕らえる | |||
|
優れた人物は小さい頃から人並みはずれた才能を現すということ。 また、子供のために大人がやり込められることのたとえです。 | |||
| 猫は傾城の生まれ変わり | |||
 傾城は絶世の美女や特に上級の遊女のこと。
傾城は絶世の美女や特に上級の遊女のこと。客に対するしぐさがどことなくネコに似ていることや、ネコの皮でつくった三味線で唄ったり踊ったことなどから、 遊女はネコの生まれ変わり、またはネコに生まれ変わるという俗説が生まれました。 | |||
| 猫の子をもらうよう | |||
|
| |||
| 女の怖がると猫の寒がるは嘘 | |||
|
| |||
| 猫の食い残し | |||
|
食べちらかした様子の例えで、行儀の悪いことをいいます。 | |||
| 女の腰と猫の鼻はいつも冷たい | |||
|
| |||
| あってもなくても猫の尻尾 | |||
|
| |||
| 猫の子の貰いがけ嫁の取りがけ | |||
 もらったばかりのネコの子はみんなから可愛がられ、
もらったばかりのネコの子はみんなから可愛がられ、嫁も家に来てすぐの間は皆から大切にされます。 初めのうちだけはどちらも珍しがられ大切にされるが、やがて粗末に扱われるようになるということです。 | |||
| 猫舌の長風呂入り | |||
|
| |||
| 猫が胡桃を回すよう | |||
|
| |||
| 猫の寒恋(ねこのかんごい) | |||
 寒さの嫌いなネコでも夏の暑い盛りには冬を恋しく思うということで、同じように寒がりな人でも真夏には冬を恋しがるということです。
寒さの嫌いなネコでも夏の暑い盛りには冬を恋しく思うということで、同じように寒がりな人でも真夏には冬を恋しがるということです。そこから、現状に満足しない身勝手さをあらわすようになり、転じて、物には限度があることのたとえになりました。 | |||
| 猫を追うより鰹節を隠せ | |||

ネコに鰹節を食われてしまうのを恐れたえず番をしてネコを追い払うより、鰹節の方を隠す方が簡単に問題を解決することが出来ます。 | |||
| ちょっかい | |||
|
| |||
| 小姑一人は猫千匹 | |||
|
嫁にとっての小姑の存在というのは、猫千匹に匹敵するほど 非常に厄介な存在であったということです。 | |||
| 猫の額 | |||
|
| |||
| 猫が肥えれば鰹節が痩せる | |||

カツオブシを食べたネコは太るが、かじられたカツオブシは痩せて細くなるということ。 | |||
| 鳴く猫はネズミを捕らぬ | |||
 ネズミを良く捕るネコは鳴かないということから、やたらとしゃべる人はとかく口先だけで、実行が伴っていないということです。
ネズミを良く捕るネコは鳴かないということから、やたらとしゃべる人はとかく口先だけで、実行が伴っていないということです。
| |||
| 猫をかぶる | |||

獰猛さを隠しあたかもおとなしいネコのように振る舞う事や人をいいます。 | |||
| 猫の落下 | |||
| |||
| 家出猫を呼び戻すおまじない | |||
ネコはフラッと家を出たまま何日も帰ってこないことがありますが、そんな時に良く行われていたおまじない(?)をご紹介しておきます。
 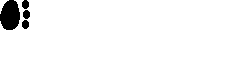
| |||
| 皿なめた猫が科(とが)を負う | |||
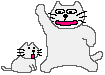
皿の上の魚を食べたネコが逃げてしまい、そのあと皿をなめただけの別のネコが捕まって罪を着せられるということ。 | |||
| キャッツアイ Cat's-eye | |||

日本名も猫目石。球状の表面が光を屈折して、白い一本の光条が細くくっきり浮き上がり、その様子がまさに猫の目が光るときを思わせます。 | |||
| だまり猫がネズミを獲る | |||
|
あまり鳴かずに物静かで派手さの無いネコがよくネズミを獲るように、派手な行動をしないが黙々としている人が、人の知らない間に大事をなすものだということです。 | |||
| 夜はすべての猫が灰色に見える | |||

夜暗くなるとネコがみんな灰色に見えるようになります。 | |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |