|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 能なし犬は昼吠える | ||||
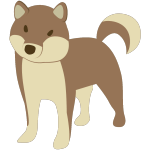 取り柄のないイヌは意味もなく、昼でもむやみに吠えます。
取り柄のないイヌは意味もなく、昼でもむやみに吠えます。才能や能力がない人ほど、自分の器以上の大きな話をしたり、騒ぎ立てたりすることの、ネガティブな意味合いの強いたとえとして使われます。 | ||||
| 犬の逃げ吠え | ||||
|
| ||||
| 心の無い人にものを食わせても犬に劣る | ||||
 感謝する気持ちがない人に何かを与えても、イヌのように懐いてくるわけでもない。無駄であるということです。
感謝する気持ちがない人に何かを与えても、イヌのように懐いてくるわけでもない。無駄であるということです。
| ||||
| 生ける犬は死せる虎に勝る | ||||
 死んでいるトラよりも、生きているイヌの方が役に立つことから、どんなに優れた者であっても、死んでしまっては何の役にも立たなくなるということです。
死んでいるトラよりも、生きているイヌの方が役に立つことから、どんなに優れた者であっても、死んでしまっては何の役にも立たなくなるということです。
| ||||
| 居候は犬にも可愛がられよ | ||||
 居候は非常に立場が弱いので、その家の飼いイヌにも好かれておいた方がよいということです。
イヌは家族の一員として扱われることが多く、居候がイヌにも可愛がられるということは、その家庭やコミュニティーにおいて受け入れられているということです。
居候は非常に立場が弱いので、その家の飼いイヌにも好かれておいた方がよいということです。
イヌは家族の一員として扱われることが多く、居候がイヌにも可愛がられるということは、その家庭やコミュニティーにおいて受け入れられているということです。
| ||||
| 旅の犬が尾をすぼめる | ||||
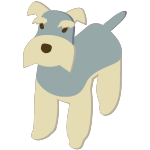 自分の家や縄張りの外に出ると尻尾をすぼめてイヌが大人しくなるということです。
自分の家や縄張りの外に出ると尻尾をすぼめてイヌが大人しくなるということです。家の中では威張っていたり態度が大きい人が、外に出るととたんに大人しくなることのたとえに使われます。 | ||||
| 犬一代に狸一匹 | ||||
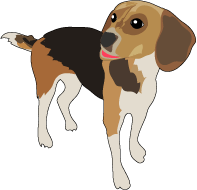 猟犬のようにずっと獲物を探し回っているイヌだとしても、タヌキのような大物を捕まえることができるのは、一生にたった一匹であるという意味から生まれた言葉です。
猟犬のようにずっと獲物を探し回っているイヌだとしても、タヌキのような大物を捕まえることができるのは、一生にたった一匹であるという意味から生まれた言葉です。
人がチャンスに巡り会えることはめったにない、ということです。 | ||||
| 盗人が犬に食われた | ||||
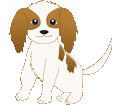 盗人がイヌにかまれても文句は言えないという意味です。
盗人がイヌにかまれても文句は言えないという意味です。自分が悪ければ他人にどのように批判や反撃されようと、それを受け入れて泣き寝入りをするしかない、ということです。 | ||||
| 負け犬の遠吠え | ||||
 弱いイヌは相手のイヌがいないところで遠吠えをする、ということに由来にしたことわざで、
相手よりも自分の立場が弱いと感じている人が面と向かっては何も言わないのに、裏では悪口や文句をいうということです。
弱いイヌは相手のイヌがいないところで遠吠えをする、ということに由来にしたことわざで、
相手よりも自分の立場が弱いと感じている人が面と向かっては何も言わないのに、裏では悪口や文句をいうということです。
| ||||
| 犬、塊(つちくれ)を逐う | ||||
|
イヌは、投げられた塊(土のカタマリ)ばかりを追って、投げた人を追いません。同様に、無知な人は、結果だけを見てその原因を追求しないということです。
涅槃経の言葉で、愚かな人間になるなと戒める言葉です。
ちなみに「追う」は、既に目に見えている物や目標へ向かうこと。 「逐う」は、まだ見つけていない物を探す。更に深く知る為に研究する。意識を向ける。注目すること。 | ||||
| 米食った犬が叩かれずに糠食った犬が叩かれる | ||||
 米を盗み食いしたイヌが逃げたあとに、残った米糠を舐めただけのイヌが見つかってしまい、叱られる様子です。
米を盗み食いしたイヌが逃げたあとに、残った米糠を舐めただけのイヌが見つかってしまい、叱られる様子です。
大きな悪事をはたらいた者が罪を逃れ、小さな悪事を犯した小物だけが捕まり罰せられることのたとえです。 | ||||
| イヌにも豊年あり | ||||
 どんなイヌにも全盛期があるように、誰にでも成功する機会というものはある、ということです。
どんなイヌにも全盛期があるように、誰にでも成功する機会というものはある、ということです。
| ||||
| 自慢の糞は犬も食わぬ | ||||
 自慢をする者はまわりの人に嫌われ、糞をかぎ回るイヌでさえ、そういう人間の糞は避けるという意味から、
自慢をする者はまわりの人に嫌われ、糞をかぎ回るイヌでさえ、そういう人間の糞は避けるという意味から、誰にも相手にされないことをいいます。 | ||||
| 飼い葉桶の中の犬 | ||||
 飼い葉桶の中にイヌが横たわって、ウシたちが干し草を食べようとすることを邪魔しているということ。
飼い葉桶の中にイヌが横たわって、ウシたちが干し草を食べようとすることを邪魔しているということ。自分には必要のないものなのに他人に使わせないようにする、意地悪な人のことをいいます。 | ||||
| 悪しき人に順って避けざれば、繋げる犬の柱を巡るが如し | ||||
|
悪い人と一緒に行動するということは、繋がれたイヌが柱の周りをグルグル回るうちに、ひもで自分の首を絞めるようなものだ、ということです。
素業の悪い人と付き合っていると、いつかは自分の身に災難が降りかかりますよということです。 | ||||
| 油樽に犬が付く | ||||
 油が入った樽には、それを舐めようとしてイヌが集まってくるといいます。
油が入った樽には、それを舐めようとしてイヌが集まってくるといいます。そこから儲け話や旨い話あがあるところには人が群がってくるものだということです。 また、不正をしている者の周りには悪人が集まってくるものだという意味もあります。 | ||||
| お伽犬 | ||||
 お伽犬(おとぎいぬ)とは、オス・メス一対の座形犬で、胡粉彩色や金銀箔押しをした美しい飾り物のことです。
お伽犬(おとぎいぬ)とは、オス・メス一対の座形犬で、胡粉彩色や金銀箔押しをした美しい飾り物のことです。
箱になっていて、中にはお守りや玩具、化粧道具などを入れ、犬箱あるいは犬張子ともいいます。 イヌは神社の「こまいぬ」が示すように、悪魔・怨霊を祓うと信じられ、守護の象徴ですので、新生児の枕元に置き、我が子の幸福を願うお守りとしたり、 また、イヌはお産が軽いところから、産所や寝所で必要とする物を入れ、安産や魔除けのお守りでもあったようです。 | ||||
| 犬走り | ||||
|
イヌが通れるくらいの幅しかない道という意味合いからこう呼ばれます。 築地の犬走り : 築地とその外側の溝との間に設けられた平地のうち、狭いもの。 城郭の犬走り : 城の石垣や土塁と、堀の間に設けられた狭い空き地。 土手の犬走り : 河川の土手、堤防などの傾斜上に設けられた平地。 線路の犬走り : 鉄道の線路と同水準に設置される保線作業員の通路など。 軒下の犬走り : 建物の軒下の外壁周縁部を砂利敷きやコンクリートを打ったもの。 | ||||
| 両虎相闘いて駑犬その弊を受く | ||||
 非常に強い二頭の虎が争っていたときに、その疲れに乗じて駑犬(どけん:つまらないイヌ)がうまい汁を吸うということです。
非常に強い二頭の虎が争っていたときに、その疲れに乗じて駑犬(どけん:つまらないイヌ)がうまい汁を吸うということです。
強豪同士が戦っているすきに、弱小の者が労せずして利益を得ることができるというたとえで、漁夫の利と同じような意味です。 | ||||
| 黒犬を 提灯にする 雪の道 | ||||
 古い川柳。
古い川柳。江戸の町は夜になると濃い闇に包まれましたが、提灯は高価で庶民には手が届かなかったといいます。 そんな江戸の冬。雪が降ったあとの夜道は一面が真っ白で、どこが道だかわからなくなっています。 そこである知恵者が真っ黒な飼い犬を先に行かせて道案内させました。真っ黒な飼い犬は臭覚で馴れた道をどんどん先へ行く、白い雪に黒い犬はよく目立ち提灯代りにされているということです。 | ||||
| 姦無きを以て吠えざるの狗を畜いべからず | ||||
 悪人がいないからといって、吠えないイヌを飼う必要はないということで、天下泰平の時代でも、無能な人間を選ぶべきではないということのたとえです。
悪人がいないからといって、吠えないイヌを飼う必要はないということで、天下泰平の時代でも、無能な人間を選ぶべきではないということのたとえです。
平和で治まった世の中においても諫めてくれる臣下が必要であり、平穏でみんな仲の良い時にも忠言を吐いてくれる友人を持たなければならないということです。 | ||||
| 邑犬群吠(ゆうけんぐんばい) | ||||

 邑(村里)のイヌが群がって吠えていると意味。
邑(村里)のイヌが群がって吠えていると意味。小人がこぞって集まり、人のうわさや悪口などに興じて騒ぎ立てることをいい、愚者が賢者を非難するたとえであります。 | ||||
| ホウレイの浜には魚を以て犬に食わしむ | ||||
 ホウレイの浜では魚が非常に沢山捕れるので、犬にも食べさせるということから、物が有り余ってる時は軽んじられるということを意味しています。
ホウレイの浜では魚が非常に沢山捕れるので、犬にも食べさせるということから、物が有り余ってる時は軽んじられるということを意味しています。(ホウレイは中国最大の淡水湖で現在の八陽湖) | ||||
| 犬兎の争い ( けんとのあらそい ) | ||||
|
疲れて死んだのを、 農夫が両方とも自分のものにしたという寓話から、 両者が争って互いに弱った時第三者に利益をとられることをいいます。 | ||||
| 犬の小道知る | ||||
|
経験や知識が豊富な者は、判断を誤ることはないという意味です。 | ||||
| 垣堅くして犬入らず | ||||
|
家庭内が健全であれば外部からこれを乱すような者が 入ってくることはないということです。 | ||||
| 外孫飼うより犬の子飼え | ||||
|
そんな孫をかわいがるより、イヌの子をかわいがるほうがましだ(???)ということです。 | ||||
| 犬に懸鯛 | ||||
 立派な鯛の飾りも見る人がいなければ価値がない。価値あるものもそれを理解できる人が持たなければ無駄だということです。
立派な鯛の飾りも見る人がいなければ価値がない。価値あるものもそれを理解できる人が持たなければ無駄だということです。
懸鯛(かけだい)は、正月、夷講、祭礼、婚礼その他の祝いに、飾り物として用いられるものです。 漁船が沖から帰ってきたとき、漁獲物のなかから2尾の魚を選んで腹合わせに吊るし、収穫を感謝し次の大漁を祈願するために、港近くの夷(えびす)様に供えたというのがはじまりで、内陸や町場にも及んだようです。 | ||||
| 尾を振る犬も噛むことあり | ||||
|
| ||||
| 夏の風邪は犬もひかぬ | ||||
|
| ||||
| 桀 (けつ)の犬尭(ぎょう)に吠ゆ | ||||
|
「桀」は中国古代の暴君。「尭」は中国古代の伝説上の帝王で理想的な君主とされています。 「桀の犬をして尭に吠えしむ」ともいいます。 | ||||
| 殿の犬には喰われ損 | ||||
 殿さまの飼っているイヌに咬まれても文句は言えるものではありません。
殿さまの飼っているイヌに咬まれても文句は言えるものではありません。勢いの強い者がやったことは、たとえ道理にはずれていることであっても泣き寝入りするしかない、という意味です。 | ||||
| 犬腹(いぬっぱら) | ||||
 お産が軽く安産の象徴でもあるイヌのように、たくさんの子を次々と生んでいく女性のことをいいます。
お産が軽く安産の象徴でもあるイヌのように、たくさんの子を次々と生んでいく女性のことをいいます。侮蔑的表現でもあるのでご注意を。 | ||||
| 兎を見て犬を放つ | ||||
| ||||
| 食うだけなら犬でも食う | ||||
|
昔は、イヌは食べることにだけ幸せを感じる生き物という認識だったためですが、現在では決してそのようなことはありませんね。 | ||||
| 猛(モウ) | ||||

「たけだけしい犬」「たけだけしい」「いさましい」「きびしい」「はげしい」の意の漢字。 | ||||
| 星守る犬 | ||||
 「守る」は見つめるという意味で、星を取ろうとじっと見つめるイヌのように卑小な者が及ばぬ望みをかけることをいいます。
「守る」は見つめるという意味で、星を取ろうとじっと見つめるイヌのように卑小な者が及ばぬ望みをかけることをいいます。分不相応な高望みをするということです。 | ||||
| 狡兎死して走狗烹らる (こうとししてそうくにらる) | ||||
| ||||
| 食いつく犬は吠えつかぬ | ||||
|
| ||||
| 影もないのに犬は吠えぬ | ||||
 犬はなにもないのに吠えたりはせず、 吠えるのはなにかがそこにあるからなのです。
犬はなにもないのに吠えたりはせず、 吠えるのはなにかがそこにあるからなのです。事実がないのであれば噂が立つこともないということで、「火のない所に煙は立たぬ」と同じ意味です。 | ||||
| 子供が生まれたら、イヌを飼いなさい・・・ | ||||
 子供が生まれたら、イヌを飼いなさい。
子供が生まれたら、イヌを飼いなさい。子供が赤ん坊の時、子供の良き守り手になるでしょう。 子供が幼年期の時、子供の良き遊び相手になるでしょう。 子供が少年期の時、子供の良き理解者となるでしょう。 そして子供が大きくなった時、 自らの死をもって子供に命の尊さを教えるでしょう。 イギリスのことわざです
| ||||
| 犬の糞でかたきを討つ | ||||
| ||||
| 犬の蚤の噛み当て | ||||
| ||||
| 嗅(キュウ)・ [臭] | ||||

口+臭⇒鼻+臭 口の部分は本来鼻をあらわし、臭はにおい、
| ||||
| 喪家の狗(そうかのイヌ) | ||||
|
| ||||
| 蜀犬日に吠ゆ(しょくけんひにほゆ) | ||||
 中国の蜀地方は霧が深く日照時間も短いので、そこのイヌはたまに太陽が照り出すと驚いてほえるという話から。
中国の蜀地方は霧が深く日照時間も短いので、そこのイヌはたまに太陽が照り出すと驚いてほえるという話から。
無知なために当然なことにも驚き恐れ怪しむことや、見識の狭い者が他人の言動を怪しんだり批判したりするをいいます。 | ||||
| 暗がりの犬の糞 | ||||
|
| ||||
| わが門で吠えぬ犬なし | ||||
|
| ||||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |



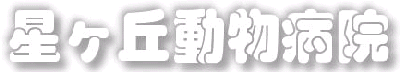


 と孟の合字。
と孟の合字。
