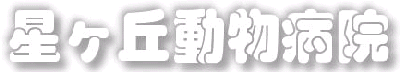|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 馬は宵に飼え、人は昼に飼え | |||
|
「飼え」というのは「食事を与えろ」という意味です。ウマをよく働かせるためには、前日の夜中によく食事をさせておくことだということです。これが人の場合だと、昼食においしいものを食べさせると夜までよく働くことができます。このように、人を動かすには報酬の与え方が重要である、というたとえです。
| |||
| 家に帰りたがる馬は高く売れる | |||
|
一瞬、やる気のなさそうウマなのに、なんで高く売れるのか?と思いそうですが、これは、家から遠い市場などに連れてこられているにも関わらず、そこから自力で帰ることができるほど、記憶力のよいウマは頭がよい、ということで、値段を高くつけることができるということです。
| |||
| 寒立馬(かんだちめ) | |||


 青森県下北半島尻屋崎周辺に一年中放牧されているウマのことで、寒風吹きすさぶ雪原でじっと立っている様子が、カモシカの「寒立ち」に似ていることからこういわれます。
青森県下北半島尻屋崎周辺に一年中放牧されているウマのことで、寒風吹きすさぶ雪原でじっと立っている様子が、カモシカの「寒立ち」に似ていることからこういわれます。
南部馬の系統で足が短く胴が長くてずんぐりしており、 おとなしくて寒さに強く、農耕馬として飼われていました。 | |||
| 手馬、手綱いらず | |||
| |||
| 先鞭をつける | |||
|
そこから、人に先んじて着手する、他に先駆けることをいいます。 | |||
| 馬に乗れば唄心 | |||
|
ウマに乗ると楽しくなり、高揚して歌を歌いたくなる、という意味です。 | |||
| 馬は土から | |||
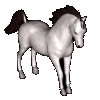 よいウマを育てるには、まず土がよいことが条件であるということです。土とは、広い土地であったり、栄養のある良質な牧草地であったり、ウマを育てるのによい環境であるということです。
よいウマを育てるには、まず土がよいことが条件であるということです。土とは、広い土地であったり、栄養のある良質な牧草地であったり、ウマを育てるのによい環境であるということです。
そこから、よいものを得ようとするのであれば、その基礎となる部分からよいものでなければならない、という意味になります。 | |||
| 内で掃除せぬ馬は外で毛を振る | |||
|
キチンと手入れされていないウマは、外に出たときに体の汚れを落とそうとして全身の毛を振ります。 そのようすから、飼い主の手入れがいかに悪いかがわかるということから、 家庭内でしつけされていない子供は、外に出ると家での教育や躾の様子がすぐにわかってしまうということです。 また内輪だけのことと悪い習慣などを隠していても、外に出るとやはり悪い癖が出るので、その話はすぐに広まってしまうということです。 | |||
| 馬を得て鞭を失う | |||
 一方を得た代わりに、もう一方を失うこと。また、
一方を得た代わりに、もう一方を失うこと。また、目的とするものは得ることができたが、それを活用する手段を失ってしまったことをいいます。 | |||
| 六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わず | |||
  
  
「六馬」とは、天帝の息子が乗る六頭の馬車を引くウマのこと。 「造父」とは、すぐれた御者で、周繆王に仕えていました。 車を引く六頭のウマの気持ちがうまく合っていなければ、すぐれた御者の造父であっても、遠くまで馬車を走らせることは不可能であることから。 | |||
| 轡(くつわ)を並べる | |||
| |||
| 入夫は一生下馬(にゅうふはいっしょうげば) | |||
|
敬意を表すためにウマを下りることです。 入り婿は生涯その家では力を持てない、 頭が上がらないということです。 | |||
| 死に馬に鍼刺す | |||
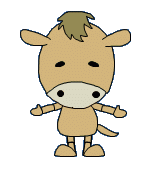 すでに死んでしまったウマに、健康を保つためのハリ治療を施すということで、何の意味もないことや役に立たないむだなことをすることのたとえです。
すでに死んでしまったウマに、健康を保つためのハリ治療を施すということで、何の意味もないことや役に立たないむだなことをすることのたとえです。 また、絶望的な状況にありながら、なお万が一の望みをもって最後の手段を講じることのたとえでもあります。 | |||
| 道草 | |||
 ウマが輸送や農作業に活躍していた頃、目的地へ行く途中や帰り道で、道端の草を食べながら時間をかけぶらぶら歩くことをいいました。
ウマが輸送や農作業に活躍していた頃、目的地へ行く途中や帰り道で、道端の草を食べながら時間をかけぶらぶら歩くことをいいました。
そこから、目的地へ行く途中で他のことに時間を費やしたり、途中で手間取ったり寄り道をすることをいうようになりました。 | |||
| 輿馬(よば)を仮る者は足を労せずして千里を致す | |||
 「輿馬」とは、車やウマのこと。 車やウマに乗って行く者は、自分の足を使わず疲れることもなく、千里もの道を行けることから。他のものをうまく利用することによって、容易に事をなしとげることのたとえです。
「輿馬」とは、車やウマのこと。 車やウマに乗って行く者は、自分の足を使わず疲れることもなく、千里もの道を行けることから。他のものをうまく利用することによって、容易に事をなしとげることのたとえです。
| |||
| 走馬灯 | |||
|
中国発祥で日本では江戸中期に夏の夜の娯楽として登場した灯籠の一種で、回り灯籠ともいいます。 灯籠の内側にもう一つ筒型の枠を入れ、そこに切り絵を貼って影絵のように見せる物です。 またその内側の枠には風車が取り付けられていて、 灯をともすと熱でくるくる回るようになっています。 | |||
| ダークホース dark horse | |||
 その能力がよくわからないが、予想外の活躍をして番狂わせを演じるかもしれない競走馬のことで、穴馬ともいいます。
そこから実力は未知だが、有力と思われる競争相手のことや、競技や選挙などで、番狂わせを演じそうな選手や候補者のことをいいます。
また、上位ではないが隠れた実力者、伏兵のことをいうこともあります。
その能力がよくわからないが、予想外の活躍をして番狂わせを演じるかもしれない競走馬のことで、穴馬ともいいます。
そこから実力は未知だが、有力と思われる競争相手のことや、競技や選挙などで、番狂わせを演じそうな選手や候補者のことをいいます。
また、上位ではないが隠れた実力者、伏兵のことをいうこともあります。
| |||
| 桂馬の高上がり | |||
 将棋で桂馬は、前のこまを飛び越して進むめるが左右には動けないので、前に進みすぎると簡単に歩に取られてしまいます。
将棋で桂馬は、前のこまを飛び越して進むめるが左右には動けないので、前に進みすぎると簡単に歩に取られてしまいます。
そこから、先輩を追い越して不意に出世をした者は、経験不足や人のねたみを受けたり、弱い者にまでやられてしまうという思わぬつまずきをするということ、分不相応の高い地位につくと失敗するということです。 | |||
| 蹴る馬も乗り手次第 | |||
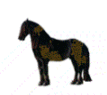 暴れウマでも乗り手の調教次第でおとなしくなるということです。
暴れウマでも乗り手の調教次第でおとなしくなるということです。そこから、たとえ乱暴で扱いにくい者でも、頭の上がらない相手がいるものだということ、また、上手い扱い方があるものだということです。 | |||
| 驥、塩車に服す (き、えんしゃにふくす) | |||
|
一日に千里も走るといわれる名馬が塩を運ぶ車を引くのに使われている、ということ。才能のすぐれた人物が世に認められないでいることをいいます。 「驥」は一日に千里を走る名馬で「塩車」は塩を運ぶ車のことです。 | |||
| 食い付き馬に乗ったよう | |||
|
食いつく癖のあるウマに乗ると、乗っているのも危ないが 降りるとウマに食いつかれるので降りることもできない、ということです。 | |||
| 轡の音にも目をさます | |||
|
轡(くつわ)はウマの口にくわえさえ、手綱を付ける鉄の輪のことです。 | |||
| 馬持たずに馬貸すな | |||
|
「馬持たず」はウマを持っていない人のことで、ウマの扱い方が下手で愛情もわかず、粗末に扱うかもしれないから貸さない方がいいということです。
物の扱い方を知らない人に、物を貸すのは良くないということです。 | |||
| 白馬馬に非ず | |||
|
中国周時代に公孫竜が、「馬」は形に名付けられた概念で「白」は色に名付けられたであるから「馬」と「白馬」は別の概念を表す、という論を説いたことから詭弁の論理のことをいいます。
| |||
| 敢(あ)えて後れたるに非ず、馬進まざればなり | |||
 自分の手柄を誇ることをせずに謙遜することのたとえ。
自分の手柄を誇ることをせずに謙遜することのたとえ。
魯の大夫孟之反が、味方の軍隊が敗れて退散するとき、わざと遅れて最後尾につき敵を防いだ。 軍がそのときの功績を称えようとすると「ウマが進まなかったために遅れた」と言って、自分の手柄を誇らなかったという故事から。 | |||
| 快馬は鞭影を見るや正路につく | |||
|
優れたウマは人間のもつ鞭の影を見ただけで 進むべき道をきちんと疾走していくといいます。 | |||
| 空馬に怪我なし | |||
 | |||
| 一馬の奔(はし)る、一毛の動かざるは無し | |||
|
ウマが走れば全身の毛で動かない毛はないということから、中心的人物がある行動を起こすと、それに付属しているものも一斉に行動を起こすことをいいます。
| |||
| 朝には富児の門を扣き、暮には肥馬の塵に随う | |||
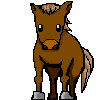 朝は金持ちの人の門を叩いてご機嫌をうかがい、夕方には肥えたウマに乗っている権力のある人の後ろから埃を浴びてお供をする、ということから、
金持ちや身分の高い人に取り入ろうとするさまをいいます。
朝は金持ちの人の門を叩いてご機嫌をうかがい、夕方には肥えたウマに乗っている権力のある人の後ろから埃を浴びてお供をする、ということから、
金持ちや身分の高い人に取り入ろうとするさまをいいます。富児とは、身分が高く裕福な人のことです。 | |||
| 弱馬道を急ぐ | |||
|
弱いウマほど焦って道を急ぐことから、実力や才能のない者に限って、気ばかり焦って功を急ぐということをいいます。
| |||
| 痩せ馬の声嚇し(おどし) | |||
 痩せて弱々しい馬が、体に似合わず大きな声でいなないて、人を驚かせることから転じて。弱い者、実力のない者が、口先だけは威勢がよいことをいいます。
痩せて弱々しい馬が、体に似合わず大きな声でいなないて、人を驚かせることから転じて。弱い者、実力のない者が、口先だけは威勢がよいことをいいます。
| |||
| 馬痩せて毛長し | |||
|
| |||
| 帰馬放牛(きばほうぎゅう) | |||
 戦争で使ってたウマやウシを野に帰し放つということから、戦争が終わって平和になることや、再び戦争をしないということを表します。
戦争で使ってたウマやウシを野に帰し放つということから、戦争が終わって平和になることや、再び戦争をしないということを表します。
| |||
| 駄賃 | |||
 元は駄馬で荷物を運ぶだけの賃金ことで、買い物や届け物など外へ出掛ける用事を頼んだ時に足代兼ご褒美として支払う手間賃のことをいいます。
元は駄馬で荷物を運ぶだけの賃金ことで、買い物や届け物など外へ出掛ける用事を頼んだ時に足代兼ご褒美として支払う手間賃のことをいいます。
そこから、使い走りなどの簡単な雑用に対して与える金品、特に子供が手伝いなどをした時に与えるお金や菓子のことをいうようになりました。 | |||
| 一言既に出ずれば駟馬も追い難し | |||
| |||
| 馬は馬方 | |||
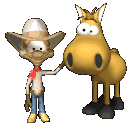 馬方はウマに人や荷物を運ばせる仕事をする人。
馬方はウマに人や荷物を運ばせる仕事をする人。慣れない素人がウマを扱おうとしてもウマは言うことを聞かないが、ウマを扱うことを職業としている人が扱えば意のままに動かすことができます。 そこから、その道の専門家は専門家だけのことはあるということです。 | |||
| 内で掃除せぬ馬は外で毛を振る | |||
| |||
| 肥馬の塵を望む | |||
 「肥馬」は肥え太っているウマで、「塵を望む」は肥馬に乗って外出する貴人のあとから塵を浴びてお供をする、貴い人の来往を遠くから見て礼拝する、おもねり媚びることをいいます。
「肥馬」は肥え太っているウマで、「塵を望む」は肥馬に乗って外出する貴人のあとから塵を浴びてお供をする、貴い人の来往を遠くから見て礼拝する、おもねり媚びることをいいます。そこから、金持ちや身分の高い人のご機嫌をとり従うさまや、権勢のある者の力のおすそわけを望むことをいいます。 | |||
| 篤(トク) | |||

「馬がゆっくり歩く」「行きづまる」「人情があつい」「真心がある」「熱心」「病が重い」「手厚くする」の意の漢字。
| |||
| 胡馬北風に嘶く(こばほくふうにいななく) | |||
 北方の胡の地に生まれ育ったウマは、他国にあっても北風が吹くごとに故郷を慕っていななくということから、故郷の忘れがたいことのたとえです。
北方の胡の地に生まれ育ったウマは、他国にあっても北風が吹くごとに故郷を慕っていななくということから、故郷の忘れがたいことのたとえです。
| |||
| 騎(キ) | |||
 「ウマにまたがること」「またがること」「乗用のウマ」「ウマに乗った兵を数える単位」の意の漢字。
「ウマにまたがること」「またがること」「乗用のウマ」「ウマに乗った兵を数える単位」の意の漢字。
馬と奇の合字。 奇は不安定、かぎ型に曲るということで、ウマに重みをかけること、足を曲げウマに乗ることを意味します。 | |||
| 長鞭馬腹に及ばず | |||
|
どんなに力や技量があっても及ばないものがあるということです。 | |||
| 鞍掛馬の稽古(くらかけうまのけいこ) | |||
 乗馬の練習は鞍掛馬(乗馬の稽古用の木馬)ではなく、実際にウマに乗ってこそ上達もするものだ、ということです。
乗馬の練習は鞍掛馬(乗馬の稽古用の木馬)ではなく、実際にウマに乗ってこそ上達もするものだ、ということです。豊富な知識がどんなにあっても、実際に役に立たなければ何の価値もないということです。 | |||
| やせ馬の先走り | |||
| |||
| 隣の馬も借りたら一日 | |||
|
| |||
| 驥尾に附す(きびにふす) | |||
 驥は一日に千里を走るという駿馬のこと。
驥は一日に千里を走るという駿馬のこと。優れた人に従えば事を成し遂げられる、先達を見習って行動する、という意味で、自分の行為を謙遜していうことばです。 | |||
| 馬に乗るとも口車に乗るな | |||
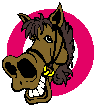 巧みな言葉やうまい話には注意が必要で、絶対に騙されてはいけないという戒めの言葉です。
巧みな言葉やうまい話には注意が必要で、絶対に騙されてはいけないという戒めの言葉です。「口車」は人を騙す巧みな弁舌で「馬に乗るとも」は口調を整える語です。 | |||
| 裸馬の捨て鞭 ( はだかうまのすてむち ) | |||
| |||
| 驕(キョウ) | |||
 「おごる」「背伸びして人の上に出る」「おごり高ぶる」「人を見下す」の意の漢字。
「おごる」「背伸びして人の上に出る」「おごり高ぶる」「人を見下す」の意の漢字。
馬と喬の合字。 喬は高く伸びて先が曲がるという意味で、ウマが首を高く上げるさま、そこから見下げるの意味も持ちました | |||
| 駑馬十駕(どばじゅうが) | |||
 駑馬が10日間馬車を引くことで、歩みがのろく劣ったウマでも、10日かかれば優れたウマが1日分行くだけは進めるということ。
駑馬が10日間馬車を引くことで、歩みがのろく劣ったウマでも、10日かかれば優れたウマが1日分行くだけは進めるということ。
そこから、才能のないものでも努力すれば、優れた者に追い付くことができるということです。 | |||
| 千里の馬は常に有れども伯楽は常に有らず | |||
 伯楽は天馬を司る星の名、それがあだ名になった、春秋時代周の馬の鑑定の名人のこと。 そこから人物を見抜き、能力を引き出し育てるのがじょうずな人をいうようになりました。 | |||
| 意馬心猿(いばしんえん) | |||

仏教用語で、ウマが走り回ったり、サルが騒ぎ立てていることを制するのが難しいように、煩悩や情欲のために心が乱れることは抑え難いということだというです。 | |||
| 荒馬のくつわは前から | |||
 思いきって正面からくつわをとれば、あばれウマもおとなしくなります。
思いきって正面からくつわをとれば、あばれウマもおとなしくなります。困難なことには小細工をせずに、思い切って大胆に堂々と正面からぶつかれということです。 | |||
| 腐り縄に馬つなぐ如し | |||
|
とうてい成功しないことなどにいいいます。 | |||
| 空馬(からうま)に怪我なし | |||
| |||
| 毛を見て馬を相す | |||
|
言葉だけで人を評価してはいけないということです。 | |||
| 癖ある馬に能あり | |||
 癖を持つウマは他の馬以上の長所を持つといいます。
癖を持つウマは他の馬以上の長所を持つといいます。同じように人も一癖ある人物には優れた点があるというたとえです。 また、才能ある者はどこか凡人とは違うところがあるということでもあります。 | |||
| 馬のもの覚えたよう | |||
 ウマは一回覚えた一つの経験をいつまでも忘れないことから、一度覚えたことをいつまでも忘れないことをいいます。
ウマは一回覚えた一つの経験をいつまでも忘れないことから、一度覚えたことをいつまでも忘れないことをいいます。
| |||
| 駑馬に鞭打つ | |||
|
そこから、能力はないが精一杯努めるつもりである、 ということを謙遜していう言葉になりました。 | |||
| 駿馬痴漢を乗せて走る ( しゅんめちかんをのせてはしる ) | |||
| |||
| 子馬の朝勇み | |||
| |||
| 書を以て御する者は馬の情を尽くさず | |||
 書物で得た知識だけでウマを乗りこなそうとする者は、ウマの癖や気持ちまで察してようとしないから、上手く乗りこなすことはできません。実践を伴わない机上論では実務にあまり役立たないということです。
書物で得た知識だけでウマを乗りこなそうとする者は、ウマの癖や気持ちまで察してようとしないから、上手く乗りこなすことはできません。実践を伴わない机上論では実務にあまり役立たないということです。
| |||
| 験(ケン) | |||

「ためす」「ためし」「調べる」「試しの手段」「試験」「しるし」「えんぎ」「良し悪しや真偽を試してみる」「証拠」の意の漢字。
馬と僉の合字。 | |||
| 竹馬の友 | |||
 一緒に竹馬に乗って遊んだ幼友達のこと。
一緒に竹馬に乗って遊んだ幼友達のこと。竹馬(チクバ)はタケウマではなく、葉のついた笹竹に手綱がわりの紐をつけたもので、これにまたがり走り回って遊ぶものです。 幼時からのライバルを蹴落とした武将が相手を評し、「彼は、自分が捨てた竹馬を拾って遊んでいた。もとから私の下風に立つべき人物なのだ」と語った中国の故事に由来する言葉で、本来の意味はライバルのことでした。 | |||
| 勝ち馬に乗る | |||
|
| |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |