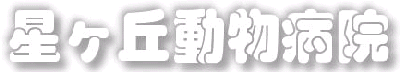|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 聖牛 | |||
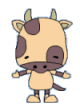
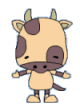
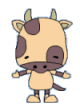
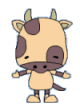
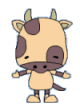 川の流れから堤防や河岸を守るための施設の一種で、雑木を結んで棟木のようにし、その間に柵を作り蛇籠を何本も並べたもの。
杭を組んだ形が2本の角を持っているように見えることから「牛」の名前が付けられたといわれています。
川の流れから堤防や河岸を守るための施設の一種で、雑木を結んで棟木のようにし、その間に柵を作り蛇籠を何本も並べたもの。
杭を組んだ形が2本の角を持っているように見えることから「牛」の名前が付けられたといわれています。
武田信玄の創案になるものといわれ山梨県内に施工されたが、信玄の勢力圏拡大に伴って周辺地域に広まり、享保年間以後は各地に流布することになりました。 | |||
| 牛は角を見て買い、人は言を聞いて用う | |||
|
ウシは角によってその良否がわかるように、人の良否はその語り口や内容によって分かるものだということです。
| |||
| 食牛の気 | |||
 トラやヒョウは、子どもの時から自分より大きなウシを食おうとするほどの激しい気性を持っているということです。
トラやヒョウは、子どもの時から自分より大きなウシを食おうとするほどの激しい気性を持っているということです。
そこから幼い頃から大きな目標を抱いていることのたとえになりました。「牛を食らうの気」ともいいます。 | |||
| 牛は願いから鼻を通す | |||
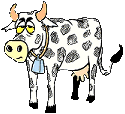 ウシはその天性によって鼻木を通される、ということです。
ウシはその天性によって鼻木を通される、ということです。
ウシが鼻輪を通されて自由を失うのは、そうしなければ従わないウシの天性が招いたものであるということで、みずから望んで災いや苦しみを受けることのたとえです。 | |||
| ずるい事は牛でもする | |||
|
| |||
| 黒牛白犢を生む | |||
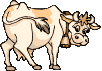 白犢(はくとく)は白い子ウシのこと。
白犢(はくとく)は白い子ウシのこと。黒いウシが白い子ウシを生むということで、この世のめぐり合わせ、吉凶禍福はどう変わるかわからない。吉が必ずしも吉でなく、凶も必ずしも凶ではないことをいいます。 | |||
| ブルペン 「bullpen」 | |||
 野球場にある、ピッチング練習する練習場で、室内、室外両方あり、プロ野球などでは、試合前は先発ピッチャーが練習し、
試合開始後はリリーバーが練習や肩を作ったりスタンバイ場所となっています。
野球場にある、ピッチング練習する練習場で、室内、室外両方あり、プロ野球などでは、試合前は先発ピッチャーが練習し、
試合開始後はリリーバーが練習や肩を作ったりスタンバイ場所となっています。
意味は直訳すると「雄牛の囲い」です。 語源には二つの説があり、一つはマウンドに向かう前の投球練習をするピッチャーを、 闘牛が闘牛場へ行く前の控えの囲いに見立てたというもの。 もうひとつは、「Bull Durham」というタバコ会社の看板がよく投球練習上のフェンスに立てられていたためというものです。 | |||
| 陶器屋に闖入した雄牛 | |||
 ”like a bull in a china shop”
”like a bull in a china shop”bullは去勢していないオスウシのことで、乱暴で破壊力があるイメージがあります。そのウシが陶器店に迷い込んで暴れる、ということを思わせることわざです。 そこから物を壊す人や、慎重な判断やふるまいが必要な状況でよく失敗したり損害を招いたりする人のことをいいます。また、はた迷惑な乱暴者、粗忽者のこともいいます。 | |||
| 卵を盗む者は牛も盗む | |||
 小さな悪事をはたらいた者は、いずれ大きな犯罪を犯すようになるということです。
小さな悪事をはたらいた者は、いずれ大きな犯罪を犯すようになるということです。
そうならないためにも、小さな悪事も見逃さずに戒めるべきである、ということでもあります。 | |||
| 牛の玉 | |||
 ウシの額に生える毛の固まったようなもので、直径3センチほどの丸さで、中に堅い芯があります。牛王(ごおう)ともいい社寺などの宝物とされています。
ウシの額に生える毛の固まったようなもので、直径3センチほどの丸さで、中に堅い芯があります。牛王(ごおう)ともいい社寺などの宝物とされています。
またウシの腹中にできる玉で胆石のことでもあり、宝物とされました。これを乾燥させてたものは、 牛黄(ごおう)として古くから黄金より高価な薬とされています。 | |||
| 牛羊(ごよう)の目をもって、他人を評量するなかれ | |||
|
自分の基準で他人を批判してはいけないというおしえです。 | |||
| 牛乳を飲む人よりも、牛乳を配達する人のほうが健康である | |||
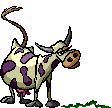 ヨーロッパのことわざです。文字通り栄養を摂るだけではなく、汗水たらして身体を動かして働いている方が健康だということです。
ヨーロッパのことわざです。文字通り栄養を摂るだけではなく、汗水たらして身体を動かして働いている方が健康だということです。また別の解釈では、与えられることに慣れてしまう側に立つよりも、与える側に回って一生懸命頑張るほうが得るものが大きい、というものもあります。 | |||
牛蹄の (しん)には尺の鯉無し (しん)には尺の鯉無し | |||
 ウシの足跡にたまった水たまりに、一尺もある鯉はいないという意味から、狭苦しい所では、大人物は手腕を振るうことが出来ないということです。
ウシの足跡にたまった水たまりに、一尺もある鯉はいないという意味から、狭苦しい所では、大人物は手腕を振るうことが出来ないということです。
牛蹄とは牛の足跡のことで、  (しん)は水たまりのことです。尺は約30cmです。 (しん)は水たまりのことです。尺は約30cmです。
| |||
| 丑の時参り(うしのときまいり) | |||
 丑の刻参り、丑の時詣で、丑参りともいい、憎いと思う人を呪い殺す方法で、主に嫉妬深い女性のすることとされたそうです。
丑の刻参り、丑の時詣で、丑参りともいい、憎いと思う人を呪い殺す方法で、主に嫉妬深い女性のすることとされたそうです。七日目満願の日に、のろわれた人は死ぬと信じられていたそうですが、その姿を人に見られると効果がなくなるとされていました。 丑の刻(午前二時頃)に神社や寺に参詣し、白衣を着て頭に五徳をのせ、足に蝋燭(ろうそく)を挿して火をともし、胸に鏡をさげ、手に金づちと釘を持ち、相手をかたどった人形を鳥居や神木に打ちつけたそうです。 | |||
| 件(ケン) | |||

「分ける」「くだり」「ことがら」「くだん・前に言ったり書いたりした物事」「いつもの」の意の漢字。 | |||
| 遅牛も淀早牛も淀 | |||
|
京を出たウシは速さは違っても結局は淀に着くように、遅い早いの違いはあっても、行き着くところは同じであるということです。 また、行く先が同じなら結果も同じであるということでもあります。 | |||
| 浮き世は牛の小車 (うきよはうしのおぐるま) | |||
|
「牛」を「憂し」に掛けており、「小車」は回転が速い小さな車のこと。略して「浮き世は車」ともいいます。 | |||
| 伏せる牛に芥(あくた) | |||
 寝ているウシの上にごみをかけるように、弱い者や死んでしまった者に、これ幸いと罪をかぶせること。
寝ているウシの上にごみをかけるように、弱い者や死んでしまった者に、これ幸いと罪をかぶせること。また、なんにも関係もない知らない他人に罪をなすりつけることもいいます。 | |||
| 牛に乗って牛を尋ねる | |||
|
| |||
| 牛の籠抜け | |||
 籠抜けは建物の入り口で客から金品を預かり、別の出口から素早く逃げ去ってしまう詐欺の手口のこと。
籠抜けは建物の入り口で客から金品を預かり、別の出口から素早く逃げ去ってしまう詐欺の手口のこと。この詐欺には機敏な行動が必要ですが鈍重なウシにはとてもできない、ということから、のろまな者には問題の迅速な処理は無理、また、ものごとを行なうのに不手際であることのたとえになりました。 | |||
| 剣を売りて牛を買う | |||
 武事をやめて農業に力を尽くすこと。
武事をやめて農業に力を尽くすこと。 ある人が渤海の太守になって赴任して行ってみると、土地の人はぜいたくで農業をきらっていたので、 自分から田畑を作ってみせて農業をすすめ、刀剣を持っている者が多かったので剣を売ってウシをを買わせると、みな富貴となったという中国故事より。 | |||
| 牛に対して琴を弾ず | |||
 中国、魯の国の公明儀がウシの前で琴の名曲を弾いて聞かせたが、ウシは知らぬ顔で草を食っていたが、蚊やあぶの羽音、子ウシの鳴き声に似せた音を出したところ、耳をそばだてたという故事から。
中国、魯の国の公明儀がウシの前で琴の名曲を弾いて聞かせたが、ウシは知らぬ顔で草を食っていたが、蚊やあぶの羽音、子ウシの鳴き声に似せた音を出したところ、耳をそばだてたという故事から。
立派な道理を説いて聞かせても、志の低い者や愚かな者には何の役にも立たないということです。 | |||
| 牛の糞みたいな奴 | |||
|
そこから、外見だけでは判断できず一筋縄ではいかない、油断のできない人のことをいいます。 | |||
| 牢(ロウ) | |||

「おり」「家畜を飼う所」「かこむ」「かこい」「人・罪人を閉じ込める所」「牢獄」「いけにえ」「堅いころ(堅牢)」「かたく守る」の意の漢字。
| |||
| 二十坊主に牛のふぐり、五十坊主に鹿の角 | |||
|
| |||
| 蚊虻牛羊を走らす(ぶんぼうぎゅうようをはしらす) | |||
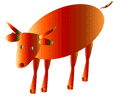 カやアブのような小さな虫が、ウシやヒツジのような大きな動物にたかって、かゆくて走る出すように、弱小のものが強大なものを動かすことをいいます。
カやアブのような小さな虫が、ウシやヒツジのような大きな動物にたかって、かゆくて走る出すように、弱小のものが強大なものを動かすことをいいます。
小さな物でも油断をしていると、それが禍となり大害を引き起こすことがあるというたとえです。 | |||
| 牛の小便と親の意見 | |||
| |||
| 牛売って牛にならず | |||
|
| |||
| 年寄りの言う事と牛の尻繋(しりがい)は外れない | |||
 経験に裏打ちされた老人の知識や考え方は尊いもので、間違いや見当はずれが少なく、正しいものであるということです。
経験に裏打ちされた老人の知識や考え方は尊いもので、間違いや見当はずれが少なく、正しいものであるということです。
しりがいはウシやウマの尻に掛けて、車との固定するもので、なかなか外れないようになっています。 | |||
| 一牛鳴地 | |||
|
| |||
| 画工闘牛の尾を誤って牧童に笑われる | |||
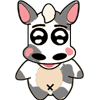 闘牛は股の間に尾をはさんで戦うが、尾を振って戦っている闘牛の絵を珍重していた男が、牧童にそれを笑われてその絵を燃やしてしまったという中国宋の故事。
闘牛は股の間に尾をはさんで戦うが、尾を振って戦っている闘牛の絵を珍重していた男が、牧童にそれを笑われてその絵を燃やしてしまったという中国宋の故事。
実物をよく観察した上でないと、とんだ失敗をするということで、そこから、無学な者でも、専門の事に詳しい知識をもつ者からは教えを受けるべきだ、というたとえに使われます。 | |||
| 学は牛毛のごとく、成るは麟角(りんかく)のごとし | |||
 ウシの毛はとても多く、キリンの角は少ないことから。
ウシの毛はとても多く、キリンの角は少ないことから。学問を志す人は多いけれど、その学問がきちんと身につく人は少ないということです。 | |||
| 弱牛の尻押し | |||
|
| |||
| 痩せ牛も数たかれ | |||
|
| |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |