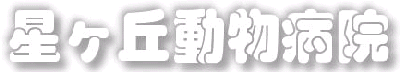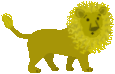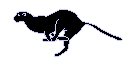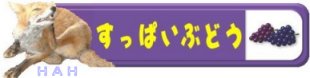|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 古だぬき・古狸 | |||
 年をとったタヌキのことで、化けたり人を騙したりする力を持つとされています。
年をとったタヌキのことで、化けたり人を騙したりする力を持つとされています。そこから、年をとって、経験を積み、悪がしこくなったり、ずるがしこくなった人をいいます。 | |||
| 分福(ぶんぶく)茶釜 | |||


群馬県の館林市に実在する茂林寺に伝わる民話です。 昔々、ある一人の貧しい男性がワナにかかったタヌキを助けてあげました。その夜、タヌキは男性のもとへやってきて、お礼に自分が茶釜に化けるからそれを売ればいいと言いました。あくる日、男性はタヌキが化けた茶釜をお寺の和尚さんに売りました。和尚さんは茶釜を持ち帰り、さっそく水を入れて火にかけました。すると「あ、あちち。あつーい!」タヌキはあまりの熱さに耐え切れず、半分もとの姿に戻ったまま男性のところに逃げ帰りました。そしてタヌキはこんな提案をしたのです。「茶釜が曲芸を披露するお店を開こう。」そうして、タヌキは毎晩お客さんの前で綱渡りをやってみせました。茶釜が綱渡りをする、といううわさはたちまち人々の間に広まり、お店は大盛況!楽しんでいるお客さんを見て、タヌキは大喜びです。もちろん、貧乏だった男性も大金持ちになりました。しかし茶釜に化けたタヌキが、もとの姿に戻ることは二度とありませんでした。そして福を分け与えるという意味で分福茶釜と名付けられました。 | |||
| 戦狼外交 | |||
 21世紀に入り中国の外交官が採用したとされる、より過激で攻撃的な外交スタイルのことで、主に西側諸国との間において、貿易摩擦や人権問題などの領域で用いられています。
21世紀に入り中国の外交官が採用したとされる、より過激で攻撃的な外交スタイルのことで、主に西側諸国との間において、貿易摩擦や人権問題などの領域で用いられています。
強硬な姿勢や攻撃的な言動を使い自国の利益を強く主張し、外交交渉や対話による解決を拒否する傾向があります。 中国のアクション映画「戦狼 ウルフ・オブ・ウォー」に由来する造語です。 | |||
| 狐につままれたよう | |||
 どうしてそうなったのか意外でただ呆れている様子や、前後の事情がさっぱりわからず、ぼんやりするさまを表します。
到底信じられない、化かされたような感じがする、といった意味をたとえていう言い回しです。「つままれる」とは化かされるという意味です。
どうしてそうなったのか意外でただ呆れている様子や、前後の事情がさっぱりわからず、ぼんやりするさまを表します。
到底信じられない、化かされたような感じがする、といった意味をたとえていう言い回しです。「つままれる」とは化かされるという意味です。
| |||
| 野狐禅(やこぜん) | |||
 禅の修行者が、まだ悟り切っていないのに悟ったつもりになってうぬぼれることを、野狐にたとえていう言葉です。
そこから、禅に似て非なる邪禅のことや、生半可な知識で物事を理解したような顔でうぬぼれている人のことをいいます。
禅の修行者が、まだ悟り切っていないのに悟ったつもりになってうぬぼれることを、野狐にたとえていう言葉です。
そこから、禅に似て非なる邪禅のことや、生半可な知識で物事を理解したような顔でうぬぼれている人のことをいいます。野狐(やこ)とは低級な妖狐の1つです。 | |||
| 狐日和(きつねびより) | |||
|
なかなか一定しない天気のことをいいます。 | |||
| 狸から上前 | |||
| |||
| The quick brown fox jumps over the lazy dog. | |||
 「素早い茶色のキツネはのろまなイヌを飛び越える」は、英語のパングラムの一つです。
「素早い茶色のキツネはのろまなイヌを飛び越える」は、英語のパングラムの一つです。パングラムとは「いろは歌」のように、ある言語に存在する言葉をすべて使い、かつ重複をなるべくなくした短文のことです。 英語で特に有名なのがこの文章で、すべてのアルファベットを表現でき、文法が自然なのでタイプライターやコンピューターのキーボードの試験などによく用いられます。 ただし、これには複数回使われている語があります。 | |||
| 千金の裘は一狐の腋に非ず(せんきんのきゅうはいっこのえきにあらず) | |||
 裘(きゅう)はキツネの腋の下の白い毛皮で作った高価な衣。
裘(きゅう)はキツネの腋の下の白い毛皮で作った高価な衣。千金の価値のある高価な皮の衣は、一匹のキツネのわずかな白い毛だけでは出来ないという意味から、 国を治めるにはすぐれた人材を多く集め、それらの人々の力を集めなければならないというたとえです。 | |||
| 城狐社鼠 ( じょうこしゃそ ) | |||
| |||
| 狐之を埋めて狐之をあばく | |||
|
そこから、疑い深い人は自分で始めた物事を自分の手でぶちこわしてしまう、ということをいいます。 | |||
| 獅子は小虫を食わんとてもまず勢いをなす | |||
 百獣の王と言われる獅子は、弱い獲物を捕らえるにも油断なく力を抜かずに全力で向かうことから、すぐれた人物はどんな事にでも細心の注意を払い最善を尽くすものだ、ということです。
百獣の王と言われる獅子は、弱い獲物を捕らえるにも油断なく力を抜かずに全力で向かうことから、すぐれた人物はどんな事にでも細心の注意を払い最善を尽くすものだ、ということです。
| |||
| 狐憑き(きつねつき) | |||
 キツネの霊に取り憑かれたといわれる人の精神の異常な状態をいいます。また、そのような精神状態にある人、そのような事が起こり得ると信じる信仰や迷信のこともいいます。
キツネの霊に取り憑かれたといわれる人の精神の異常な状態をいいます。また、そのような精神状態にある人、そのような事が起こり得ると信じる信仰や迷信のこともいいます。
昔から特に女性に多く、自分がキツネになったつもりで種々の事を口走り動作します。キツネを落とすには行者や神職を招いて松葉いぶしなどの呪術を行いました。 | |||
| 獅子も頭の使いがら | |||
 お祭りの獅子舞いは、頭(獅子頭)を振る人の上手下手によって良し悪しが決まることから、先頭に立つ指導者の働きが重要であるということです。
お祭りの獅子舞いは、頭(獅子頭)を振る人の上手下手によって良し悪しが決まることから、先頭に立つ指導者の働きが重要であるということです。
| |||
| キツネ死して丘に首す(ししてきゅうにしゅす) | |||
|
キツネは丘の穴に住んでいるので、死ぬときも首を丘の方に向けて死ぬという意味で、 家を忘れないことのたとえ。また、故郷を思うことのたとえです。
| |||
| 落花狼藉(らっかろうぜき) | |||
 落花とは花が散り乱れて地面に落ちることで、狼藉とはオオカミが草を敷いて寝た跡の意味から、多くのものが秩序なく入り乱れて散乱しているさまのことをいいます。
落花とは花が散り乱れて地面に落ちることで、狼藉とはオオカミが草を敷いて寝た跡の意味から、多くのものが秩序なく入り乱れて散乱しているさまのことをいいます。
女性を花に見立て女性に狼藉(乱暴)を働くということです。 | |||
| 狐裘蒙戎 (こきゅうもうじゅう) | |||
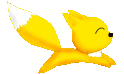 高貴な人が着るキツネの皮ごろもの毛が乱れるという意味から、身分の高い人が礼儀・作法を忘れ、常軌を逸して国政が乱れているということを表します。
高貴な人が着るキツネの皮ごろもの毛が乱れるという意味から、身分の高い人が礼儀・作法を忘れ、常軌を逸して国政が乱れているということを表します。「狐裘」はキツネの腋の下の白い毛皮で作った高価な皮ごろも。「蒙戎」は乱れた様子。 | |||
| 獅子屈中に異獣なし(ししくっちゅうにいじゅうなし) | |||
|
| |||
| 狼に衣 | |||
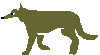 | |||
| 獅子の座(獅子座) | |||
|
| |||
| 一狐裘三十年(いっこきゅうさんじゅうねん) | |||

狐裘(こきゅう)とはキツネのわきの下の皮を集めて作った白い皮衣のこと。
| |||
| 獅子の分け前 | |||
|
強いライオンが弱い動物たちを働かせて、その成果を一人占めし、働いたものにはちっとも分け前を与えない、というイソップ寓話。 強い者が利益を独占することのたとえ。また、身近な者の不運や災難は、人に処世の知恵を与えるということ。
| |||
| きつね焼き | |||
|
| |||
| 同じ穴の狢(ムジナ) | |||
|
タヌキ・キツネなどイヌ科の中型獣やアナグマ・テンなどのイタチ科の中小型獣の個体群を「ムジナ」と表現しています。 | |||
| 羊の皮を被った狼 | |||
 新約聖書で「偽預言者を警戒しなさい。彼らはヒツジの皮を身にまとってあなたがたのところに来る。」とあるそうです。
新約聖書で「偽預言者を警戒しなさい。彼らはヒツジの皮を身にまとってあなたがたのところに来る。」とあるそうです。
一見ヒツジのように大人しいけれど、実はオオカミのように恐ろしい、温良を装った悪者、 偽善者、 腹黒い人という意味です。 | |||
| 鹿待つところの狸 | |||
 シカを射ようと思って待っているところにタヌキが出てきたので、それを捕るということから。
シカを射ようと思って待っているところにタヌキが出てきたので、それを捕るということから。
期待に反してつまらないものを手に入れることで、どんなにつまらぬものでも獲物が何もないよりはましであるということです。 | |||
| 管豹の一斑(かんぴょうのいっぱん) | |||


 管の中からヒョウを覗き、まだら模様の一部分だけを見ているということで、物の見方や見識がたいそう狭いことのたとえです。
管の中からヒョウを覗き、まだら模様の一部分だけを見ているということで、物の見方や見識がたいそう狭いことのたとえです。
| |||
| 狐疑逡巡(こぎ しゅんじゅん) | |||
|
| |||
| 狸の腹鼓(タヌキのはらづつみ) | |||
 タヌキは月の夜に、腹をたたいて楽しむという昔話で、たぬきばやしともいいます。
タヌキは月の夜に、腹をたたいて楽しむという昔話で、たぬきばやしともいいます。 狂言には、老尼に化けたタヌキが猟師に殺生の恐ろしさを説くが、正体を見破られて命乞いのために腹鼓を打つ、という話があります。 囲碁では一線に並ぶことによって敵石の手数が増えることを防ぐ攻め合いの手筋をいいます。 | |||
| 獅子の歯噛み | |||
|
| |||
| 狐が下手の射る矢を恐る | |||
 下手な者の射る矢はどこへ飛ぶかわからないので、上手が射る矢よりかえって始末が悪く、賢いキツネもどこに逃げてよいか困ります。
下手な者の射る矢はどこへ飛ぶかわからないので、上手が射る矢よりかえって始末が悪く、賢いキツネもどこに逃げてよいか困ります。
正常な人は相手にできるが、無茶な者は相手にしにくいということです。 | |||
| 狼子野心(ろうしやしん) | |||
| |||
| 獅子奮迅(ししふんじん) | |||
|
「獅子奮迅の活躍」として用いられます。 | |||
| 狐の子は頬白(つらじろ) | |||
|
| |||
| イタチの道切(みちき)り | |||
 イタチの通路を遮断することやイタチが目の前の道を横切ることをいいます。イタチは決まった道だけを通る習性ですが、遮断されると同じ通路を二度と通らないといいます。また、イタチが道を横切ると凶事が起こるという迷信があります。
そこから往来、交際、音信などの絶えることのたとえとしてもいいます。
イタチの通路を遮断することやイタチが目の前の道を横切ることをいいます。イタチは決まった道だけを通る習性ですが、遮断されると同じ通路を二度と通らないといいます。また、イタチが道を横切ると凶事が起こるという迷信があります。
そこから往来、交際、音信などの絶えることのたとえとしてもいいます。
| |||
| 狐その尾を濡らす | |||
|
非力な子狐が川を渡る時に、最初のうちは尾を高く揚げているが、やがて力尽き水に濡らしてしまいます。 | |||
| 獅子吼 ( ししく ) | |||
|
| |||
| 焼き餅焼くなら狐色 | |||
|
| |||
| イタチごっこ | |||
 いつまでやってもキリが無いようなことを表わします。
いつまでやってもキリが無いようなことを表わします。
何人かが向かい合って手を出し、その手の甲を順番につねる。つねっている手の甲をさらに上からつねる…という具合に上へ上へと行くだけでいつまでも続く遊び。この時「いたちごっこ、ねずみごっこ」と言いながら遊んだのが語源とされてます。 昔はイタチやネズミがごく身近な動物で、噛み付く様子が手の甲をつねるのに似ていたことと、農作物にとっては天敵であるそれらを、つねることで駆除するような意味・願いもあったといいます。 | |||
| 一匹狼 | |||
 群れを離れて一匹だけで暮らす狼のこと。
群れを離れて一匹だけで暮らす狼のこと。そこから集団に属さず独自の立場で行動する人をいうようになりました。 | |||
| 狸が人に化かされる | |||
|
だまそうとして反対にだまされることや、甘く見た相手からしてやられる、ということを表します。 | |||
| 獅子の子落し | |||
 獅子は 子が生まれて三日経つとその子を千尋の谷へ突き落とし 生き残った子だけを育てるという言い伝えから、子供を厳しく鍛え育てることを表します。
獅子は 子が生まれて三日経つとその子を千尋の谷へ突き落とし 生き残った子だけを育てるという言い伝えから、子供を厳しく鍛え育てることを表します。
もとは古い中国の故事で、獅子とは清涼山という山に棲む架空の聖獣のことですが、歌舞伎で定番の連獅子から、実在のライオンとの混同が始まったらしいです。 | |||
| おのが字の つくりを食らう 狐かな | |||
 江戸時代の俳人、野々口立圃(ののぐちりゅうほ)の句。
江戸時代の俳人、野々口立圃(ののぐちりゅうほ)の句。逸話では、農家に頼まれて瓜畑(うりばたけ)を荒らすキツネを戒めるため、立圃はこのような句の立て札を作ったそうです。 これが効いたのか、その後キツネはピタリと畑を荒らさなくなったといいます。昔は字を読んで内容を理解するキツネもいた? | |||
| キツネに小豆飯(あずきめし) | |||

「猫に鰹節」と同じ意味で、好物を前に置いておくとすぐ手を出すから油断ができないということ。 | |||
| キツネが落ちる | |||
 キツネの霊に取り付かれたような病気(精神病)が治り、
キツネの霊に取り付かれたような病気(精神病)が治り、正常に戻ること。 キツネつきの状態から、普通の状態に戻ること。 | |||
| 狼煙(ノロシ) | |||
 敵襲などの変事の急報のために、高く上げる煙や火。
敵襲などの変事の急報のために、高く上げる煙や火。古くは草や薪を燃し、後には、火薬を用いた花火のようなものもあったそうです。 中国ではオオカミの糞(ふん)は燃料としても使われていたが、火に加えると煙が真っ直ぐに上がるのでノロシには最適ということから、狼煙という文字が使われるようになりました。 | |||
| 狸親父(タヌキオヤジ) | |||
 世故にたけた悪賢い男をののしっていう場合に使います。
世故にたけた悪賢い男をののしっていう場合に使います。たぬきじじいともいいます。 | |||
| 鎌イタチ | |||
 体を物にぶつけても触れてもいないのに、鎌で切ったような切り傷ができる現象のことで、かつては、イタチのような魔獣の仕業とされていました。
体を物にぶつけても触れてもいないのに、鎌で切ったような切り傷ができる現象のことで、かつては、イタチのような魔獣の仕業とされていました。
実際は、厳寒時小さな旋風などの中心に真空の部分が出来、人体が触れると気圧の差から、皮膚が切れたり出血することがあるのだそうです。 | |||
| Dandelion(ダンデライオン)タンポポ | |||
|
| |||
| イタチの最後っ屁(さいごっぺ) | |||
|
イタチが追い詰められて進退きわまると、悪臭を放ち、相手がひるむすきに逃げることから、窮地に追い詰められたときに使う非常手段を表わします。
| |||
| 狸(タヌキ)寝入り | |||
 都合の悪いときに眠ったふりをすること。
都合の悪いときに眠ったふりをすること。タヌキはおどろかされると気を失う習性がり、しばらくしてから逃げ去るといわれていました。昔の人はこの行動を人をだますためだと考えた事からいわれるようになりました。 | |||
| キツネにつままれる | |||
|
また、意外な事が起こって何が何だかわからず、 ぽかんとすることをいいます。 「キツネにつままれたような顔」のような言い方をします。 | |||
| 狐(キツネ)と狸(タヌキ)の化かし合い | |||


といわれるところから、 悪賢い者どうしが互いに だまし合うことのたとえになりました。 | |||
| 狐(キツネ)火 | |||
|
また、歌舞伎などで、人魂(ひとだま)やキツネ火に見せるために使う特殊な火のこともいいます。 | |||
| 狼藉(ろうぜき) | |||
|
中国では「藉」は、「敷く」や「踏む」「雑」などの意味があり、狼(オオカミ)が寝るために敷いた草の乱れた様子の意味から、物が散らかっている様子を意味するようになリました。
| |||
| 「ごんぎつね」 | |||
|
新美南吉が創作した童話。現在では小学校の国語教科書のほとんどに採用されているので、 子どもたちにとって「ごん」は最も有名(?)なキツネでしょう。読む人に深い感動を与え、色々な事を考えさせられますが、特にコミュニケーションというものがいかに難しいものであるかを語っているようです。
| |||
| 一斑(いっぱん)を見て全豹(ぜんぴょう)を卜(ぼく)す | |||
| |||
| 狼狽(ろうばい) | |||

「狼」はオオカミ、「狽」はオオカミに似た伝説の動物で、前足と後ろ足の長さが違うそうです。 そのため自分で歩くのは苦手でいつもオオカミの背に乗って2匹一緒だったため、離ればなれになった時ひどくあわてふためきました。 | |||
| 「キツネうどん」と「タヌキそば」 | |||
| |||
| キツネと酸っぱいブドウ | |||
|
| |||
| とらぬ狸(たぬき)の皮算用(かわざんよう) | |||

まだ捕らえていないタヌキの皮を売って、 | |||
| タヌキの置物 | |||

縁起物としてよく店先などに置いてあるものは、比較的性格の良い動物とされるタヌキを擬人化して、人間の理想像を象徴してるものだそうです。
いつも行く居酒屋のあのタヌキ。とても偉いやつだったんですね〜。 | |||
| 豹変(ひょうへん) | |||
|
豹(ひょう)の毛皮は秋になると、汚い毛が抜けて細い美しい毛並に変わるとこから、心や行いが、すっかりきれいに変わることをいいます。 | |||
| 虎の威をかる狐 | |||
|
権力のある者の威光を後ろだてにして、いばっている小人物のたとえ。 | |||
| キツネの嫁入り | |||
|
日が照っているのに雨の降ること。 | |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |