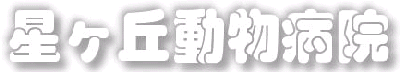|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 心猿 | |||
 
 

欲望を抑えることは難しいということです。 | |||
| 猿が仏を笑う | |||
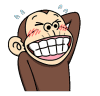 浅知恵しかない小利口なものが、深い知恵のある人の真の偉さをわからないで嘲笑することのたとえです。
浅知恵しかない小利口なものが、深い知恵のある人の真の偉さをわからないで嘲笑することのたとえです。
自分の小さな知恵では、知恵のある人の一部だけしか分かっていないことを、悟ることができない浅はかさを意味しています。 | |||
| 猿を決め込む | |||
 見ざる聞かざる言わざる、のことわざから。
見ざる聞かざる言わざる、のことわざから。知らぬ振りや、無視を決め込むという意味です。 | |||
| 猿に数珠見せたよう | |||
 サルに数珠を与えると、面白がっていつまでも数珠を爪繰(つまぐ)るといいます。
サルに数珠を与えると、面白がっていつまでも数珠を爪繰(つまぐ)るといいます。
そこからいつまでたっても同じことの繰り返しで果てしがない様子をいいます。 | |||
| 猿に烏帽子 | |||
| |||
| 猿の空蚤 | |||
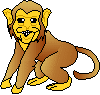 サルがいつもノミを取っているようなふりをしているが、本当は恰好だけで取っていないということです。
サルがいつもノミを取っているようなふりをしているが、本当は恰好だけで取っていないということです。そこから、用事や仕事があるふりをして実際は何もしていない様子のことをいいます。 | |||
| 猿が柿淡す | |||
 「淡(あわ)す」 は渋柿の渋を抜くこと。
「淡(あわ)す」 は渋柿の渋を抜くこと。サルが柿を食べるために渋を抜く時のようすをいいますが、 渋が抜けるまで待てないで、何度も出しては食べ、またもどすことをくりかえし、結局満足に甘い柿が得られないということです。 つまり、気が早くて 完成まで待てないことのたとえです。 | |||
| 九百九十九匹の鼻欠け猿、満足な一匹の猿を笑う | |||
|
| |||
| 猿は人間に毛が三筋足らぬ | |||
 サルは人間によく似て利口そうに見えるが、人間より毛が三本少ないので、それだけ知恵は浅いという俗説です。
サルは人間によく似て利口そうに見えるが、人間より毛が三本少ないので、それだけ知恵は浅いという俗説です。「サルは人間に毛が三本足らぬ」ともいいます。 | |||
| 猿に絵馬 | |||
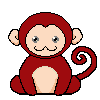 サルとウマを取り合わせた図柄が多いことから、取り合わせのよいもののたとえです。
サルとウマを取り合わせた図柄が多いことから、取り合わせのよいもののたとえです。
昔はサルを馬小屋の守護とする信仰があり、農家では「申」と書かれた紙を馬小屋に貼っていたり、正月や祭りではサルがウマをひくところの描かれた絵馬や神札が用いられていました。 ちなみに日光東照宮の有名な「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿の彫刻があるのは神厩舎、つまり馬小屋です。 | |||
| 木から落ちた猿 | |||
 頼みにするところやよりどころを失って、どうしたらいいか分からない状態のたとえです。
頼みにするところやよりどころを失って、どうしたらいいか分からない状態のたとえです。木の上では悠々と自由に動けるサルも、誤って木から落ちてしまうと身動きがとれなくなることに由来しています。 | |||
| 利口の猿が手を焼く | |||
|
| |||
| 猿が髭揉む(さるがひげもむ) | |||
|
| |||
| 百匹目の猿 | |||
 ある行動や考えなどがある一定数を超えると、これが接触のない同類の仲間にも伝播するという説。
ある行動や考えなどがある一定数を超えると、これが接触のない同類の仲間にも伝播するという説。
瀬戸内のある小島で一匹のサルがイモを洗う習慣を身に付け、それが集団内に広まっていくとある閾値を超えた次の日には群れ全体がイモを洗うようになり、さらにはまったく交流がないはずの他の島までこの文化が伝播した。 ※【例として報告されていた上記の有名な逸話は創作されたものでした。】 | |||
| 猿知恵(さるぢえ) | |||
|
気候や食料にも恵まれて、なに不自由ない島に、500匹のサルが住んでいました。 ある日1匹が、海が輝いているのを見て、海の向こうにはもっとすばらしい場所があるのではないかと思い、沖へ向かって泳いでいってしまいました。 その後、いつまでもそのサルが帰ってこないのを見たほかのサルは、そのサルが良い場所を見つけたと思い込んで同じように沖へ泳ぎ始め、500匹すべての行方が分からなくなってしまいました。 | |||
| 敵もさるもの引掻くもの | |||
|
| |||
| 毛のない猿 | |||

“からだに毛が生えていないことだけがサルとの違い” | |||
| 猿真似(さるまね) | |||
|
サルが人の動作をまねるように、他人の表面だけまねること。 | |||
| 猿酒 | |||
 野生の猿が果実や木の実を、樹木の穴や岩の窪みになどに蓄えておいたものに、雨や露が溜まり自然に発酵して酒のようになったもの。ましら酒。
野生の猿が果実や木の実を、樹木の穴や岩の窪みになどに蓄えておいたものに、雨や露が溜まり自然に発酵して酒のようになったもの。ましら酒。
実際にはそのようなものは無いらしく、山葡萄などの果物が熟し落ちたものが偶然の一致によって酒のように発酵したものを、山に入った猟師なとが偶然見つけて味わったのだといわれています。 | |||
| 霊長類 | |||

キツネザル、ツバイなどの原猿亜目とサル、類人猿、ヒトなどの真猿亜目とに分類されます。でもなぜ「霊長」なのでしょうか。
prime minister(総理大臣)というように最高位を表す言葉です。 | |||
| モンキー・レンチ (Monkey Wrench) | |||
|
「ハンドルが自由に動く様子がサルのおもちゃに似ているから」「サルでも使える工具だから」などという説もありますが、「発明者の名前(Charles Moncky)に由来する」という説が真実らしいです。 | |||
| 猿芝居 | |||
|
下手な芝居を馬鹿にしたり、あざけっていうこと。 あるいは、考えが浅く思慮の足りないおろかな考えのこと。 | |||
| 猿楽(さるがく) | |||

音楽・軽業・奇術や滑稽な物まねなどの古代の雑芸。 | |||
| 猿股(さるまた) | |||
 猿回しのサルにはかせた猿股引(ももひき)きから生じた言葉で、腰から股のあたりをおおうズボン型の男性用下着のことです。
猿回しのサルにはかせた猿股引(ももひき)きから生じた言葉で、腰から股のあたりをおおうズボン型の男性用下着のことです。
| |||
| サルスベリ(百日紅) | |||
| |||
| 猿の尻笑い | |||
|
サルが他のサルの尻の赤いのをさして笑うということで、自分の欠点に気が付かず、他人の欠点をとり上げてバカにするということです。
| |||
| 朝三暮四(ちょうさんぼし) | |||

「荘子」に載っているお話です。 | |||
| 猿猴(エンコウ)月を取る | |||
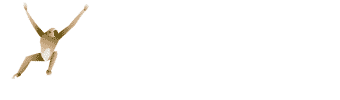
猿猴はサル、サルたちが、木の下の水面に映った月を取ろうとして、木の枝から手と尾をつないで数匹つり下がったところ、重みで木の枝が折れて、みんな落ちて溺れ死んだという仏典から生まれた言葉。 身の程をわきまえず、欲張ったまねをすると失敗し、災いを招くということです。 | |||
| 「サル」と「エテ」 | |||

猿の事を擬人化した表現に「エテ公」というものがありますが、エテという言葉自体に「猿」という意味は無く、忌(い)み言葉を避けるために作られた言葉といわれています。
| |||
| 猿も木から落ちる | |||
 その猿でも木から落ちることがあるように、どんなに上手な人でもいつでもうまくできるわけではなく、たまには失敗するということ。 | |||
| 見ざる・言わざる・聞かざる | |||
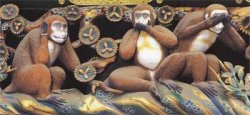
日光東照宮には、徳川家康公が関ヶ原の合戦で乗馬した馬を最初に奉納した、神厩舎があります。 | |||
| 動物小話 「動物園でとある親子の会話」 | |||

子:「あのサルは、隣のおばあさんによく似ているね。」 | |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |