|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 兎の罠に狐がかかる | |||
|
| |||
| 改竄(かいざん) | |||
|
ネズミの動作に対するイメージに由来し、「ネズミがこそこそ巣穴に入るように、文書にこっそり文字を入れたり消したりして書き換える」という発想から生まれたと考えられています。 そこでネズミが巣穴に入ることを表すのが、その本来の意味だとされています。 竄が「かくれる」「のがれる」「食い荒らす」といった意味はここから来ています。 | |||
| 驚喜するウサギ | |||
|
喜びに目がくらんで周りが目に入らなくなった人を揶揄する言葉です。 | |||
| 鼠と猫が仲良くなると八百屋は破産 | |||
| |||
| 兎の昼寝 | |||
 油断をして思わぬ失敗をすること。また昼寝ばかりする人のことを表す意味もあります。
油断をして思わぬ失敗をすること。また昼寝ばかりする人のことを表す意味もあります。日本には室町時代に伝わったとされる、イソップ寓話のウサギと亀で、ウサギが昼寝をして競争に負けた話に由来します。 | |||
| 兎を置く | |||
 相手が待ち合わせの約束を守らず、すっぽかされた時や、待ちぼうけを食らわせられた時にフランス人が使う言葉だそうです。
相手が待ち合わせの約束を守らず、すっぽかされた時や、待ちぼうけを食らわせられた時にフランス人が使う言葉だそうです。
「昨日は、カトリーヌにウサギを置かれたよ」のように使うそうです。 この表現は、16世紀頃から使われていたそうですが、今とは意味はずいぶん違っていました。 当時「兎を置く」は、娼婦のサービスを受けた後、お金を払わずに立ち去る事を表していたようです。 | |||
| 時に遇(あ)えば鼠も虎になる | |||
|
権力をふるうようになるというたとえです。 | |||
| 鼠の尾まで錐の鞘 | |||
 錐とは穴を開ける大工道具で鞘はそのカバーのことです。ネズミの尾みたいなものでも、錐の鞘として役に立つということです。
錐とは穴を開ける大工道具で鞘はそのカバーのことです。ネズミの尾みたいなものでも、錐の鞘として役に立つということです。
どんな下らないものでも工夫すれば役に立つということ。また、逆に工夫ではあるがケチのすることという意味もあります。 | |||
| 兎兵法 | |||
 本当の兵法を知らないでへたな策略をめぐらし 、
本当の兵法を知らないでへたな策略をめぐらし 、かえって失敗することをいいます。 そこから実用的でないことを意味します。 因幡の白ウサギの故事からきています。 | |||
| 兎のひり放し | |||
|
| |||
| ねずみ花火 | |||
| |||
| しめこの兎 | |||
 物事がうまくいったということをしゃれていうことばで、しめた、しめこのうさうさ ともいいます。
物事がうまくいったということをしゃれていうことばで、しめた、しめこのうさうさ ともいいます。
「うまくいった」の意の「しめた」に、ウサギを「絞(し)める」をかけています。 | |||
| 急ぐ鼠は雨に会う、急ぐ鼠は穴に迷う | |||
| |||
| 年劫の兎 | |||
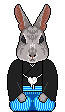 長い年月を生き抜いて悪賢くなったウサギのことで、一筋縄ではいかない人のことをいいます。
長い年月を生き抜いて悪賢くなったウサギのことで、一筋縄ではいかない人のことをいいます。
劫「ごう」とは仏教用語では「こう」と読み、仏教が説く時間のうちで最も長い単位のことで、比喩として以下の二つがあります 磐石劫:四十里四方の大石を、いわゆる天人の羽衣で百年に一度払い、その大きな石が摩滅して無くなってもなお終わらない時間。 芥子劫:方四十里の城に小さな芥子粒を満たして百年に一度、一粒ずつ取り去り、その芥子がすべて無くなってもなお尽きないほどの長い時間。 | |||
| 脱兎 | |||
|
孫氏の兵法にある「始めは処女の如く、後は脱兎の如し」からきています。 | |||
| 鼠口(そこう)ついに象牙なし | |||
|
| |||
| 兎の股引(ももひき) | |||
| |||
| 千金の弩は鼠の為に機を発たず | |||
| |||
| ただの鼠ではない | |||
|
| |||
| 鼠は大黒天(だいこくてん)の使い | |||

 ネズミは古代から人間の大切な穀物を荒らす憎い敵とみなされてきたが、時に予知能力への評価は高く、シロネズミは白色が吉兆とされ、福をもたらす七福神の一人の大黒天の使いとされました。
ネズミは古代から人間の大切な穀物を荒らす憎い敵とみなされてきたが、時に予知能力への評価は高く、シロネズミは白色が吉兆とされ、福をもたらす七福神の一人の大黒天の使いとされました。
| |||
| 月日の鼠 ( つきひのねずみ ) | |||
 | |||
| 兎の字 | |||
|
免職になったことの隠語です。 | |||
| 兎を得て罠を忘れる | |||
 ウサギを罠で捕まえたのに、罠のお陰で捕まえられたことは忘れてしまうことから、目的を果たしてしまうと手段にしていたものが不用になり忘れられる、道具には用が無くなるというたとえです。
ウサギを罠で捕まえたのに、罠のお陰で捕まえられたことは忘れてしまうことから、目的を果たしてしまうと手段にしていたものが不用になり忘れられる、道具には用が無くなるというたとえです。「魚を得て筌を忘る」と同じ意味です。 | |||
| 兎起鶻落(ときこつらく) | |||
 野ウサギが巣穴から素早く走り出したり、ハヤブサが獲物を捕らえようと急降下したりする様子のことです。
野ウサギが巣穴から素早く走り出したり、ハヤブサが獲物を捕らえようと急降下したりする様子のことです。そこから、書家の書画や文章の筆運びに非常な勢いがあることのたとえです。 | |||
| 鼠壁を忘れる 壁鼠を忘れず | |||
|
| |||
| 狡兎三窟 | |||
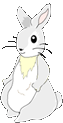 狡兎はすばしっこいウサギのこと。
狡兎はすばしっこいウサギのこと。ウサギは穴を3つ持っていて敵から追われた時、そのどれかに逃げ込んで身を助けるということから、 身を守るため、たくさんの避難場所やさまざまな策を用意しておくようにとの教えです。 また、ずる賢い者は用心深く、抜かりなく困難から逃れる手段を用意している、という意味もあります。 | |||
| 鼠が居なくなると火事になる | |||
| |||
| 兎兵法 | |||
 本当の兵法を知らないで、つまらない謀略を巡らして、
本当の兵法を知らないで、つまらない謀略を巡らして、かえって失敗することや実用的でないことをいいます。 因幡(いなば)の白ウサギの故事に基づきます。 | |||
| 寒の兎か白鷺か | |||
|
| |||
| 兎波を走る | |||
 月影が水面に映る様のたとえで、波が白く輝いているのがまるでウサギが走るように見えるところからこのようにいいます。
月影が水面に映る様のたとえで、波が白く輝いているのがまるでウサギが走るように見えるところからこのようにいいます。
また、ウサギは象や馬に較べ水に入る度合いの少ないことから、仏教の悟りに於いて浅い段階にとどまっている人のたとえの場合もあります。 | |||
| ネズミの嫁入り | |||
|
あるネズミが天下一の婿をとろうとしたが、候補者のそれぞれにさらに強いものがいることがわかり、結局、同類のネズミを婿にすることにしたという昔話です。 あれこれ迷っても結局は平凡なところに落ち着くものだということです。
| |||
| 兎の子生まれっぱなし | |||
|
| |||
| 鼠の子算用(さんよう) | |||
ネズミの子孫が増えるように際限なく増えたり広まっていくことです。 「ネズミ算式に増える」といった表現で使われることが多いようです。 | |||
| 猫の額にある物を鼠がうかがう | |||
|
大胆不敵でだいそれた望みをいだくことや、 身分をかえりみないことをいいます。 | |||
| 春の日に兎を釣るよう | |||
|
| |||
| 国に盗人家に鼠 | |||
|
内部の賊というものはどこにでもいるということです。 | |||
| 鼠尾馬尾鼠尾(そびばびそび) | |||
 酒や茶を注ぐ時は、一気に入れるのではなく、最初細く(ネズミの尾のように細く)ちょろちょろと、次に太く(ウマの尾のように太く)、最後にもう1度ネズミの尾にもどり細く注ぐように、ということ。
酒や茶を注ぐ時は、一気に入れるのではなく、最初細く(ネズミの尾のように細く)ちょろちょろと、次に太く(ウマの尾のように太く)、最後にもう1度ネズミの尾にもどり細く注ぐように、ということ。こうするとこぼれるなどの粗相なく、上手に注ぐことができますよ、という教えです。 | |||
| 兎の角 | |||
|
| |||
| 兎の毛でついたほど | |||
|
きわめてわずかなことや、ほんの少し、非常に小さい、 ということのたとえとして使われます。 | |||
| 兎に祭文(うさぎにさいもん) | |||
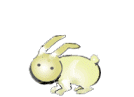
| |||
| 鼠は社に憑りて貴し | |||
 神社にネズミがいつ居てしまった場合、捕まえるのに神社を壊すわけにもいかず、燻りだそうとしても火事になるのを恐れ、ついついそのままにしてしまう。
神社にネズミがいつ居てしまった場合、捕まえるのに神社を壊すわけにもいかず、燻りだそうとしても火事になるのを恐れ、ついついそのままにしてしまう。
そこから、主君のそばで守られる奸臣のことや、小人が主君の威光をかさにきて威張っているというたとえです。 | |||
| 濡れ鼠(ネズミ) | |||
|
| |||
| 首鼠(しゅそ) | |||
|
| |||
| ウサギの登り坂 | |||
|
| なぶればウサギも食いつく | ||
|
| |||
| 鼠尾を支う(そびをかう) | |||
|
鼠尾は筆のこと。 | |||
| 兎の糞 | |||
|
また、兎糞とはウサギの糞のようなコロコロ便のこともいいます。(若い女性に多い、精神的なストレスが原因だとされる、けいれん性の便秘だと兎糞状の便になりやすいようです。) | |||
| Rats leave a sinking ship. | |||
|
その組織の衰退のきざしをいち早く察知して、 すばやく退社、脱党する人を指していうことわざです。 (sink:沈む、沈没する) | |||
| ウサギの逆立ち | |||
|
| |||
| 鼠牙雀角(ソガジャッカク) | |||
|
| |||
| ウサギの耳 | |||
|
| |||
| 冤(エン) | |||

「ぬれぎぬ」「無実の罪」「冤罪」「うらみ」「不平不満」の意の漢字。 | |||
| ねずみ小僧次郎吉 | |||
 生涯に武家屋敷99ヶ所に120回盗みに入り、計金3100両余 などを盗み、「義賊」との評判が高い大泥棒。二度捕らえられ、最後は江戸市中引き回しの上磔(はりつけ)獄門となりました。
生涯に武家屋敷99ヶ所に120回盗みに入り、計金3100両余 などを盗み、「義賊」との評判が高い大泥棒。二度捕らえられ、最後は江戸市中引き回しの上磔(はりつけ)獄門となりました。
歌舞伎や芝居などでねずみ小僧を題材としたものが江戸中の評判になりましたが、実際は盗んだ金で贅沢をし、貧乏人に施した形跡は無かったようです。 | |||
| 竄(サン、ザン) | |||

「かくれる」「のがれる」「いれる」「かすか」「ひそか」「すてる」「しみいる」「あらためる」の意の漢字。
| |||
| 関節ネズミ | |||
|
| |||
| ネズミ捕り | |||
|
速度違反を取り締まる方法には以下の3種類があります。 1:オービス(無人速度取り締り機)、 2:パトカー・白バイ追尾取り締り(高速機動隊取り締り) 3:有人式一般速度取り締り 3番目をネズミ捕りといい、路上に速度測定器を設置しておき、そこで速度違反が発覚すると、その先の誘導場所に連絡し検挙する方法で、速度違反を取り締まる方法では大変厳しく、対象速度は15Km/h超過からが一般的といわれています。 | |||
| ネズミが塩を引く | |||
また、少量ずつ減っていき最終的にはなくなること。  ネズミが塩をこっそり盗んでいくのは、かなり少量ずつで目立たないが、 何回も盗みを繰り返されると、いつの間にか大量になくなってしまうから。 | |||
| ねずみ算 | |||
| |||
| ねずみ講 | |||
|
ピラミッド型組織で、正式には無限連鎖講と呼ばれる犯罪。 ネズミは繁殖力が非常に高く、すぐ増える動物の代表であり、 講というのは「民間の金融組織」という意味があることから、 「ネズミの様に増殖していく民間の金銭配当組織」ということです。 | |||
| 月のウサギ | |||
月の影の模様から、「月にはウサギがいる」というのは昔からの伝承ですが、これにまつわる伝説の内、最も代表的であろうものはインドの神話にさかのぼります。
| |||
| 袋のネズミ | |||
|
| |||
| ウサギ跳び | |||
 かつてのスポ根モノには欠かせなかったトレーニング。
かつてのスポ根モノには欠かせなかったトレーニング。下半身・ジャンプ力を鍛えるには過酷な練習が良いとされていた時代の悪しき産物で、現在では絶対にやるべきではないものとして知られています。
| |||
| 窮鼠(きゅうそ)猫をかむ | |||
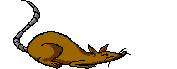
ネコに追い詰められれば、ネズミも必死で猫に噛みつくの意から。 | |||
| 動物小話 その6 「ネズミの嫁」 | |||

ネズミのお嫁さんが、嫁ぎ先から、実家の方へ戻ってきてしまいましたので、 お母さん:「どうしたんだい、どうして、帰ってきちゃったんだい。」 | |||
| バニーガール(bunny girl) | |||
|
bunny は幼児語でウサギのこと、俗語としては、かわいこちゃんや活発で魅力的な女の子の意味に使われます。
| |||
| パソコンの「マウス」と「ミッキー」 | |||

パソコンの操作に使うマウスは英語のmouse(ネズミ)ですが、マウスの動きをコンピュータ本体に伝える信号の単位(マウスの移動距離)は、何とmickey(ミッキー)。1ミッキーはマウスが1/200インチ(およそ1.27mm)移動したことを表します。
| |||
| 兎走烏飛(とそううひ) | |||
| |||
| 株を守りて兎を待つ(かぶをまもりてウサギをまつ) | |||

古代中国戦国時代の宋の農夫が走ってきた兎が切り株にぶつかって死んだのを捕り、それに味をしめ以後仕事もしないで切り株を見張っていたが、二匹めは現れず、畑の収穫も出来なかった。という故事。
| |||
| 動物小話 「ネズミがチュウ」 | |||

男A : 「ねずみ取りにかかったよ、ずいぶん大きなネズミだ。」 男B : 「どーれ、ちっとも大きくねぇじゃあねぇか、小せぇよ。」 男A : 「いいや、大きい。」 男B : 「小さい。」 男A : 「大きい。」 男B : 「小さい。」 男A : 「大きい。」 男B : 「小さい。」 そんなことをいっていると、中でネズミが、“チュウ(中)”。 | |||
| 大山鳴動して鼠一匹(たいざんめいどうしてねずみいっぴき) | |||

大げさに騒いだわりに大したことが無い結果に終わるという意味です。「大山」は「泰山」とも書きます。 | |||
| 頭の黒いネズミ | |||
|
ネズミというのは、「寝ず見」というほどで、夜眠らないで人の寝静まった頃を見計らって、食物などを失敬していくドロボウ的存在です。 | |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |



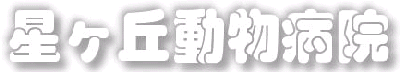


 アラブのことわざ。
アラブのことわざ。


 ネズミには年ごろの娘がおり、嫁に出すなら強くりっぱな男でなければと思い、最も強いと思った太陽のところへ行って、「お天道さま、あなたはこの世でいちばんえらいお方です。どうか娘を嫁にしてください」といいました。すると太陽は「残念だが、この世にはわたしよりずっと強い者がいる。あの雲にさえぎられたら、わたしの光は地上にとどかなくなってしまうのだよ」といいました。
ネズミには年ごろの娘がおり、嫁に出すなら強くりっぱな男でなければと思い、最も強いと思った太陽のところへ行って、「お天道さま、あなたはこの世でいちばんえらいお方です。どうか娘を嫁にしてください」といいました。すると太陽は「残念だが、この世にはわたしよりずっと強い者がいる。あの雲にさえぎられたら、わたしの光は地上にとどかなくなってしまうのだよ」といいました。

