|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 鯨鯢(げいげい)の顎(あぎと)にかく | |||
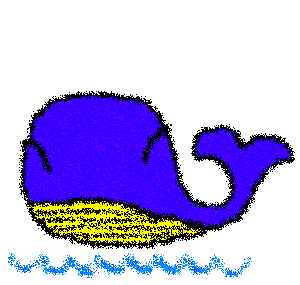 クジラに食われそうになること。海で危険な目に遭って命を落としそうになることのたとえです。
クジラに食われそうになること。海で危険な目に遭って命を落としそうになることのたとえです。
「鯨鯢」とは「クジラ」のことで、それぞれの漢字が、雄のクジラと雌のクジラを示すものなのです。また「顎」とは「あご」のことです。 | |||
| 馴染みては猪の子も可愛 | |||
 どのようなものでも近くにいて慣れ親しむと情が移ってかわいく思えるということです。
どのようなものでも近くにいて慣れ親しむと情が移ってかわいく思えるということです。
| |||
| 亥の子餅に蝿がおらん | |||
|
亥の子とは、陰暦十月最初の亥の日に行う祭りのことです。
時候的にも寒さに向かうおりでもあるので、亥の子の餅をつくころには、自然にハエがいなくなるものだということです。
| |||
| 酔象 | |||
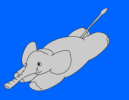 酒に酔って暴れるゾウ、発情して凶暴になった雄のゾウという意味です。
酒に酔って暴れるゾウ、発情して凶暴になった雄のゾウという意味です。転じて仏教では凶悪な心や狂暴なもののたとえに用いられることばです。 本将棋にはなく、中将棋などの将棋で用いられることのある駒の一種でもあります。 真後ろ以外の全ての方向に1マス進むことができ、成ると王将と同じ動きをする「太子」になる。また、「太子」が自駒として盤上に存在する場合、王将を取られても勝負に負けないという効果を持つ。 安時代の日本ではこの駒が既に用いられていたと考えられています。 | |||
| シシ食えば古傷がうずく | |||
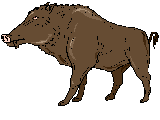 傷がうずくほど精が強いという意味で、肉食を禁じた仏教思想の因果応報に基づくようなことわざです。
傷がうずくほど精が強いという意味で、肉食を禁じた仏教思想の因果応報に基づくようなことわざです。
肉食が禁じられた江戸時代にもイノシシは山鯨と称され、寒さ厳しい冬の季節の栄養補給源や、ある種の薬として一部の人たちにに食べられていたようです。 | |||
| 林の中の象の様に | |||
 「良き伴侶を得られない場合は、孤独を貫け 孤独に歩め 悪をなさず 求めるところは少なく 林の中の象のように 」これは仏陀の言葉で”孤独”が必ずしも不幸に結び付くわけではないことを説いたといわれています。
「良き伴侶を得られない場合は、孤独を貫け 孤独に歩め 悪をなさず 求めるところは少なく 林の中の象のように 」これは仏陀の言葉で”孤独”が必ずしも不幸に結び付くわけではないことを説いたといわれています。
良き伴侶と出会えることは喜ばしいことですが、出会えなかったからといって決して不幸になるわけではありません。求めるものが少なければ、不幸になることも無く、静かに安寧に生きることが出来るということです。 | |||
| 梧鼠(ごそ)の五技 | |||
| |||
| Elephant in the Room「象が部屋にいる」 | |||
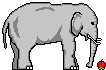 皆が見て見ぬふりをするような問題や、タブー・触れてはいけない話題を意味します。
部屋の中に大きな象がいて誰しもが見逃すことができない状況なのに、触れることができない状況から由来しているそうです。
つまり「elephant」は、そこに居合わせた人がみな重要な問題と認識していながら、この場ではあえて触れずにいる、そういう話題を暗に示す意味合いがあります。
皆が見て見ぬふりをするような問題や、タブー・触れてはいけない話題を意味します。
部屋の中に大きな象がいて誰しもが見逃すことができない状況なのに、触れることができない状況から由来しているそうです。
つまり「elephant」は、そこに居合わせた人がみな重要な問題と認識していながら、この場ではあえて触れずにいる、そういう話題を暗に示す意味合いがあります。
| |||
| 猪首(いくび) | |||
 そのような首のことをいいます。 また、兜(かぶと)をややあお向けにかぶることは、 敵の矢を恐れない勇ましいかぶり方とされていましたが、 首が短く見えることからこのようにいいました。 | |||
| さとうきびが象の口に | |||
 タイのことわざ。
タイのことわざ。さとうきびはゾウが大好きな食べ物ですので、ゾウの口にさとうきびが入ったらぜったい戻ってきません。価値があるものが誰かの手に渡ってしまうと、二度と自分の元に戻ってくることはないということです。 | |||
| 偃鼠(えんそ)河に飲めども腹を満たすに過ぎず | |||
|
| |||
| 群盲象を評す | |||
 大勢の盲人が一頭のゾウをなでて、自分の触れたところだけの印象から、ゾウの全体の形についてさまざまな意見を言ったということから、
凡人が大事業や大人物を評価してもその一面だけにとらわれて、全体的な判断は出来ないということです。
大勢の盲人が一頭のゾウをなでて、自分の触れたところだけの印象から、ゾウの全体の形についてさまざまな意見を言ったということから、
凡人が大事業や大人物を評価してもその一面だけにとらわれて、全体的な判断は出来ないということです。「群盲象を撫でる」「衆盲象を摸す」ともいいます。 | |||
| 灰色のサイ | |||
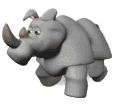 不良債権や少子高齢化などのように、将来マーケットにおいて高い確率で大きな問題を引き起こす恐れがあるのにもかかわらず、現時点で軽視されがちな潜在的リスクのことをいう証券用語です。 | |||
| 白い象(white elephant) | |||
 英語においては白い象(white elephant)というのは、維持費のかかる、わずらわしい物や無用の長物を意味します。
英語においては白い象(white elephant)というのは、維持費のかかる、わずらわしい物や無用の長物を意味します。これは次のような昔話によるものだそうです。 昔、タイのある王が自分の嫌いな家臣に、珍しくて縁起の良いとされる白いゾウを贈りました。 しかし、大食らいのゾウであるため莫大な金がかかり、しかも物を踏みつぶしたりで家の中が目茶苦茶になったりしますが、 捨ててしまったり、森の中に逃がしたり、あるいは殺したりは絶対にできませんので、その家臣はほとほと困ってしまった…というものです。 | |||
| 猪は射手の前、焼酎は上戸の前 | |||
|
物には、それぞれ置くにふさわしい場所があるといったことです。 | |||
| もぐらたたき | |||
|
そこから、たとえ一ケ所を制圧しても別の場所で次々と新たな活動が始まるので、なかなか終わらせられないということです。 | |||
| 猪の手負い | |||
|
そこから、きわめて危険であることのたとえです。 | |||
| 象牙の塔 | |||
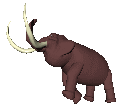 そこから、とても地位の高い人は様々な問題から遠いところにいるため、世間の現実が分からないという意味で使われたり、 学者などが研究熱心なあまり、現実社会と疎遠になったときに使われるようになりました。 | |||
| 天然つぶてに猪をうつ | |||
|
| |||
| 鼻が邪魔じゃまだと思うゾウはいない | |||
|
ゾウの鼻は長くて重いけどそんなことを気にするゾウはいません。他人から見れば大きなハンデに見えることでも、 もともと自分が持っていたものや自ら背負ったものなら苦にならないということで、人は欠点があってもそれなりに克服して生きていくということです。 | |||
| 豕(いのこ)を抱いて臭きを忘る | |||
|
イノコは臭いものだけれどもイノコをかかえている本人にはその臭さがわからないことから、自分の欠点や醜さは自分では気づかないということです。 | |||
| 封豕長蛇(ほうしちょうだ) | |||
 「封」は大きいの意味で、「豕」とはイノシシのことです。 | |||
| 鯨の喧嘩にエビの背が裂ける | |||
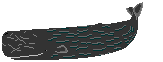 韓国の諺。力を持った者同士が争う中で、
韓国の諺。力を持った者同士が争う中で、力の弱い者が故なく巻き添えを食うこと。 | |||
| 熊の親切 | |||
 ロシアのことわざで、余計なお世話をすること。
ロシアのことわざで、余計なお世話をすること。クマがハエを払おうとして老人を殴り殺してしまったというクルイロフの寓話より。 | |||
| 鼬の無き間の貂の誇り (いたちのなきまのてんのほこり) | |||
 天敵であるイタチが居ない間だけテンが威張ることから。
天敵であるイタチが居ない間だけテンが威張ることから。自分よりすぐれた者や力の強いものがいないときだけ、得意がったり威張ったりすることをいいます。 「貂(テン)」はイタチ科の動物。 | |||
| 一匹の鯨に七浦賑わう | |||
 一頭のクジラがとれると、七つの浦つまり七つの浜、多くの漁村がうるおうということで、獲物が大きいとその恩恵を受ける者が多いということです。
一頭のクジラがとれると、七つの浦つまり七つの浜、多くの漁村がうるおうということで、獲物が大きいとその恩恵を受ける者が多いということです。
| |||
| 猪尾助(ちょびすけ) | |||
|
また、小生意気に出しゃばることや何事にも心得顔にふるまい、ややもすれば失策するものにもいいます。 | |||
| イの一番 | |||
 古来、シカ、カモシカ、イノシシをすべて「シシ」と呼んでいいましたが、これらを区別するためにイノシシを「イの一番」と呼ぶようになりました。
古来、シカ、カモシカ、イノシシをすべて「シシ」と呼んでいいましたが、これらを区別するためにイノシシを「イの一番」と呼ぶようになりました。
ほかのシカは「カノシシ」、カモシカは「カモシシ」と呼びます。 | |||
| 猪食った報い | |||
|
| |||
| 鰯網で鯨捕る | |||
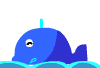 イワシを捕ろうとして仕掛けた網でクジラが捕れることから、思わぬ幸運や収穫に遭遇することをいいます。
イワシを捕ろうとして仕掛けた網でクジラが捕れることから、思わぬ幸運や収穫に遭遇することをいいます。又あるはずがないということを表すこともあります。 | |||
| 燃犀の明 (ねんさいのめい) | |||
 中国晋の故事によると、サイの角を燃やした光は水中深くの普通は見えないところが透き通ってよく見える、ということから、
物事を明確に見抜く才知のたとえです。また、暗い所を明かるく照らす、見識が明らかで徹底していることという意味もあります。
中国晋の故事によると、サイの角を燃やした光は水中深くの普通は見えないところが透き通ってよく見える、ということから、
物事を明確に見抜く才知のたとえです。また、暗い所を明かるく照らす、見識が明らかで徹底していることという意味もあります。
| |||
| 猪も七代目には豕(いのこ)になる | |||
| |||
| 女の髪の毛には大象もつながる | |||
 女色の魅力に負けて大きなゾウも大人しくつながれる、という意味です。
女色の魅力に負けて大きなゾウも大人しくつながれる、という意味です。女性の色気が男をひきつける威力がおおきく、男を支配する力が強いことのたとえです。 | |||
| 鼬の目陰(まかげ) | |||
|
| |||
| 象の牙を見て、その大なるを知る | |||
|
| |||
| 逐(チク) | |||

「追う」「追い払う」「退ける」「駆逐」「従う」「後についていく」「きそう」「走る」「物を順をおう」の意の漢字。
| |||
| リスに穴を教える | |||
|
| |||
| 蝙蝠傘(こうもりがさ) | |||
 細い鉄の骨に絹・ナイロンなどを張った洋傘で、開くとコウモリが翼を広げた形に似るところから、このように言われるようになりました。
細い鉄の骨に絹・ナイロンなどを張った洋傘で、開くとコウモリが翼を広げた形に似るところから、このように言われるようになりました。
| |||
| ゾウに乗ってバッタ狩り | |||
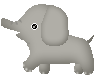 タイのことわざ。小さな動物であるバッタを捕まえるのにわざわざ大きなゾウに乗って行くのはおおげさすぎます。
つまり莫大な投資をしたのにも関わらず、ほんのちっぽけな利益、または価値のないものしか手に入らなかった様子をいいます。また、必要以上な大げさな行動をあらわすこともあります。
タイのことわざ。小さな動物であるバッタを捕まえるのにわざわざ大きなゾウに乗って行くのはおおげさすぎます。
つまり莫大な投資をしたのにも関わらず、ほんのちっぽけな利益、または価値のないものしか手に入らなかった様子をいいます。また、必要以上な大げさな行動をあらわすこともあります。
| |||
| 鯨波(とき) | |||
 合戦で、士気を鼓舞するために多人数の者が同時に叫び声をあげたり、大将が「えいえい」と叫び、部下一同が「おう」と答える、とき(鬨)の声。または大波のこと。
合戦で、士気を鼓舞するために多人数の者が同時に叫び声をあげたり、大将が「えいえい」と叫び、部下一同が「おう」と答える、とき(鬨)の声。または大波のこと。
| |||
| ゾウの耳 | |||

高温乾燥地域に住むゾウは、汗をかくことで体温調節をすると大量の水分補給が必要になります。そこで暑くなるとあの耳をパタパタ動かして耳にたくさん通っている血管の中の血液を冷やし、それが全身を巡ることで体温を下げ水分の節約もしているわけです。
| |||
| イルカの睡眠 | |||
|
| |||
| 熊手(くまで) | |||
 長い柄の先に鉄のツメをつけて敵を馬から引き落としたり、取りおさえるのに用いる武具や、先端を爪状に曲げた細い竹を何本もつけた、庭の掃除などにも使われる農具のこと。
長い柄の先に鉄のツメをつけて敵を馬から引き落としたり、取りおさえるのに用いる武具や、先端を爪状に曲げた細い竹を何本もつけた、庭の掃除などにも使われる農具のこと。
幸運や金運を「かき集める」という意味を込めて、商売繁盛の縁起物であったり、欲張りな人のたとえでも使われます。 | |||
| 鯨飲(げいいん) | |||
|
| |||
| 豪(ゴウ) | |||

「ヤマアラシ」「すぐれる」「ひいでる」「つよい」「えらい」「おとこだて」「ぜいたく」「金持ち」「傑出する」の意の漢字。高と豕の合字。 | |||
| むささびは 木末(こぬれ)求むと あしひきの 山の猟夫(さつお)に あひにけるかも | |||
|
そこを運悪くあっけなく猟師に捕まってしまったのが、 あわれであり、おかしくもあります。 天智天皇の皇子である志貴皇子(しきのみこ)の歌。 | |||
| カバのあくび | |||
|
オス同士がメスをめぐって争う時や、自分のテリトリーに入り込んできたほかの動物を追い払う時などに、牙のはえた大きな口を開けて、自分の力を誇示して見せているのです。 | |||
| 像(ゾウ) | |||

「にる」「にせる」「かたどる」「かたち」「すがた」の意の漢字。 | |||
| ゾウの葬式 | |||



ゾウには家族と一緒に生活する習性があるのは有名ですが、仲間が死んだ時には人間でいう葬式に当たる儀式をするそうです。
| |||
| ヘナチョコ | |||

埴土(へなつち)で作った猪口(チョコ)で、焼き目から酒が染みだして使い物にならなくなります。そこで使い物にならない失敗作を「へな猪口」と言い、それが未熟者をさす言葉になりました。
| |||
| 毅(キ、たけし、つよし) | |||

「つよい」「たけし」「意志が強くくじけない」「決断力がある」「おこる」「いかる」の意の漢字。
| |||
| 猪武者(いのししむしゃ) | |||
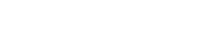
前後の事情も考えないで我武者羅に突進するだけの武士のこと。向こう見ずな武士。 | |||
| 猪突猛進(しょとつもうしん) | |||
|
イノシシがひたすら突進する様子をいいます。 | |||
| ゼブラ(シマウマ・斑馬) | |||
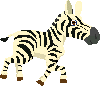
ゼブラとは「シマウマ」の事をいいますが、シマウマを漢字で表現すると「斑馬」と書きます。
| |||
| ヤマアラシのジレンマ | |||
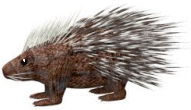
「自己の自立」と「相手との一体感」、また「自分を愛する」と「人をも愛する」
| |||
| 有象無象(うぞうむぞう) | |||
|
「有相無相」に同じで、数は多いが種々雑多なくだらない人や物、またろくでもない連中のことをいいます。 | |||
| 山よりも大きなイノシシは出ぬ | |||
|
そのイノシシが住んでいる山より大きなイノシシが出たなどというのは、いくらなんでも話しがオーバー過ぎる。 | |||
| 蝙蝠(コウモリ) | |||
 
コウモリという動物の大好物というと「蚊」です。そして、その「蚊を食べる」と言うことが、コウモリの名前の由来になっているのです。
| |||
| 鯨幕(くじらまく) | |||
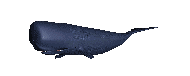
お葬式など凶事に用いられる黒白の幕のこと。 | |||
| 他人の罪はヤマネコの目で、おのが罪はモグラの目でみる | |||
|
チェコのことわざ。 | |||
| カバは血の汗をかく? | |||

カバは人のような汗はかかないが皮膚に粘液を分泌します。それが赤いので血の汗をかいているようにみえるのです。 | |||
| アシカの番 | |||

アシカは陸に上がって眠るが、用心深い動物で1頭は必ず見張り役で起きているます。 | |||
| 鳥無き里の蝙蝠(コウモリ) | |||
|
コウモリは空を飛べますがトリの仲間ではありません。 | |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |



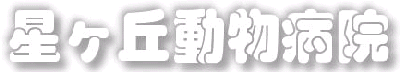


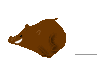
 と豕の合字。
と豕の合字。 と殳の合字。豕はイノシシ、
と殳の合字。豕はイノシシ、