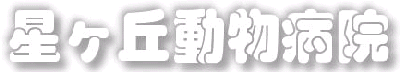|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 月に一鶏を攘(ぬす)み、もって来年を待つ | |||||
 悪事と知っていても、なかなかやめられないことをいいます。
悪事と知っていても、なかなかやめられないことをいいます。毎日ニワトリを盗んでいる者に悪い事はやめるようにと戒めたところ、 これからは月に一羽にして、来年になったらやめると答えたという故事から。 | |||||
| 鳩を憎み豆作らぬ | |||||
|
| |||||
| 鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん | |||||
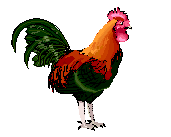 論語より。小さなニワトリを料理するのに、どうしてウシをさばくような大きな刃物を使う必要があるだろうか、ということです。
論語より。小さなニワトリを料理するのに、どうしてウシをさばくような大きな刃物を使う必要があるだろうか、ということです。そこから、小さな事柄を処理するのに大がかりな態勢で臨むことの無意味さをいいます。また、小事に大人物は必要ないという意味もあります。 | |||||
| 賢い鶏は卵から鳴く | |||||
 シリアのことわざです。
シリアのことわざです。のちに大成する人物は、幼い時から並外れた能力を示すものだ、ということです。 | |||||
| 金の卵を産む鵞鳥(ガチョウ)を殺すな | |||||
|
毎日金の卵をひとつずつ生むガチョウを持っていた男が、腹の中にはたくさん金の卵が入っているものと思い、殺してお腹の中を見たら何もなく元も子も無くなってしまうというイソップ物語。
目先の利益に目がくらんで、将来続くはずの利益を犠牲にするな、あるいは将来への大局的な見通しを失ってはならない、という戒めです。 | |||||
| 鶏鳴の助 | |||||
 賢い妃が、君主に国政を怠らせないようにするために、「家臣は、ニワトリがなく前から働いています。閣下もしっかりしなさいませ!」と告げ、君主を早起きさせたという故事によります。
賢い妃が、君主に国政を怠らせないようにするために、「家臣は、ニワトリがなく前から働いています。閣下もしっかりしなさいませ!」と告げ、君主を早起きさせたという故事によります。
内助の功のことをいいます。 | |||||
| 欲の熊鷹股裂くる(よくのクマタカまたさくる) | |||||
|
2頭のイノシシをつかんだクマタカが、必死で左右に逃げようとするイノシシを、欲にかられてどちらも放さなかったのでその股が裂けてしまったという話。 あまり欲張りすぎるとひどい目に遭いますよ、ということです。 | |||||
| 従兄弟同士は鴨の味 | |||||
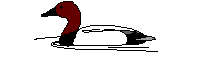 従兄弟同士の夫婦はとても仲がよい、ということのたとえです。
従兄弟同士の夫婦はとても仲がよい、ということのたとえです。カモの肉の味がよいように、夫婦仲がよいということです。 | |||||
| 鳩尾(みぞおち) | |||||
 胸の中央にあるくぼんだ部分のことで、飲んだ水が落ちる水落から変化した言葉。
胸の中央にあるくぼんだ部分のことで、飲んだ水が落ちる水落から変化した言葉。文字としての鳩尾の語源は、左右のあばら骨をハトの羽にみたてると、みぞおちの所がハトの尾になるからです。 | |||||
| 鸚鵡能 (おうむよ)く言えども飛鳥を離れず | |||||
 オウムが人間のことばをいくら話せても、やはり鳥でしかないという意味。
オウムが人間のことばをいくら話せても、やはり鳥でしかないという意味。いくら言葉を巧みに話せても、口先だけで礼を欠いていれば、鳥獣と同じだということです。 | |||||
| 雄鶏自らその尾を断つ | |||||
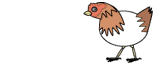
『左伝』より、尾の立派な雄鶏は、祭祀の犠牲にされることを知って自ら尾を食いちぎって難を避けるということ。才知が人にすぐれている者は災いを受けることを知っていて、愚人を装って人の目をくらますということです。
| |||||
| 下種と鷹とに餌を飼え (げすとたかとにえをかえ) | |||||
 品性が劣って心の卑しい者や、能力が不十分であったりする者には、鷹狩りのタカに餌を与えるように、ご馳走や金品などの利益を与えて上手く手なずけて使うのがよいということです。
品性が劣って心の卑しい者や、能力が不十分であったりする者には、鷹狩りのタカに餌を与えるように、ご馳走や金品などの利益を与えて上手く手なずけて使うのがよいということです。
| |||||
| 鶏頭(ケイトウ) | |||||
 真夏に咲く草花で真っ赤な花がニワトリの頭のトサカに見立てているものと思われます。
真夏に咲く草花で真っ赤な花がニワトリの頭のトサカに見立てているものと思われます。
| |||||
| 鷲はハエを捕らえず | |||||
 ワシなどの大きな鳥は小さなハエなど捕らえないということで、大物は小さな利益などは問題にしないということです。
ワシなどの大きな鳥は小さなハエなど捕らえないということで、大物は小さな利益などは問題にしないということです。
| |||||
| 牝鶏(めんどり)につつかれて時をうたう | |||||
 夫が妻の意見に従って動くということで、いわゆる「かかあ天下」のことをニワトリの雌雄にたとえた言葉です。
夫が妻の意見に従って動くということで、いわゆる「かかあ天下」のことをニワトリの雌雄にたとえた言葉です。もともとは男性中心の道徳観から妻を非難していったもののようです。 | |||||
| 鷹を養うが如し | |||||
 タカは空腹だと鷹狩りでよく働くが、満腹になるとと飛び去ってしまうように、上手に飼うのは大変です。
タカは空腹だと鷹狩りでよく働くが、満腹になるとと飛び去ってしまうように、上手に飼うのは大変です。
ひと癖ある者やひねくれた者も、その欲望を満足させないと不平をいって従わないし、十分に満足させればそむいたりし、上手く操って使いこなすのはむずかしいということです。 | |||||
| 献上の鴨 | |||||
|
| |||||
| 卵がかえる前にニワトリを数えるな | |||||
|
これから起きるかどうか確かではないことを期待して、計画を立てるべきではないということ。 | |||||
| アヒルの火事見舞い | |||||
| |||||
| 鶏肋 ( けいろく ) | |||||
|
| |||||
| 鳶職(とびしょく) | |||||
| |||||
| 鶏冠(トサカ)に来る | |||||
 「頭に来る」を強調した言い方で、カッときて頭に血が上った様を鶏冠(トサカ)にたとえたようです。
「頭に来る」を強調した言い方で、カッときて頭に血が上った様を鶏冠(トサカ)にたとえたようです。映画の中で使われたことから流行った言葉だそうです。 | |||||
| 梟雄(きょうゆう) | |||||
 梟はフクロウ。
梟はフクロウ。死骸を高い木の上にさらすと鳥が寄り付かないというほど獰猛で、他の鳥たちにも敬遠されることから、残忍で荒々しいこと人や、悪者などの首領のことをいいます。 | |||||
| 木鶏(もっけい・ぼっけい) | |||||
 木製の闘鶏のこと。
木製の闘鶏のこと。真に強い者は敵に対して少しも動じないことのたとえで、荘子の中にある有名な話です。 他の闘鶏が鳴いていても顔色も変えず、まるで木彫りの鶏のようで完全に闘鶏として仕上がったということです。 実際に闘わせてみますと、ほかの闘鶏は闘わずして逃げるしかありません。 そこから褒められても、けなされても、態度が変わらず、泰然自若としたことをいうようになりました。 | |||||
| 千貫(せんがん)の鷹も放さねば知れず | |||||
 金千貫の値打ちがあるという、優れた才能があるタカでも、実際に試してみないとその力量はわかりません。
金千貫の値打ちがあるという、優れた才能があるタカでも、実際に試してみないとその力量はわかりません。いかに才能ある人でも、実際にことに当たらなければ、その才能の真価はわからないものだということです。 | |||||
| みにくいアヒルの子 | |||||
|
| |||||
| 鷲掴み | |||||
 ワシが獲物をつかむように、乱暴に物をつかむこと、また、指を広げて物をあらあらしくつかみ取ることをいいます。
ワシが獲物をつかむように、乱暴に物をつかむこと、また、指を広げて物をあらあらしくつかみ取ることをいいます。
| |||||
| ニワトリは3歩歩くと忘れる | |||||

直ぐに物忘れすること、或いはよく忘れる人をからかったり、侮ったりするときに使われます。 | |||||
| ニワトリははだし | |||||
| |||||
| 水鳥の 鴨の羽色の 春山の おほつかなくも 思ほゆるかも | |||||
| |||||
| 鷹(タカ)は飢えても穂を摘(つ)まず | |||||

鷹(タカ)は高(タカ)に通じる言葉。 | |||||
| チキンレース (Chicken Race) | |||||
アメリカでは負けた者はチキン(弱虫・臆病者)といわれ、バカにされるということです。 | |||||
| 鳶(トンビ)に油揚げをさらわれる | |||||
|
| |||||
| 鷹揚(おうよう) | |||||
|
また、おっとりとして上品な様子をいいます。 「鷹揚に構える」というように使います。 | |||||
| 鳥居 | |||||

神社の入り口にかならずある「鳥居」の名前は、読んで字の如し「鳥がいる所」と言う意味で、止り木をさしています。そしてとまるべき鳥はニワトリなのです。
| |||||
| カモ(にする) | |||||

カモは鳥の鴨、カモは比較的捕まえやすい鳥なので、利益をあげやすいという意味で使われるようになりました。 | |||||
| 夜をこめて 鳥の空音(そらね)は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ | |||||

「夜が明けないうちに、ニワトリの鳴き声を真似して、 作者は、日本の随筆文学を代表する「枕草子」を書いた清少納言です。
| |||||
| 鳶(トビ)が鷹(タカ)を生む | |||||

トビは平凡な鳥。タカは立派な鳥のたとえ。 | |||||
| 上見ぬ鷲(ワシ) | |||||
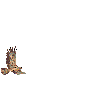
鳥類の王、ワシは他の鳥を恐れず眼下の獲物をねらうだけで、上からの攻撃を警戒する必要は無いことから、何も恐れず悠々としています。 | |||||
| 一富士・二鷹・三茄子(いちふじにたかさんなすび) | |||||
|
いわゆる初夢に見ると縁起の良いものとして有名ですが、この3つが縁起良いといわれた理由としては、次の二つの説が有名です。 | |||||
| 能ある鷹は爪を隠す(のうあるタカはつめをかくす) | |||||

「能」と言うのは能力や才能のこと。 | |||||
| 鴨の水かき | |||||
| |||||
| 鵜呑み(うのみ) | |||||

人の意見を何の疑いもなく信じて受け入れてしまう事をいいます。 | |||||
| 家鴨(アヒル)も鴨(カモ)の気位 | |||||
|
それほどでもないものが、気位(きぐらい)だけは高く持っていることのたとえです。
| |||||
| ニワトリ鳴かずとも朝は来る | |||||
|
ことさらに自分の力を誇示して、自分がいなければ事は決してならないなどという人を諷している、インドのことわざです。
| |||||
| 鳩に豆鉄砲 | |||||

驚きのあまり、目を丸くしてきょとんとしているようす。 | |||||
| 風見鶏(かざみどり) | |||||

寺院の塔の上や建物の屋根などに取りつけてあるニワトリをかたどった風向計。 | |||||
| 鳩首(きゅうしゅ) | |||||


人々が集まって額を付け合うようにして、相談をすることをいいます。 | |||||
| 逢い戻りは鴨の味(あいもどりはカモのあじ) | |||||



よりを戻した男女の仲は、肉の中でも特に美味とされたカモの肉のような味わいだということから。一度別れた男女の仲が元に戻ると、その仲は前より一層細やかになるということです。
| |||||
| 鴨が葱をしょって来る | |||||
|
カモにネギがあればすぐに食べられます。 | |||||
| 鵜の目鷹の目 | |||||
|
鵜は水中で魚を探すのに都合の良い鋭い目を持ち、鷹は空中から獲物を探すのに適した鋭い目を持っています。 | |||||
| 手品に出てくる白いハト | |||||
|
手品に出てくるハトはどうして白ばかりで他の色のハトがいないのでしょうか。 | |||||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |