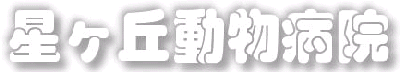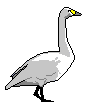|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 雀の巣も構(く)うに溜まる | |||||
| |||||
| 江戸雀 | |||||
 江戸に住み江戸市中の事に精通し、それをしゃべり歩いたり噂に詳しい人のことを、うるさいスズメに見立てたことばです。
江戸に住み江戸市中の事に精通し、それをしゃべり歩いたり噂に詳しい人のことを、うるさいスズメに見立てたことばです。
また17世紀。江戸で刊行された初めての江戸地誌のことでもあります。実用的な江戸の名所案内として作られており、 巻末にはおよそ東西南北三里四方の大概を記すとあり、大名屋敷・社寺・町・橋の総数などが付されています。 京都・大坂(難波)の町案内書と合わせて「三雀」と呼ばれていました。 | |||||
| 雀脅して鶴失う | |||||
|
| |||||
| 鶴の林 | |||||
| |||||
| 鶴の粟 蟻の塔 | |||||
|
アリが細かな土砂の粒を一つずつ運んで蟻塚を築くように 少しずつ拾い集めてたくわえることをいいます。 | |||||
| 梅に鶯 | |||||
|
あとに「柳に燕」「紅葉に鹿」「牡丹に唐獅子」「竹に虎」などと続けてもいいます。 | |||||
| 烏の頭(かしら)白くなるまで | |||||
 秦に捕らえられた燕の大子丹が帰郷を願い出たとき、秦王が、カラスの頭が白くなり馬に角が生えたら許してやろう、
と言ったという故事から、永久にその時期が来ないことやありえないことのたとえです。
秦に捕らえられた燕の大子丹が帰郷を願い出たとき、秦王が、カラスの頭が白くなり馬に角が生えたら許してやろう、
と言ったという故事から、永久にその時期が来ないことやありえないことのたとえです。
| |||||
| 騒ぐカラスも団子一つ騒がぬカラスも団子一つ | |||||
 騒いでも騒がなくても、結果は同じことであるということで、どうもがいてみても一生は一生だということのたとえです。
騒いでも騒がなくても、結果は同じことであるということで、どうもがいてみても一生は一生だということのたとえです。
どうもがいてみても一生は一生であるならば、あまり気の進まない事を毎日無理して行うよりも、好きなことを行いながら生活するほうがいいかな、ということ? | |||||
| 燕の幕上に巣くうがごとし | |||||
|
ツバメが幕の上に巣を作りいつ落ちるかわからない危ない状態である、という意味で非常に危険なことのたとえです。
| |||||
| 烏百度洗っても鷺にはならぬ | |||||
 色の黒いカラスはいくら洗っても白いサギにはなりません。
色の黒いカラスはいくら洗っても白いサギにはなりません。むだな骨折りや見当違いの努力はやめて、自分の持つ特性を生かす工夫をしたほうが良いということです。 | |||||
| 勧学院の雀は蒙求を囀(さえず)る | |||||
|
門前の小僧習わぬ経を読むと同じです。 勧学院とは藤原氏一族のためにたてられた教育施設で、蒙求とは中国唐代の教科書のことです。 | |||||
| 闘雀(とうじゃく)人を恐れず | |||||

スズメのようなものでも、けんかに夢中になっているときは、人が近づいても逃げようとしないことから、そのことに無我夢中になっている者は、予想外の力や強さを発揮することがあるということです。
| |||||
| 雀海中に入って蛤となる | |||||
 物事が大きく変化することのたとえです。
物事が大きく変化することのたとえです。古代中国の俗信で、晩秋にスズメが集まって騒いでいるのは、海の中へ入るとスズメがハマグリに変化すると考えられていたことから。 | |||||
| カラスの口からケラがあまる | |||||
 食べ物を選ばずなんでも食べるカラスにも、ケラのように食べないものがあるということで。
食べ物を選ばずなんでも食べるカラスにも、ケラのように食べないものがあるということで。口の卑しい者でも、食べ残すものや嫌いなものがあるということです。 | |||||
| カラスの濡れ羽色 | |||||
| |||||
| 掃き溜めに鶴 | |||||
|
掃き溜めは、ごみを集めておく所やごみすて場のこと、また種々雑多なものがはいりこんでいる所のことです。 そこから、汚いところやつまらないところ、むさくるしい所に似つかわしくない、すぐれたものや美しいものなど、際立っているものが現れることをいいます。 | |||||
| カラスの腹を肥やす | |||||
 
  屍を野山にさらしカラスのついばむままにまかせることで、のたれ死にするということです。
屍を野山にさらしカラスのついばむままにまかせることで、のたれ死にするということです。
| |||||
| 今泣いたカラスがもう笑う | |||||
 ついさっきまで泣いていたのに、何らかのきっかけで急に機嫌を直してすぐ笑う、ということで機嫌がよくなった子供をからかっていうこと。
ついさっきまで泣いていたのに、何らかのきっかけで急に機嫌を直してすぐ笑う、ということで機嫌がよくなった子供をからかっていうこと。また子供の機嫌が変わりやすいことをいいます。 | |||||
| 鶴の脛(はぎ)切るべからず | |||||
 出典は「荘子」。ツルのすねは長くカモの足は短いが、いずれも自然界を生き抜くために長年かけて進化してきた結果であり、それぞれ持ち前の性質があるのだから、いたずらに人の手を加えて、長いからといって切ったり、短いからといって継ぎ足したりしてはならない、ということです。
出典は「荘子」。ツルのすねは長くカモの足は短いが、いずれも自然界を生き抜くために長年かけて進化してきた結果であり、それぞれ持ち前の性質があるのだから、いたずらに人の手を加えて、長いからといって切ったり、短いからといって継ぎ足したりしてはならない、ということです。
| |||||
| 誰か烏の雌雄を知らん | |||||
 カラスのオスとメスの区別がつかないように、似たりよったりしていて区別がつきにくいものをいいます。また、そこから人の心や物事の善悪・優劣の判断が難しいこともいいます。
カラスのオスとメスの区別がつかないように、似たりよったりしていて区別がつきにくいものをいいます。また、そこから人の心や物事の善悪・優劣の判断が難しいこともいいます。
| |||||
| 雀の糠よろこび | |||||
|
| |||||
| 奥烏の愛 | |||||
 人を深く愛するとその家の屋根にとまっている、本来不吉で嫌な鳥であるカラスにさえ愛情を感じるということ。
人を深く愛するとその家の屋根にとまっている、本来不吉で嫌な鳥であるカラスにさえ愛情を感じるということ。人を心の底から愛すると、その人に関係のあるもの全てに愛が及ぶということです。 | |||||
| 鶯張り(うぐいすばり) | |||||
 木造の床板の張り方の一つで、京都知恩院の渡り廊下が有名。
木造の床板の張り方の一つで、京都知恩院の渡り廊下が有名。踏むと床板をとめたかすがいがきしんで、ウグイスの鳴き声のような音をたてるしかけになっています。 | |||||
| 夕鶴 | |||||
|
各地に伝わる民話の一つである『鶴の恩返し』を題材としている、 木下順二作の戯曲。
| |||||
| 烏有(うゆう)に帰す | |||||
 跡形もなくなること。特に火災ですべてを失うことで、 灰燼に帰すと同じ意味です。
跡形もなくなること。特に火災ですべてを失うことで、 灰燼に帰すと同じ意味です。
「烏有」は漢文で「いずくんぞあらんや」と読み下し、「どうしてあるだろうか、いやない」という意味で、転じて「全く無い状態になること」を表します。 | |||||
| 着た切り雀 | |||||
|
| |||||
| 鶴嘴(つるはし) | |||||
|
鋼製で細長くツルの嘴(くちばし)のように両先端をとがらせ、 カシ等の堅木の柄をつけたもの。 | |||||
| 燕返し | |||||
| |||||
| カラスの足跡 | |||||
|
| |||||
| 鵠は浴せずして白し | |||||
| |||||
| 門前雀羅(じゃくら)を張る | |||||
|
| |||||
| 鶴翼 | |||||
|
兵力が敵部隊より多い時に有効な陣形で、 △形に兵を配する魚鱗の陣と対称をなします。 | |||||
| 雀の足跡(すずめのあしあと) | |||||
|
スズメが歩いたときの足跡のような、踊っている文字、 下手な文字のことをいいます。 | |||||
| 鶴首(かくしゅ) | |||||
|
| |||||
| 権兵衛が種まきゃカラスがほじる | |||||
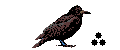 権兵衛さんが畑に豆をまいていると、すぐにカラスが掘り起こして食べているということしで、苦労してやったことを後から誰かがぶちこわして、せっかくの骨折りが無駄になるということです。
権兵衛さんが畑に豆をまいていると、すぐにカラスが掘り起こして食べているということしで、苦労してやったことを後から誰かがぶちこわして、せっかくの骨折りが無駄になるということです。
| |||||
| 欣喜雀躍(きんきじゃくやく) | |||||
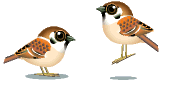 「欣喜」はとても喜ぶことで、「雀躍」はスズメのようにピョンピョン跳ね回ることをいいます。
「欣喜」はとても喜ぶことで、「雀躍」はスズメのようにピョンピョン跳ね回ることをいいます。
そこから、非常に喜ぶこと、小躍りして喜ぶ、有頂天になる、などの意味になります。 | |||||
| 雀隠れ | |||||
| |||||
| 烏(カラス)に反哺(はんぽ)の孝(こう)あり | |||||
|
カラスの子が成長後、老いた親に食物を口移しに与えて 養うとされていることから、鳥や獣でさえそうなのだから 育ててもらった親の恩には報いるものだということです。 | |||||
| 旅人の 宿りせむ野に 霜降らば わが子羽ぐくめ 天の鶴群(たずむら) | |||||
|
わが子を羽でつつんでおくれ、空行くツルの群れよ 万葉集の作者不明の句、天平5年(733)遣唐使船が旅立つ時、 使節の一員であるわが子の無事を祈って母親が詠んだもので、 わが子の安全を託す母親の強い思いが痛いように伺われます。 「羽ぐくむ」は、親鳥がひな鳥を自分の羽根で、 くるみ・かばい・まもる姿で「育む」の語源です。 | |||||
| 燕尾服(えんびふく) | |||||
 男性の夜間用正式礼服。
男性の夜間用正式礼服。上着の前丈が短く、背の裾が長く先が二つに割れて燕の尾のようになっている。 色は主に黒。共布のズボン、白のベスト、白の蝶ネクタイ、黒のエナメル靴などと組み合わせて着る。 | |||||
| 鶯や 柳のうしろ 薮の前 | |||||
 ウグイスという鳥は薄暗い所を好み、低空でしかも落ち着きがない感じで飛びます。
ウグイスという鳥は薄暗い所を好み、低空でしかも落ち着きがない感じで飛びます。いま柳の木の後にいたかと思えば、もう藪の前にいる。まるで実況中継のような松尾芭蕉の句。 | |||||
| すずめの角 | |||||
 スズメは弱い鳥であるから、たとえそのスズメに角が生えても、恐るるに足らないということ。
スズメは弱い鳥であるから、たとえそのスズメに角が生えても、恐るるに足らないということ。
| |||||
| 旅烏(たびがらす) | |||||
| |||||
| 浮かれガラス | |||||
| |||||
| 風声鶴唳(ふうせいかくれい) | |||||
 ささいなことにもびくびくとし、おびえることを表します。 | |||||
| 鳥篭に鶴をいれたよう | |||||
 小鳥の鳥かごに、ツルを入れたらせまくて身動きできない事から、押さえつけられのびのびしない様子をいいます。
小鳥の鳥かごに、ツルを入れたらせまくて身動きできない事から、押さえつけられのびのびしない様子をいいます。
| |||||
| 雀斑(ソバカス) | |||||
 顔や首・手など露出の多い部分にできる褐色の小斑点で、女子に多く思春期に目立ちはじめ、日光に当たると増えるようです。読みの「そばかす」と漢字の「雀斑」は、それぞれ別のものに由来しています。
顔や首・手など露出の多い部分にできる褐色の小斑点で、女子に多く思春期に目立ちはじめ、日光に当たると増えるようです。読みの「そばかす」と漢字の「雀斑」は、それぞれ別のものに由来しています。
| |||||
| 雀の涙 | |||||
|
| |||||
| 亀の年を鶴が羨(うらや)む | |||||

千年の寿命を保つという鶴が、万年の亀を羨ましがるという意味です。 | |||||
| 正鵠(せいこく)を射る | |||||
| |||||
| 烏合(うごう)の衆(しゅう) | |||||
  
カラスの集団の意味。 | |||||
| 鵜(ウ)のまねをする烏(カラス) | |||||

鵜は水にもぐって魚を捕まえる鳥。そんなことのできない烏が鵜の真似をしようとすれば、おぼれてしまうことから、人の真似をして、自分の能力以上のことをしようとして失敗してしまうことをいいます。
| |||||
| 燕雀(えんじゃく)いずくんぞ鴻鵠(こうこく)の志を知らんや | |||||
|
小人物には、しょせん大人物の志は理解出来ないというたとえです。 | |||||
| 鶯(ウグイス)鳴かせたこともある | |||||
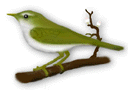
今でこそ年老いてしまったが、若い頃はこれでも、枝から枝へと移るウグイスを梅の枝に止めさせて鳴かせるように、 | |||||
| 鶴の一声 | |||||
 一声しか鳴かないツルの鳴き声は、他の鳥と比べてひときわ大きくて他を圧倒しています。
一声しか鳴かないツルの鳴き声は、他の鳥と比べてひときわ大きくて他を圧倒しています。そこから、衆人の千言を一声で鎮めるような優れた者の声や、多くの人を否応なしに従わせる有力者や権威者の一言をいうようになりました。 | |||||
| 鶴九皐(ツルきゅうこう)に鳴き、声天に聞こゆ | |||||
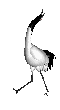 ツルがどんな奥深い沢で鳴いてもその声は天に届くということから 優れた人物はどんなところに隠れ住んでいても 必ず人の知るところとなる、ということです。 | |||||
| 烏(カラス)の行水 | |||||
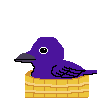
烏(カラス)が水浴びする時間はとても短いことから、入浴時間がすごく短いこと、すぐに風呂から出ることをいいます。 | |||||
| 若いツバメ | |||||

女性から見て年下の恋人の事を「若いツバメ」といいますが、もとは平塚雷鳥(らいてふ)に端を発しています。 | |||||
| 白鳥の歌 | |||||
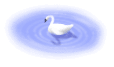
死に瀕したハクチョウは、最も美しく歌うと古来から伝えられています。 | |||||
| 闇夜に烏(カラス)、雪に鷺(サギ) | |||||
|
はっきり判別できないことのたとえ。 | |||||
| crane:クレーン(ツル) | |||||

crane(クレーン)は鶴、動詞になると「起重機で持ち上げる」になります。建設現場や荷揚げ港で利用される「クレーン」はその形が鶴の首に似ていることから名付けられたものです。
| |||||
| 烏(カラス)と鳥(トリ) | |||||
 漢字の「烏(カラス)」は「鳥(トリ)」と似ていますが、違いは横線が一本入っているかいないかだけです。
漢字の「烏(カラス)」は「鳥(トリ)」と似ていますが、違いは横線が一本入っているかいないかだけです。この一本線は目の部分にあたりますが、カラスは顔まで真っ黒で瞳がはっきり見えません。 それでこの部分に線を書かない、ということなのです。 | |||||
| スワローズ | |||||

プロ野球チームのヤクルトスワローズは、かつては国鉄が所有する球団でした。 | |||||
| 雀(スズメ)百まで踊りを忘れず | |||||
|
幼い時に身につけた習慣や若いときの道楽の癖は、年をとっても直らないものだということ。
| |||||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |