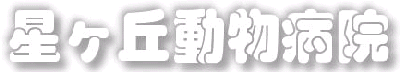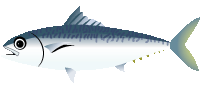|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 雑魚寝(ざこね) | |||
|
| |||
| 鯉口(こいぐち)を切る | |||
また、刀を抜く構えにはいることをいいます。 | |||
| 釜中の魚(ふちゅうのうお) | |||
|
| |||
| 鰹木(かつおぎ) | |||
 伊勢神宮正殿はじめ神社などの建物で、千木(ちぎ)と千木の間の棟木の上に、棟と直交させて並べた短い材のことで、形が鰹節に似ているのでこのように呼ばれるようです。
大棟を押さえるための補強材として置いたものの名残ですが、現在は千木と同様に装飾的に用いられています。
伊勢神宮正殿はじめ神社などの建物で、千木(ちぎ)と千木の間の棟木の上に、棟と直交させて並べた短い材のことで、形が鰹節に似ているのでこのように呼ばれるようです。
大棟を押さえるための補強材として置いたものの名残ですが、現在は千木と同様に装飾的に用いられています。
| |||
| 鮎(アユ)と鯰(ナマズ)のワケありな関係 | |||
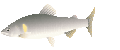
「鮎」と「鯰」はちょっとワケありな関係で、それぞれ「アユ」「ナマズ」と読みますが、もともとは鮎をナマズと読んでいたらしいです。 | |||
| 魚もおぼれる? | |||
|
マグロなどは常に泳ぎ続けており、最高時速が160キロほどになることは知られていますが、こうした魚は泳ぎを止めると、生きていけません。 これは、泳ぐのをやめるとえらに水が流れなくなり、酸素不足になるためです。そのため、泳げないような狭い場所に入り込んだり、延縄などにかかり泳ぐスピードが落ちると溺れ死んでしまうというわけです。カツオやサメもそうです。 | |||
| 鰻の寝床(ウナギのねどこ) | |||
|
| |||
| 鰯(イワシ)で精進(しょうじん)落ち | |||
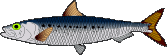
「精進落ち」は魚肉類を一切食べずに、 このせっかくの大事な時を、イワシのようなつまらない魚ですることから、つまらないことで、長い間の努力が報われなかったり、無駄になってしまうことを表しています。
| |||
| 池魚(ちぎょ)のわざわい | |||
| |||
| グチをこぼす | |||
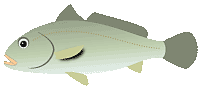
言ってもしかたがないことを言って嘆くことや、言っても甲斐のないことを口に出してぶつぶつこぼすことをいいます。 | |||
| 鰻登り(ウナギのぼり) | |||
|
物価・気温、地位などが見る見るうちに登ること。 | |||
| 逃がした魚は大きい | |||
 釣り落した魚は実物より大きく見える、
釣り落した魚は実物より大きく見える、ということから。 手に入る寸前に失ってしまった物や機会は、 とても惜しい気がするものだ、ということです。 | |||
| 河豚(フグ)食う馬鹿に食わぬ馬鹿 | |||
|
猛毒があるとわかっているフグを食べて、たかが魚のために命を失うのは思慮のない人がすることだが、だからといって、フグほどおいしい魚を食べないのも愚かなことだということ。
| |||
| 木魚(もくぎょ) | |||
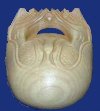
ポクポクとお経につきものの木魚は心を和ませるような柔らかい響きで不思議なカタチですね。 | |||
| ごまめの歯ぎしり | |||

実力や力量の足りない者が、いたずらにいきりたつことのたとえ。また、弱い者が、どうにもならないことに腹を立てて、くやしがることをいいます。 | |||
| ニベもない | |||

鰾膠(ニベ)は魚の名前、その鰾(うきぶくろ)から粘着力の強い膠(にかわ)が取れます。 | |||
| 水魚の交わり | |||
|
非常に親密な友情、交際などをあらわす言葉で、語源は三国志にあります。 | |||
| とどのつまり | |||
 日本人の魚に対する関心は非常に高いものがあり、成長につれて名前を使い分ける出世魚もその例です。
日本人の魚に対する関心は非常に高いものがあり、成長につれて名前を使い分ける出世魚もその例です。そんな出世魚の中でもひときわ有名(?)なのがボラで、次のように成長につれて名前が変わります。 ハク ⇒ オボコ ⇒ スバシリ ⇒ イナ ⇒ ボラ ⇒ トド ものの行き詰まりを「とどのつまり」と言うのは、ここから来ています。 | |||
| 江戸っ子は 五月の鯉の 吹き流し 口先ばかりで はらわたはなし | |||
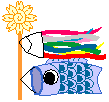 「吹流し」は風に泳ぐコイノボリのことで、吹き抜けになっていて腹の中が空洞になっていることから、
「吹流し」は風に泳ぐコイノボリのことで、吹き抜けになっていて腹の中が空洞になっていることから、江戸っ子というのは気が短く、言いたいことをポンポンと発し、その言葉使いも荒っぽいのですが、腹の中は空っぽでさっぱりしており、物事にこだわらないということをいっています。 また、口先ばかり威勢が良くて、胆力がないという意味もあるようです。 | |||
| 肴(さかな) | |||
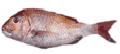
「肴(さかな)」ということばの語源は、「酒菜(さかな)」で、「菜(な)」はもともと飯の副食物「おかず」のことを指していました。
| |||
| カマトト | |||

本当は知っているのにちょっとおとぼけた少女のフリをするため「カマボコは魚(トト) から作るのかえ?」と尋ねるたのが語源といわれています。 | |||
| 魚と大根を同時に食べる理由 | |||

焼き魚ですと大抵一緒に大根おろしが付いてきますが、実はこの組み合わせには、味覚以外でも理由があるのです。 | |||
| たらふく食う | |||

腹いっぱいく食うことで、漢字で書くと「鱈腹食う」となります。 | |||
| 水清ければ魚棲まず(うおすまず) | |||

水が清らかすぎると、隠れる場所もエサも無いので魚は棲まないということから、 | |||
| くさっても鯛(タイ) | |||
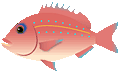
鯛はお祝いのときなどに食べるとても立派な魚。 | |||
| サバを読む | |||
|
「読む」は数えることで、都合のいいように数や年齢をごまかすことを意味し、江戸時代から使われています。
これには3つの説があると言われています。
| |||
| 目黒の秋刀魚(サンマ) | |||

落語の演題。 | |||
| アンコウの待ち食い | |||

アンコウは、暗い深い海の底にじっとしていて、背びれをゆらりゆらりとなびかせて魚たちを誘惑し、近づいてきたらその大きな口でパクリとります。
| |||
| 金魚のうんこ | |||
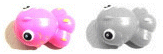
金魚の糞が細く長く連なっていることから | |||
| 柳の下のドジョウ | |||
|
前に捕まえたからといって、同じ柳の下でドジョウをまた捕まえられるとは限りません。 | |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |