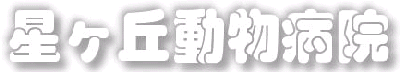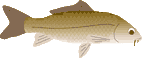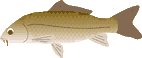|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 七皿食うて鮫臭い | |||
|
散々食べたあげく、サメ肉のようにまずい料理だと文句をつけること。
| |||
| 水を離れた魚 | |||
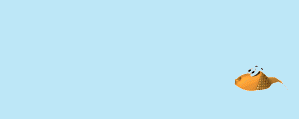
水から出たサカナのように、 頼りを失って自由がきかないことのたとえです。 | |||
| 清水に魚棲まず | |||
|
あまりにも心が清らかで欲のない人は、かえって人に親しまれないということです。 | |||
| 磯のカサゴは口ばっかり | |||
| |||
| イワシ七度洗えばタイの味 | |||
 
 
  イワシは脂肪が多く生臭い大衆魚ですが、よく洗って生臭みを落とせば、タイのような美味しい魚だという意味です。
ごく平凡な人間でも、よく磨けば能力を発揮できるようになるというたとえです。
イワシは脂肪が多く生臭い大衆魚ですが、よく洗って生臭みを落とせば、タイのような美味しい魚だという意味です。
ごく平凡な人間でも、よく磨けば能力を発揮できるようになるというたとえです。
| |||
| 網羅(もうら) | |||
 「網」は魚を捕るアミで、「羅」は鳥を捕るアミのこと。
この2つのアミで全てのものを集めることから、そのことに関するすべての情報を集めるという意味になりました。
「網」は魚を捕るアミで、「羅」は鳥を捕るアミのこと。
この2つのアミで全てのものを集めることから、そのことに関するすべての情報を集めるという意味になりました。
| |||
| 一網打尽 | |||
 一つの網で根こそぎサカナを捕獲することをいいます。そこから犯罪者を一挙に捕らえたときや、逃げ場を無くして取り尽くすことを表します。
一つの網で根こそぎサカナを捕獲することをいいます。そこから犯罪者を一挙に捕らえたときや、逃げ場を無くして取り尽くすことを表します。
宋の時代の検察官が犯罪者を一斉検挙した時に言ったとされてます。 | |||
| 炬燵で河豚汁 | |||
| |||
| 池魚籠鳥 | |||
 池に飼われているサカナや、かごの中のトリのことです。そこから不自由な身の上をいいます。
池に飼われているサカナや、かごの中のトリのことです。そこから不自由な身の上をいいます。
「池魚籠鳥に江湖山藪の思いあり」といえば、池のサカナやかごのトリは、大河や湖水、山や沢などの自由の天地にあこがれるのと同じに、 宮仕えの者が田園の閑日月にあこがれるということです。 | |||
| 沖の物を獲らんとして岸の物を逸す | |||
 
 沖は大漁を、岸は小魚を意味します。
沖は大漁を、岸は小魚を意味します。大きな利益を得ようとして、わずかな利益をも逃してしまうことをいいます。 | |||
| 麦飯で鯉を釣る | |||
|
わずかな元手で大きな利益を手に入れるたとえです。 | |||
| 雑魚の魚交じり(ざこのととまじり) | |||
 弱小者が強大者の中に交じっていることで、身分や能力・知恵の低い者が高い者に交じっていて不相応な地位にいるということです
弱小者が強大者の中に交じっていることで、身分や能力・知恵の低い者が高い者に交じっていて不相応な地位にいるということです
| |||
| 魚を得て筌(うけ)を忘る | |||
 荘氏から、魚を取ってしまえば筌(魚とりの道具)を忘れてしまうことから、いったん目的を達成すると、それまで役に立っていたものの恩恵も忘れてしまうものだということです。
荘氏から、魚を取ってしまえば筌(魚とりの道具)を忘れてしまうことから、いったん目的を達成すると、それまで役に立っていたものの恩恵も忘れてしまうものだということです。
| |||
| 鯖の生き腐れ | |||
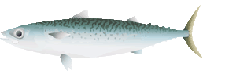 サバは外見は新鮮でも腐り始めていることがあります。
サバは外見は新鮮でも腐り始めていることがあります。サバの肉は漁獲してから短時間に酵素分解が進むので、人によっては蕁麻疹がでたりする事があるところからこのようにいいます。 | |||
| 夏座敷と鰈は縁側がよい | |||
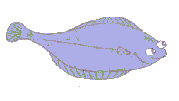 カレイの背びれと腹びれのつけ根を縁側といい、身が締まっていて特に美味しいと珍重されています。
カレイの背びれと腹びれのつけ根を縁側といい、身が締まっていて特に美味しいと珍重されています。また、 夏の座敷は風通しの良い涼しい縁側がとても良いものです。 この二つの縁側をかけ合わせた風流なことわざです。 | |||
| 田作りも魚のうち | |||
|
ゴマメのように小さな魚でも、魚の仲間に違いはないということから、 弱小で無力な者でも仲間には違いがないということです。 | |||
| 恋とはサメのようなものだ。常に前進してないと死んでしまう | |||
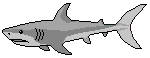 外洋を泳ぐ遊泳性のサメは自分の意志でエラを動かせないので エラを動かす為に、泳いでいないと息ができず呼吸出来ません。 恋愛も常に前進してないと、あっという間に終わってしまうものです。 だから動かないといけないのです。恋は常に前進あるのみなのです。 | |||
| 鮒の仲間には鮒が王 | |||
 つまらないものの集団では、やっぱりつまらないものが長になるということです。また程度のそうよくないもののなかでは、やはりそのようなものが頭になるということです。
つまらないものの集団では、やっぱりつまらないものが長になるということです。また程度のそうよくないもののなかでは、やはりそのようなものが頭になるということです。
| |||
| うちの鯛より隣の鰯 | |||
 ついうらやましく思うものであるということです。 | |||
| 生簀(いけす)の鯉 | |||
| |||
| 魯魚(ろぎょ)の誤り | |||
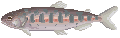 文字の誤りのことや、書き間違いのことをいいます。 | |||
| 小水の魚 | |||
|
| |||
| 淵に臨みて魚を羨むは退いて網を結ぶに如かず | |||
|
淵に面してサカナを欲しいと思ってただみているよりは、帰ってサカナを取る網を編んだほうが良い、ということから、他人の幸福をうらやむよりは、自分で幸福を得る工夫をすべきである、ということです。
| |||
| 鯉の一跳ね | |||
| |||
| 献上ものの鯛 | |||
 とびきりいいものを選んでいることから、いかにも姿がいい優れた容姿であることで、人並みはずれた美しさを意味します。
とびきりいいものを選んでいることから、いかにも姿がいい優れた容姿であることで、人並みはずれた美しさを意味します。
| |||
| 山の芋鰻になる | |||
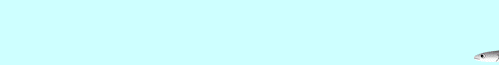
そのありえないことが起きるということから、 起こることのないことが起きることのたとえです。 思いもよらないほど変化することや、 普通の者が急に出世することをいいます。 | |||
| 天を指して魚を射る | |||
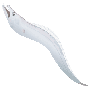 天を指してもサカナを射るが出来ないように、方法や力量を誤れば目的を達成することができないということ。
天を指してもサカナを射るが出来ないように、方法や力量を誤れば目的を達成することができないということ。また同時に「叶わぬ見当違いな望みを抱くこと」という意味もあります。 | |||
| 炬燵で河豚汁(こたつでふぐじる) | |||
|
| |||
| 恵比寿様が鯛を釣ったよう | |||
|
| |||
| 鉄砲 | |||
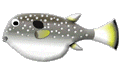 フグはめったにあたりませんが、毒は強くたまにあたれば死にます。鉄砲も実弾に当れば死傷することから、関東ではフグのことを「鉄砲」といい、略称として「鉄」とも呼ばれます。
「てっちり」は鉄(フグ)の入ったちり鍋、「てっさ」は鉄の刺身のことです。
フグはめったにあたりませんが、毒は強くたまにあたれば死にます。鉄砲も実弾に当れば死傷することから、関東ではフグのことを「鉄砲」といい、略称として「鉄」とも呼ばれます。
「てっちり」は鉄(フグ)の入ったちり鍋、「てっさ」は鉄の刺身のことです。
| |||
| 香餌の下必ず死魚あり | |||
|
| |||
| 一発カマス | |||
| |||
| サンマが出るとあんまが引込む | |||
 秋のサンマは脂が乗って栄養価がばっちり。食欲の秋にサンマを食べると元気が出て、あんまにかかる必要もなくなるということわざ。「サンマが出るとあんまが泣く」ともいいます。
秋のサンマは脂が乗って栄養価がばっちり。食欲の秋にサンマを食べると元気が出て、あんまにかかる必要もなくなるということわざ。「サンマが出るとあんまが泣く」ともいいます。
| |||
| 流れる川に大魚なし | |||
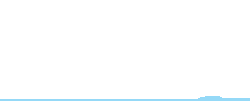 大きなサカナは川の大きな淵に棲み、流れの早い小さな川には棲みません。
大きなサカナは川の大きな淵に棲み、流れの早い小さな川には棲みません。
同じように、大人物が活躍できるためには、それ相応の場というものが必要で、その場があってはじめて能力が発揮されるということです。 | |||
| 魚腹に葬(ほうむ)らる | |||
|
サカナのエサとなって食われるということで、水死することや水に身を投げることをいいます。 | |||
| 事が延びれば尾鰭(おひれ)が付く | |||
 魚にはなくてはならない尾と鰭(ひれ)ですが、本体に付属するところから、余計なものの意になりました。
魚にはなくてはならない尾と鰭(ひれ)ですが、本体に付属するところから、余計なものの意になりました。そこから、物事は手早く進めないと、いろいろと余計なことが起こってやりにくくなる、ということをいっています。 | |||
| 呑舟の魚枝流に遊がず(どんしゅうのうおしりゅうにおよがず) | |||
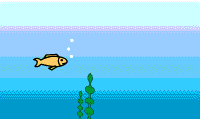 舟を呑むほどの大魚は小さな川には棲まないといいます。
舟を呑むほどの大魚は小さな川には棲まないといいます。そこから大人物はつまらない者と交わったりしないということ。また、大きな志をもつ人物は、細かいことにこだわらないということです。 | |||
| 干潟の鰯 | |||
| |||
| 魚を争う者は濡る | |||
|
利を得ようとする者は、苦痛をさけることはできないということです。 | |||
| 河豚と間男は食い初むと堪忍ならぬもの | |||
|
| |||
| 泥鰌(ドジョウ)の地団駄(じたんだ) | |||
|
| |||
| 鯛知らず | |||
| |||
| 地震とナマズ | |||
| |||
| 水広ければ魚大なり | |||
 水が広ければサカナは大きく、山が高ければ木は高くなるように、人も成功するためには、働く場所がよくなければならないということ。
また、上に立つ者の度量が大きくなければ、すぐれた部下は集まらないということです。
水が広ければサカナは大きく、山が高ければ木は高くなるように、人も成功するためには、働く場所がよくなければならないということ。
また、上に立つ者の度量が大きくなければ、すぐれた部下は集まらないということです。
| |||
| 呑鉤(どんこう)の魚は飢えを忍ばざるを嘆く | |||
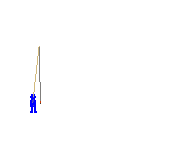 釣り針を飲み込んで釣り上げられたサカナが、「なぜもっと空腹をがまんしなかったのか」と悔やみ嘆くように、
ことが起きてから、後悔しても手遅れだということです。
釣り針を飲み込んで釣り上げられたサカナが、「なぜもっと空腹をがまんしなかったのか」と悔やみ嘆くように、
ことが起きてから、後悔しても手遅れだということです。後悔は先に立たないということです。 | |||
| アンコ型 | |||
 お相撲さんの体型で、丸くてどっしりしていて腹が突き出ている超肥満体型のことです。
お相撲さんの体型で、丸くてどっしりしていて腹が突き出ている超肥満体型のことです。
お腹にアンコが一杯詰まった鯛焼からではなく、姿かたちが魚のアンコウに似ているからで、つまってアンコ型となったようです。 逆のやせ体型のお相撲さんをソップ型といいます。 | |||
| 瓢箪で鯰をおさえる | |||
| |||
| 及ばぬ鯉の滝登り | |||
| |||
| 鯛も独りは旨からず | |||
 高級魚のタイのような旨いものでも、一人で食べたのでは美味しくありません。
高級魚のタイのような旨いものでも、一人で食べたのでは美味しくありません。食事はたくさんの人と食べたほうが美味しいということです。 | |||
| 水積もりて魚集まる | |||
|
| |||
| どじょうすくい | |||
 安来節の「どじょうすくい」の動きは本来はウナギ獲りで、大阪では屋号が「出雲屋」のウナギ屋が多く、出雲のウナギを使うところからともいわれ、また、出雲地方では盆踊りの後ドジョウを捕る風習があり、これらが融合して出来た動きといわれます。
安来節の「どじょうすくい」の動きは本来はウナギ獲りで、大阪では屋号が「出雲屋」のウナギ屋が多く、出雲のウナギを使うところからともいわれ、また、出雲地方では盆踊りの後ドジョウを捕る風習があり、これらが融合して出来た動きといわれます。
また、「どじょうすくい」は「土壌すくい」という説もあります。 これは、古来出雲は砂鉄の産地で、砂鉄をとる「カゴで土をさらい水でゆすいで砂鉄を採る」土壌すくいからその振りが付けられた、というもので、 踊り手がザルを持っているのは、砂金採りのように川で砂鉄と砂を振り分けるため、といわれています。 | |||
| ヒラメ社員 | |||
 ヒラメは海底の砂から目だけを出して、獲物がこないか、危険はないか常にキョロキョロと観察する習性があります。
それが、上司にこびへつらったり、能力以上の出世ばかりを気にしている社員の様子に似ていることからこういわれます。
ヒラメは海底の砂から目だけを出して、獲物がこないか、危険はないか常にキョロキョロと観察する習性があります。
それが、上司にこびへつらったり、能力以上の出世ばかりを気にしている社員の様子に似ていることからこういわれます。
| |||
| 魚は殿様に、餅は乞食に焼かせろ | |||
 焼き物のコツを表現した言葉で、適材適所ということです。
焼き物のコツを表現した言葉で、適材適所ということです。お魚は片身を七分どおり焼き上げてからひっくり返すと、身が焼き網にくっついたり身が崩れしないので、のんびりした殿様のように、あくせくしていない人にじっくり焼かせるのがよく、 餅を焼くにはよくひっくり返して焦げないよう万遍なく熱が加わるように焼くのがよいので、お腹を空かせ早く食べたくてしょっちゅうひっくり返しがちな貧乏人に適役ということです。 | |||
| 鮟鱇(アンコウ)武者 | |||
|
形ばかりという意味もあります。 | |||
| 鯔背(イナセ) | |||
 魚河岸の若い衆のあいだで流行した髪型の形が、ボラの若魚のイナの背ビレに似ていることから鯔背銀杏(イナセイチョウ)と呼ばれていました。
そこから、魚河岸の若い衆のように、気風がよくて、粋な若い人をいうようになりました。
魚河岸の若い衆のあいだで流行した髪型の形が、ボラの若魚のイナの背ビレに似ていることから鯔背銀杏(イナセイチョウ)と呼ばれていました。
そこから、魚河岸の若い衆のように、気風がよくて、粋な若い人をいうようになりました。
| |||
| 魚は江湖に相忘( あいわす ) る | |||
 | |||
| 河豚は食いたし命は惜しし | |||
| |||
| アラを探す | |||
|
| |||
| サメ肌 | |||
|
その突起のせいでサメを触るとザラザラした手ざわりがあり、そこから、荒れてザラザラした皮膚をサメ肌といいます。 昔はザラザラを利用して刀の柄(つか)などの武具に、今はわさびおろしにも使われています。 | |||
| 尾鰭(おひれ)が付く | |||
 尾と鰭は魚本来の付属物ですが、それがさまざまな形で余計に付け加えられ、
あることないこといろいろな事も付け加わり、話が大げさに誇張され複雑になることをいいます。
尾と鰭は魚本来の付属物ですが、それがさまざまな形で余計に付け加えられ、
あることないこといろいろな事も付け加わり、話が大げさに誇張され複雑になることをいいます。
| |||
| 網、呑舟(どんしゅう)の魚を漏らす | |||
 網の目が粗くて、舟を呑み込むほど大きな魚を漏らすことから、法律の不備により、大悪人・大罪人を捕らえきれずに取り逃がしてしまうことをいいます。
網の目が粗くて、舟を呑み込むほど大きな魚を漏らすことから、法律の不備により、大悪人・大罪人を捕らえきれずに取り逃がしてしまうことをいいます。
| |||
| とかくメダカは群れたがる | |||
| |||
| 以魚駆蠅(いぎょくよう) | |||
 サカナでハエを追うとすると、かえってますますハエが寄って来てしまいます。そこから、物事の処理や解決に間違ったやり方・方法を用いることをいいます。
サカナでハエを追うとすると、かえってますますハエが寄って来てしまいます。そこから、物事の処理や解決に間違ったやり方・方法を用いることをいいます。
| |||
| 大魚(たいぎょ)は小池(しょうち)に棲(す)まず | |||
|
不遇な人を慰めるための諺でしょう。 | |||
| 轍鮒の急(てっぷのきゅう) | |||
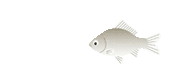 差し迫った危険、また、差し迫った困窮のたとえで、「轍鮒」はわだち(車輪の跡)の水たまりにいるフナのことで、以下のような荘子の故事に基づきます。
差し迫った危険、また、差し迫った困窮のたとえで、「轍鮒」はわだち(車輪の跡)の水たまりにいるフナのことで、以下のような荘子の故事に基づきます。
| |||
| 鯖折り(さばおり) | |||
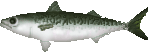 相撲では、両手で相手のまわしを引きつけ、自分の上背と体重で相手を圧して、相手の腰をくじいて押し倒す決まり手。
相撲では、両手で相手のまわしを引きつけ、自分の上背と体重で相手を圧して、相手の腰をくじいて押し倒す決まり手。
サバは傷みやすいので、鮮度を保つには釣り上げたらその場でエラに指を入れて首を折って血抜きをします。相撲の決まり手がこの様子に似ていたのでそのような決まり手の名前になったのでしょう。 | |||
| 鰯(イワシ)の頭も信心から | |||
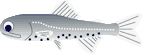
イワシの頭のようにつまらないものでも、不思議な力がやどっていると信じてしまえばそれなりの価値が出てきて、ありがたいものに見えてくる、ということです。
| |||
| 木によって魚(うお)を求む | |||
 木に登って魚がいないかと探すこと。やりかたがまちがっていれば、どんなにがんばっても目的は達成出来ないということ。
木に登って魚がいないかと探すこと。やりかたがまちがっていれば、どんなにがんばっても目的は達成出来ないということ。また出来そうもない望みをもつことをいいます。 | |||
| ごり押し | |||
| |||
| 若鮎 | |||
|
そこから、若くぴちぴちした人の姿の形容としても使われます。 | |||
| 魚の目に水見えず人の目に空見えず | |||
|
| |||
| 魚心あれば水心 | |||

魚に水と親しむ心があれば、水もそれに応じる心を持つという意味で、相手が自分に対して好意を持てば、自分も相手に好意を持つ用意があるということです。
| |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |