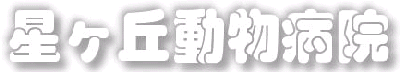|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 塒(とぐろ)を巻く | |||
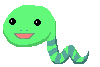
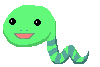 ヘビが長い体を渦巻きのように巻いて落ち着くさまをいいます。
ヘビが長い体を渦巻きのように巻いて落ち着くさまをいいます。また、複数の人が何をするでもなくある場所に集まって、長い時間いるさまなどを意味することもあります。 | |||
| 蛙鳴蝉噪(あめいせんそう) | |||
 やかましく騒ぎ立てたることや、くだらない議論や下手な文章のたとえです。
やかましく騒ぎ立てたることや、くだらない議論や下手な文章のたとえです。蛙や蝉がやかましく鳴き騒ぐように、ただ騒ぐだけで何の内容もないことから。 | |||
| 長蛇(ちょうだ)の列 | |||
|
転じて、延々と続いている人の列をたとえた表現です。 | |||
| 亀鑑(きかん) | |||
|
| |||
| 生殺しの蛇に噛まれる | |||
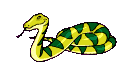 ヘビの息の根を完全に止めず、生かしも殺しもしない状態にしておくと、恨んだヘビが噛み付いてくることから。
ヘビの息の根を完全に止めず、生かしも殺しもしない状態にしておくと、恨んだヘビが噛み付いてくることから。
痛めつけたまま、半死半生の状態にしておくと、恨みを受けて害を招くことがあるということです。 | |||
| 蛙、オタマジャクシの時を忘れる | |||

お金持ちや権力者、地位の高い人が、昔の貧乏だった頃のことや苦労したり努力したりしていた頃のことを忘れてしまって、偉そうな態度に成ってしまうことを指して、このように表します。 | |||
| 亀毛 | |||
|
元の言葉は「亀毛兎角」で、カメの甲羅に毛が生えたりウサギの頭に角が生えるという意味から、本来ないもの、この世にあり得ないもの、実在するはずがない物事のたとえです。
元は戦争がおこる前触れのことをいった言葉ですが、いまは「神経質」「こだわりすぎる」という意味で使われます。 | |||
| 石亀の脚絆 | |||
|
脚絆(きゃはん)は脛の部分に巻く布や革でできた被服のこと。 | |||
| 蛇の足より人の足見よ | |||
|
そこから、役に立たないことを考えたり論じたりするよりも、身近なことについて考えるほうが大切だということです。 | |||
| 雁が飛べば石亀も地団駄 | |||
|
| |||
| 蛙におんばこ | |||
|
| |||
| 人捕(と)る亀は人に捕らるる | |||
| |||
| 蛇稽古(へびげいこ) | |||
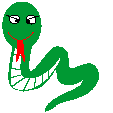 稽古事などが長続きしないことです。
稽古事などが長続きしないことです。ヘビは冬眠する動物で、暖かくなる春に冬眠から目覚めて、寒くなり始める秋には土の中に入ってしまいます。 そのヘビのように、春に活動を始めて秋にはやめてしまうことからこのようにいうようになりました。 | |||
| 蛇(くちなわ)の口裂け | |||
 ヘビは欲深く、自分の口より大きなものを口に入れようとして口が裂けることから、欲が深すぎるあまりに身を滅ぼしてしまうことをいいます。
ヘビは欲深く、自分の口より大きなものを口に入れようとして口が裂けることから、欲が深すぎるあまりに身を滅ぼしてしまうことをいいます。
| |||
| 鎮守の沼にも蛇は棲む | |||
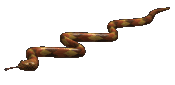 鎮守とは土地や施設などを守護する神のことで、ここでのヘビは邪悪なものをさします。
鎮守とは土地や施設などを守護する神のことで、ここでのヘビは邪悪なものをさします。
神聖な場所であってもヘビのような邪悪なものが棲みついているということから、悪人はどのような場所にでもいるものだということです。 | |||
| 盲亀の浮木 | |||
 大海の底にすみ、百年に一度だけ海面に出てくる盲目のカメが、海面に浮かぶ一本の木に出会い、その木にあいている穴に入ることは容易ではないという、仏教の説話から。
大海の底にすみ、百年に一度だけ海面に出てくる盲目のカメが、海面に浮かぶ一本の木に出会い、その木にあいている穴に入ることは容易ではないという、仏教の説話から。
もとは、仏または仏教の教えにめぐり合うことは、非常に難しいことをいったものですが、出会うことが甚だ困難であること、また、めったにない幸運にめぐり合うことのたとえになりました。 | |||
| 竜と心得た蛙子 | |||
 リュウになると期待していた我が子もやはりカエルの子に過ぎなかったということから、優れていると思い込んでいた我が子が、親と同様の凡才でしかなかったということで、親の欲目からくる見込み違いをいいます。
リュウになると期待していた我が子もやはりカエルの子に過ぎなかったということから、優れていると思い込んでいた我が子が、親と同様の凡才でしかなかったということで、親の欲目からくる見込み違いをいいます。
| |||
| 蛇の目を灰汁(あく)で洗ったよう | |||
 もともと鋭いヘビの目をさらに灰汁で洗うことで、眼光がきわめて鋭くなること。そこから、物事を明白にすることや、善悪を明らかにすることをいいます。
もともと鋭いヘビの目をさらに灰汁で洗うことで、眼光がきわめて鋭くなること。そこから、物事を明白にすることや、善悪を明らかにすることをいいます。
| |||
| 常山の蛇勢(じょうざんのだせい) | |||
 『孫子』より、先陣と後陣また右翼と左翼が、互いに連携して攻撃や防御をするため隙がない陣法のことをいいます。そこから、文章などの構成が一貫しており破綻がないことを表します。
『孫子』より、先陣と後陣また右翼と左翼が、互いに連携して攻撃や防御をするため隙がない陣法のことをいいます。そこから、文章などの構成が一貫しており破綻がないことを表します。
「常山」は中国五岳の一つで、ここに住む「卒然」という両頭のヘビは、首・胴・尾が連携して使われ、敵の付け入るすきがまったくなかったといいます。 | |||
| 流星光底長蛇を逸す(りゅうせいこうていちょうだをいっす) | |||
 せっかくの機会、またとない機会を逃してしまうことや、惜しいところで大敵を取り逃がしてしまうことのたとえで、
上杉謙信と武田信玄の川中島の合戦をうたった詩にあります。
せっかくの機会、またとない機会を逃してしまうことや、惜しいところで大敵を取り逃がしてしまうことのたとえで、
上杉謙信と武田信玄の川中島の合戦をうたった詩にあります。
江戸時代の儒学者、史家頼山陽の詩『不識庵の機山を撃つの図に題す』に「遺恨なり十年一剣を磨き、流星光底長蛇を逸す(十年の苦心もむなしく、撃ち損なってしまった)」とあるのに基づきます。 「底」は「下」の意味で「流星光底」は振り下ろす刀剣の閃光を流星にたとえたことばで「長蛇」は「大きな獲物」や「またとない機会」を表します。 | |||
| 蛇は竹の筒に入れても真っすぐにならぬ | |||
 生まれつき精神の曲がっているものは、どんなことをしても治すのは難しいものだということです。
生まれつき精神の曲がっているものは、どんなことをしても治すのは難しいものだということです。
| |||
| 蛇が出そうで蚊も出ぬ | |||
 ヘビのような恐ろしいものが出そうな予感がしていたが、実際は蚊ほどの小さいものさえ出ないということから、何か大きなことが起こりそうだが、実際はこれといって何も起きないということです。
ヘビのような恐ろしいものが出そうな予感がしていたが、実際は蚊ほどの小さいものさえ出ないということから、何か大きなことが起こりそうだが、実際はこれといって何も起きないということです。
| |||
| 蛙の目借り時 | |||
 おだやかな春の眠くてたまらない時期をいい、俳句の季語でもあります。
おだやかな春の眠くてたまらない時期をいい、俳句の季語でもあります。
春のひとときついうとうとしてしまうのは、カエルが人の目を借りるためだという俗説が古くからあり、カエルのオスがさかんに鳴いてメスを求める意の「妻(め)狩る」から転じたといいます。 | |||
| 信なき亀は甲を破る | |||
 約束を守らなかったカメが甲羅を割って死んでしまったという昔話から、約束を破ると身に災いを受けるということです。
約束を守らなかったカメが甲羅を割って死んでしまったという昔話から、約束を破ると身に災いを受けるということです。
| |||
| 草を打って蛇を驚かす | |||
 何気なくした行為が思いがけない結果を生ずること。また、一人を懲らしめて、それと関係する他の人をも戒めること。
何気なくした行為が思いがけない結果を生ずること。また、一人を懲らしめて、それと関係する他の人をも戒めること。
昔、中国に“王魯(おうろ)”という役人がいて、部下が同僚の収賄を告発してきたとき、実は自らもせっせとわいろを受け取っていたので、「お前は草を打っただけだが、蛇(自分)は驚きで十分こたえている」と答えた、という故事から、ある者を懲らしめることによって関連する者への戒めとするたとえ。 | |||
| 蛇婿入り | |||
 男性に身を変えたヘビが娘に求婚するもので、毎晩訪れてくる男の着物に針を通し、翌朝糸をたどって正体がヘビであることを知るという昔話の一つ。
男性に身を変えたヘビが娘に求婚するもので、毎晩訪れてくる男の着物に針を通し、翌朝糸をたどって正体がヘビであることを知るという昔話の一つ。
| |||
| 杯中の蛇影 ( はいちゅうのだえい ) | |||
 晋の楽広が友人宅で酒を飲んだ時、壁にかけてある蛇模様の漆絵が、杯の中に映ったのを本物のヘビと思い、ヘビを飲み込んだと勘違いして神経を病んで病気になってしまった。
後で、それが絵に描いたヘビだったこと聞いて納得し、たちまち治ったという故事。疑いをもてば、なんでもないことも神経を悩ますということです。
晋の楽広が友人宅で酒を飲んだ時、壁にかけてある蛇模様の漆絵が、杯の中に映ったのを本物のヘビと思い、ヘビを飲み込んだと勘違いして神経を病んで病気になってしまった。
後で、それが絵に描いたヘビだったこと聞いて納得し、たちまち治ったという故事。疑いをもてば、なんでもないことも神経を悩ますということです。
| |||
| 蛇は一寸にしてその貌(かたち)を知り、人は一言にてその志を知らる | |||
|
| |||
| 蛇は寸にして人を呑む | |||
 大蛇は一寸くらいの小さいころから、自分より大きな人間を呑むほどの勢いがある。偉人や英雄すぐれた人は幼いときから、普通の人と違った気概があるということのたとえです。
大蛇は一寸くらいの小さいころから、自分より大きな人間を呑むほどの勢いがある。偉人や英雄すぐれた人は幼いときから、普通の人と違った気概があるということのたとえです。
| |||
| 灰吹きへ載せた亀の子 | |||
|
| |||
| 蛙の願立て | |||
|
カエルが人間のように立って歩けるようにと願を立てて、清水寺にこもってその望みを達し、勇んで帰ろうとすると手足は前に向いているが、目はうしろに向いているため進む方向が分からず、歩けなくなりひからびて死んでしまったという話から。 | |||
| ヒキガエルが蚊を呑んだよう | |||
 何の苦もなく簡単に行うことや、小さすぎて問題にならないことをいいます。
何の苦もなく簡単に行うことや、小さすぎて問題にならないことをいいます。
| |||
| 蛇に噛まれて朽ち縄に怖じる(へびにかまれてくちなわにおじる) | |||
|
| |||
| 蛇に見こまれた蛙(カエル) | |||
|
蛙は蛇が苦手なので蛇を目の前にすると怖くて全く動けなくなってしまいます。そのことから、自分より強いものを目の前にしたときに、恐ろしさのあまり動けなくなってしまうことをいいます。
| |||
| 蛇の足より人の足見よ | |||
|
| |||
| 蛇の目傘 | |||
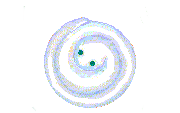 白い輪が入ったデザインが上から見た時に、ヘビの目に見える事から、この名前がつきました。現在は無地や各種柄物の和傘も全て蛇の目傘と呼んでおり、細身の美しい和傘の総称となっております。
白い輪が入ったデザインが上から見た時に、ヘビの目に見える事から、この名前がつきました。現在は無地や各種柄物の和傘も全て蛇の目傘と呼んでおり、細身の美しい和傘の総称となっております。
| |||
| 蛙の頬冠り( ほおかむり ) | |||
 カエルの目は背後にあるので、ほおかむりをすれば目がふさがれ、前方が見えないことから目先の見えないこと、目先の利かないことをいいます。
カエルの目は背後にあるので、ほおかむりをすれば目がふさがれ、前方が見えないことから目先の見えないこと、目先の利かないことをいいます。
| |||
| 蛇の生殺しは人を噛む | |||
 ヘビは生命力が強く簡単には死なず、半殺しにされてもまだ生きていて噛み付いてくることもあります。
ヘビは生命力が強く簡単には死なず、半殺しにされてもまだ生きていて噛み付いてくることもあります。物事の決着をうやむやにしておくと、後に思わぬしっぺ返しを受けることがある、というたとえです。 | |||
| カエルは口から呑まるる | |||

カエルは鳴くから居場所が分かって蛇に呑まれるということから、余計なことを言って自ら禍(わざわい)を招くことをいいます。 | |||
| 女の情けに蛇が住む | |||
|
| |||
| 鬼が出るか蛇(じゃ)が出るか | |||
 前途にはどんな運命が待ち構えているのか予測しがたいということのたとえです。
前途にはどんな運命が待ち構えているのか予測しがたいということのたとえです。直面する問題の答えが吉と出るか凶と出るか、不安に思う気持ちをあらわす言葉です。 | |||
| 蟒蛇(うわばみ) | |||
 巨大な蛇のことで、古代語の「おろち」に代わって用いられるようになった言葉。大蛇は大きなものでも何でも、沢山のみ込むというところから、大酒飲みのことをいうようにもなりました。
巨大な蛇のことで、古代語の「おろち」に代わって用いられるようになった言葉。大蛇は大きなものでも何でも、沢山のみ込むというところから、大酒飲みのことをいうようにもなりました。
| |||
| カエルの子はカエル | |||
 おたまじゃくしはカエルの子と思えぬほど似ていませんが大きくなると親と同じカエルになります。
おたまじゃくしはカエルの子と思えぬほど似ていませんが大きくなると親と同じカエルになります。そこから、子どもの才能や性質は親に似て、平凡な親の子どもはやはり平凡だということです。 | |||
| 蛇腹(じゃばら) | |||
|
| |||
| 亀の子束子(タワシ) | |||
 シュロを針金で巻いたタワシで、今では、束子(タワシ)の代名詞となっている亀の子束子ですが、西尾商店の独自のブランド名として商標登録もされています。
シュロを針金で巻いたタワシで、今では、束子(タワシ)の代名詞となっている亀の子束子ですが、西尾商店の独自のブランド名として商標登録もされています。
靴ふきマットの製造が専門であった会社で、潰れて返品されて山積みになっていたものを、ある日、社長の奥さまが丸めて洗い物をしていました。 それを見かけた社長が、これは商品になるとひらめき発明したといいます。 その形から「亀に似ている」ということと、洗う道具というのは、水にも縁がある亀は縁起も良いということで亀束子に、更に子をつけて親しみやすく『亀の子束子』と初代社長が命名したといいます。 | |||
| トカゲのしっぽ切り | |||
| |||
| 蛇口 (じゃぐち) | |||

 日本で水道が布設された明治中頃は、道路端に設けられた共用栓でした。これはイギリスからの輸入品で、ヨーロッパの水の守護神であるライオンのレリーフがついており、口から水が出るようになっていたのです。
日本で水道が布設された明治中頃は、道路端に設けられた共用栓でした。これはイギリスからの輸入品で、ヨーロッパの水の守護神であるライオンのレリーフがついており、口から水が出るようになっていたのです。
その共用栓が徐々に国産化されていく過程で、中国や日本の水の守護神である龍の形に変わり、そして「龍口」がいつしか「蛇口」と呼ばれるようになりました。 | |||
| カエル女房 | |||
|
| |||
| やぶをつついて蛇を出す | |||
 わざわざやぶをつついたりしたら、びっくりした蛇が出て来てしまうということから、しなくても良いことをしたために受けなくてもよい害を受けてひどい目にあうことをいいます。
わざわざやぶをつついたりしたら、びっくりした蛇が出て来てしまうということから、しなくても良いことをしたために受けなくてもよい害を受けてひどい目にあうことをいいます。省略して「やぶへび」ともいいます。 | |||
| Crocodile tears 鰐の空涙(ワニのそらなみだ) | |||
|
ワニは偽善の象徴とされ、涙を流しながら生き物を食べるという伝説から、見せかけの、偽りの涙のことをいいます。
| |||
| ウミガメの涙の正体は? | |||
|
ウミガメは卵を産むときに涙を流すとよくいわれますが、別にお産が苦痛で泣いているわけではなく、いつでも涙を流して泣いているんです。
| |||
| ヘビ頭じじい | |||

タイのことわざ。 | |||
| 井の中の蛙(カワズ)大海を知らず | |||
|
自分の考えがとてもせまく、広い世界にはいろいろなことがあるのを、何も知らないでいるたとえ。 または、見聞(けんしき)がせまいことをいいます。 | |||
| カメレオンの本当の色は? | |||
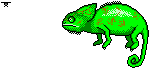
カメレオンは外敵から身を守る方法として環境によって体色を変化させますが、元々は何色なのでしょうか? | |||
| 亀の甲より年の劫(こう) | |||
|
「年の功」ともいいます。劫(こう)は仏教語で極めて長い時間のこと。 | |||
| 蛙の面に水(カエルのつらにみず) | |||

蛙は水の中や水のそばに住んでいるので、顔に水がかかっても全く平気な顔をしています。 | |||
| 出歯亀(デバガメ) | |||
|
この亀太郎、出っ歯だったため弁護人が彼を「出歯亀」と法廷で何度も連発したので、新聞などで大いに受けたのです。 そして現代にまで出歯亀という語は窃視趣味やその窃視行動を指す語として残ってしまいました。 | |||
| オタマジャクシ | |||

滋賀県にある多賀神社が「杓子(シャクシ)」と言うものを最初に販売していましたが、これが「御多賀杓子(オタガジャクシ)」と呼ばれていました。
| |||
| 穐(あき、シュウ) | |||

「あき」「とき」「みのり」「歳月」の意の漢字で、秋の俗字。禾と亀の合字。
| |||
| 蛇の道は蛇(ジャのみちはヘビ) | |||
|
ヘビの通る道は仲間のヘビには良く分かるの意から、同類の者には仲間のことなら、何でもよく分かるということです。 | |||
| カエル(カワズ)の行列 | |||
|
蛙が後足で立つと目が後ろ向きなために前が見えないということから、向こう見ずなこと。またそのような人々の集まりのことをいいます。 | |||
| 動物小話 「国語のテスト」 | |||

国語のテストで、「カエルの子は( )」の( )に適当な言葉を入れなさい、 | |||
| 月とスッポン | |||
|
同じように丸い形をしているけれども、池の表に浮かぶスッポンと池に映る月とは大きな隔たりがあリます。 | |||
| 蛇足(だそく) | |||
|
一人分しか酒が無いので、ヘビの画を一番先に描いた者が飲むことにしたところ、ある者が素早く仕上げたが他の者はほとんど出来ていないのを見て、足を書き足してもまだ時間があまるといって足を付けはじめた。
| |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |