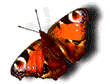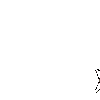|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 悪い虫がつく | ||||
|
衣類、書画などや穀類、農作物などに害虫がたかって そこなわれる状態もいいます。 また未婚の女性や、後家などに愛人ができたり、 遊女・若衆などに情夫ができるをいうこともあります。 父親が娘に交際相手ができたことを呪っていうことわざでもあります。 | ||||
| 鈴虫は音のために籠に飼われる | ||||
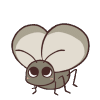 スズムシは美しい声を出すために、人に捕えられて籠に入れられ窮屈な生活を送ることになる。
という意味から、才能があるがゆえに、かえって不幸な生涯を送ることがあるということです。
スズムシは美しい声を出すために、人に捕えられて籠に入れられ窮屈な生活を送ることになる。
という意味から、才能があるがゆえに、かえって不幸な生涯を送ることがあるということです。
| ||||
| 鳴く虫は捕らる | ||||
|
| ||||
| 虫も殺さない | ||||
|
性質の優しい様子をいいます。 ムシさえも殺さないほどおとなしいさまで、 性質が穏やかでおとなしい人のたとえです。 | ||||
| 虫が知らせる | ||||
|
| ||||
| 虫が好かない | ||||
はっきりした理由はないが、何となく嫌だと思う様子。 | ||||
| 勝ち虫 | ||||
|
退かないところから不退転の精神を表すものとして、 「勝ち虫」と呼ばれ、縁起物として武士に喜ばれました。 戦国時代には兜や鎧、箙(えびら)刀の鍔(つば)などの武具、 陣羽織や印籠の装飾に用いられたそうです。 とんぼ柄は現在も、剣道具や竹刀袋の柄として 用いられることが多いようです。 | ||||
| 面々の蜂を払う | ||||
| ||||
| 蜘蛛の巣で石を吊る | ||||
 
 
ということで、 きわめて危険なことを することのたとえです。 | ||||
| 小の虫を殺して大の虫を助ける | ||||
|
| ||||
| 蝉は七日の寿命 | ||||
|
長年にわたり成虫として生きる期間は1-2週間ほどといわれていましたが、研究が進み2000年代頃から1か月程度と考えられるようになってきています。 2019年には岡山県笠岡市の高校生が独自の調査手法によりアブラゼミが最長32日間、ツクツクボウシが最長26日間、クマゼミが最長15日間生存したことを確認し発表して話題となりました。 | ||||
| 蒼蠅驥尾に付して千里を致す( そうようきびにふしてせんりをいたす ) | ||||
 アオバエが名馬の尾につかまって、自分では何もしないのに1日で千里の先まで行くということで、凡人が賢人や俊傑の後ろについて、功名をなすということのたとえです。
アオバエが名馬の尾につかまって、自分では何もしないのに1日で千里の先まで行くということで、凡人が賢人や俊傑の後ろについて、功名をなすということのたとえです。
また、すぐれた人に従って行けば、何かはなしとげられる。 先達を見習って行動することを、へりくだった気持ちでいう言葉でもあります。 「蒼蠅」は、アオバエで転じて君側のざん者、侫人のたとえになります。「驥」は一日に千里を走るという駿馬。 | ||||
| 虻(あぶ)もたからず | ||||
 
  誰も寄り付いてくれないことのたとえです。
誰も寄り付いてくれないことのたとえです。アブはよく人にたかってくるけれども、そのアブさえも寄ってこないということから。 | ||||
| 仙人の千年カゲロウの一時 | ||||
 仙人の寿命は千年、カゲロウの寿命はほんの一時ということから、長短の違いはあるがどちらも同じ一生であるということです。また、同じ一生でも長短の差が激しいことのたとえでもあります。
仙人の寿命は千年、カゲロウの寿命はほんの一時ということから、長短の違いはあるがどちらも同じ一生であるということです。また、同じ一生でも長短の差が激しいことのたとえでもあります。
| ||||
| クモの巣の高張り | ||||
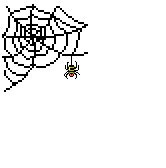 雨が降りそうなときはクモは巣を張らないので、クモが巣を張っていれば雨はなく、クモの巣に水滴がかかっているということは一時的な雨で いずれ晴れるということです。
雨が降りそうなときはクモは巣を張らないので、クモが巣を張っていれば雨はなく、クモの巣に水滴がかかっているということは一時的な雨で いずれ晴れるということです。
| ||||
| 蝉雪を知らず | ||||
|
そこから見聞の狭いことのたとえとして使われます。 | ||||
| 蚤の息も天に上がる | ||||
|
なし遂げることができるということです。 | ||||
| 蜘蛛の家に馬を繋ぐ | ||||
|
男に捨てられその恨みを果たすという女性の怨念を描いた能で、女が登場して始めの謡の内容から、 「クモの巣に荒れ馬を繋ぐことはできても、浮気男の心を捉えておくことはできない。そんな男に身をまかせまいと思っていたのに・・・。」 | ||||
| バタフライ効果 | ||||
|
| ||||
| 芋虫でもつつけば動く | ||||
|
| ||||
| 蛾の火に赴くが如し | ||||
| ||||
| 阿呆の鼻毛で蜻蛉をつなぐ | ||||
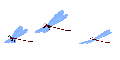 愚かな者が、自分は鼻毛を伸ばしてその先にトンボをつなげることができると誇張した言葉から、
愚かな者が、自分は鼻毛を伸ばしてその先にトンボをつなげることができると誇張した言葉から、何もかも馬鹿らしいことを意味します。 | ||||
| 尺蠖(しゃっかく)の屈するは伸びんがため | ||||
| ||||
| 蚊集まりて動すれば雷となる | ||||
|
| ||||
| 蟻の塔を組む如し | ||||
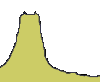 小さなアリが落ち葉や土を積み上げ、ついには高い蟻塚を築くことができます。
小さなアリが落ち葉や土を積み上げ、ついには高い蟻塚を築くことができます。弱小な者でも、こつこつと怠りなく努力を重ねていけば、いつかは大事業を成し遂げることができるということのたとえです。 | ||||
| 蜻蛉返り(とんぼがえり) | ||||
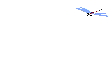 トンボが飛びながら、軽く身をひるがえして後ろへ戻るところから、地面をけって空中でからだを一回転させること。また、ある場所に行って用を済ませ、すぐに戻ってくることをいいます。
トンボが飛びながら、軽く身をひるがえして後ろへ戻るところから、地面をけって空中でからだを一回転させること。また、ある場所に行って用を済ませ、すぐに戻ってくることをいいます。
| ||||
| 群蟻腥羶に付く (ぐんぎせいせんにつく) | ||||

  腥羶(せいせん)はなまぐさいもののことで、羊の肉のことをいいます。
腥羶(せいせん)はなまぐさいもののことで、羊の肉のことをいいます。たくさんのアリが羊肉に集まることから、多くの人々が利のあるところに群がり集まってくる様のたとえです。 | ||||
| 頭の上のハエを追え | ||||
|
| ||||
| 雪隠虫も所贔屓(せっちんむしもところびいき) | ||||
|
| ||||
| 蟻の熊野参り | ||||
   
| ||||
| ほたるとヘビの眼とは同じように光る | ||||
  ヘビの眼は、月の夜などホタルのように光るといいます。だから、草薮で光るのはホタルとは限らず、ヘビの目かもしれないから「迂闊に素手で捕まえようとするな」ということです。
ヘビの眼は、月の夜などホタルのように光るといいます。だから、草薮で光るのはホタルとは限らず、ヘビの目かもしれないから「迂闊に素手で捕まえようとするな」ということです。
| ||||
| 蚊の脚に鑢(やすり)をかける | ||||
| ||||
| 顎で蝿を追う | ||||

追い払う事ができないくらい体力が衰えた様子をいいます。 | ||||
| 蜂払い(はちばらい) | ||||
| ||||
| 螢火 (けいか)を以て須弥(しゅみ)を焼く | ||||
 須弥は仏教の世界観で世界の中心にそびえる高山。
ホタルの火で須弥山のような大きな山を焼いてしまおうということで、微力を用いて、大きな仕事をしようとすることや、
力が足りないのに大きな事をしようとして努力しても、そのかいのないことをいいます。
須弥は仏教の世界観で世界の中心にそびえる高山。
ホタルの火で須弥山のような大きな山を焼いてしまおうということで、微力を用いて、大きな仕事をしようとすることや、
力が足りないのに大きな事をしようとして努力しても、そのかいのないことをいいます。
| ||||
| 蜻蛉(とんぼ)の鉢巻きで目先が見えぬ | ||||
| ||||
| 柱には虫入るも鋤(すき)の柄には虫入らず | ||||
|
| ||||
| 蚕食 ( さんしょく ) | ||||
|
端から次第に奥深く他の領域を侵略すること。 または片はしから他国の領土を侵略することで、少しずつ、でも確実に食い尽くされる怖さを感じます。 | ||||
| 蟻の甘きにつくがごとし | ||||
|
| ||||
| 追剥原へ蛍狩り(おいはぎはらへほたるがり) | ||||
 追いはぎの出るという原へ、ホタル狩りに出かけるのは危険であるように、自分から求めて危険なところへ行くことをいいます。
追いはぎの出るという原へ、ホタル狩りに出かけるのは危険であるように、自分から求めて危険なところへ行くことをいいます。
| ||||
| 蜂の巣をつついたよう | ||||
| ||||
| 青蠅白を染む ( せいようはくをしむ ) | ||||
   
| ||||
| 蟻の思いも天に昇る | ||||
| ||||
| 蟻の這い出る隙(すき)もない | ||||
|
| ||||
| 虫唾(むしず)が走る | ||||
|
そこから吐き気を覚えるほどに不快、激しく嫌うことをいいます。 | ||||
| 蠅がたかる | ||||
| ||||
| 水に燃えたつ蛍 | ||||
| ||||
| 蟻集まって木揺がす | ||||
|
アリのような弱小な虫でも、たくさん集まれば木を動かすようになるところから、無力な群集でも恐ろしい、ということ。
また、無力なアリが集まっても木を揺るがすことはできず、身分不相応な望み、ということにたとえることもあるそうです。
| ||||
| みみず腫れ | ||||
|
| ||||
| 虫が付く | ||||
|
| ||||
| 虫がいい | ||||
|
| ||||
| やれ打つな ハエが手をする 足をする | ||||
|
俳人小林一茶の有名な句ですが、拝むようなその姿を見るとハエたたきで打とうとするとき少しかわいそうに思います。 | ||||
| 極楽トンボ | ||||
| ||||
| おけらになる | ||||

一文無し、所持金が全然無くなるという意味で、「おけら」は、昆虫の「ケラ」の俗称です。 | ||||
| 蜉蝣の一期(ふゆうのいちご) | ||||
|
カゲロウの一生は朝生まれて夕方には死んでしまうほど短いことから、人生の短くはかないことのたとえとして使われます。 | ||||
| 蝶番(ちょうつがい) | ||||
|
| ||||
| 蜻蛉玉(とんぼだま) | ||||
 ガラス製の玉の一種で、丸い玉の表面に二色以上の色ガラスでまだらの文様などを表したものです。
ガラス製の玉の一種で、丸い玉の表面に二色以上の色ガラスでまだらの文様などを表したものです。トンボの複眼に似ていることからこのようにいわれ、古墳の副葬品として出土もしているほど古くからあります。 英語ではBEADS、またはGLASS BEADSといいます。 | ||||
| 蜂起(ほうき) | ||||
| ||||
| 蚊のまつげに巣食う | ||||
| ||||
| グラスホッパー (カクテル) | ||||
 Ggrasshopperとは、英語でバッタやキリギリスの事で、このカクテルの色合いからつけられました。
Ggrasshopperとは、英語でバッタやキリギリスの事で、このカクテルの色合いからつけられました。
ミントリキュール・カカオリキュール・生クリームでつくられており、香り高く、コクがあり、舌ざわりものどごしも、非常になめらかなカクテル。 極甘口なので食後のデザートがわりにもなります。 | ||||
| 胡蝶の夢(こちょうのゆめ) | ||||
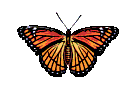 荘子が、蝶になって百年間花上に遊んだ夢を見て目覚めたが、自分が夢の中で蝶になったのか、蝶が夢の中で自分になっているのか分からなくなったという故事。
そこから現実の世界と夢の世界の区別がつかないこと、またこの世のはかないことをいいます。
荘子が、蝶になって百年間花上に遊んだ夢を見て目覚めたが、自分が夢の中で蝶になったのか、蝶が夢の中で自分になっているのか分からなくなったという故事。
そこから現実の世界と夢の世界の区別がつかないこと、またこの世のはかないことをいいます。
| ||||
| ゴキブリ | ||||
| ||||
| 虫の息 | ||||
|
虫のようなあるかないかわからないくらいの呼吸ということで、今にも息を引きとりそうな弱々しい呼吸のこと。 | ||||
| スカラベ SCARAB(フンコロガシ) | ||||
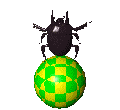
ファーブルが「昆虫記」の中で研究した虫としても有名で、タマオシコガネやフンコロガシの学名でもあります。 | ||||
| きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに 衣かたしき ひとりかも寝む | ||||
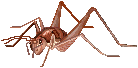
「こおろぎがしきりに鳴いている。白々と霜のおりているこの寒い夜を、寒々としたむしろの上に私は着物の片方の袖を敷いて、一人寂しく寝るのだろうか。」
| ||||
| ウクレレ | ||||

 ハワイ語で「ウク」が蚤(ノミ)、「レレ」が跳ねるの意味で、「ウクレレ」とは「跳ねるノミ」が語源だそうです。
ハワイ語で「ウク」が蚤(ノミ)、「レレ」が跳ねるの意味で、「ウクレレ」とは「跳ねるノミ」が語源だそうです。これはウクレレを弾く指の動きが飛び跳ねるノミのように見えたから、というものと、歌い踊る姿がノミが跳ねるように見えたから、という説があるそうです。 | ||||
| 玉虫色 | ||||
|
玉虫の羽根は、見る角度や光の当たり具合で、金紫色や金緑色に見えたり美しいもので、高価な着物や各種装飾に使われていました。 | ||||
| 蜘蛛(クモ)の子を散らす | ||||

クモの子が入っている袋を破ると、 たくさんの子クモが四方八方に散るところから、 大勢の人間が散り散りに逃げ惑う様子をいいます。 | ||||
| 夏の虫、氷を笑う | ||||
|
夏の虫が冬の氷のことを理解できずに氷のことを笑う、ということから、見識の狭いことや無知なことをいいます。
| ||||
| 蚤(ノミ)の夫婦 | ||||

ノミのメスはオスより大きいというところから、夫より妻の方が、身体が大きい夫婦のことをいいます。 | ||||
| 蟷螂の斧(とうろうのおの) | ||||
|
「蟷螂」とはカマキリのこと。カマキリがその前足を斧(おの)のように振り上げて、大きな車に襲(おそ)いかかろうとする様子から、力のない者が、自分の力量も考えずに力の強い者に立ち向かうこと、むだな抵抗のことをあらわします。
| ||||
| 一寸(いっすん)の虫にも五分の魂 | ||||

小さく弱い者にも、意地や考えがあるからあなどってはならないということ。 | ||||
| 泣きっ面に蜂 | ||||
 つらい目にあって泣いているところに、 | ||||
| 尻切れトンボ | ||||

トンボの尾はやわらかくて切れやすく、切れると飛べなくなってしまいます。 | ||||
| 蓼(たで)食う虫もすきずき | ||||
|
人の好き嫌いは人それぞれさまざまである、ということ。好みは人によって違う、ということ。または、物好きなことのたとえです。 | ||||
| 飛んで火に入る夏の虫 | ||||

夏の虫にはあかりを求めて飛んで来ては、勝手に火に落ちて身を焼やいて死んでしまうものがいます。 | ||||
| 蝶よ花よ | ||||
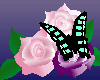
親が自分の娘を可愛がり、大事にする様子です。 | ||||
| 蚊の目玉のスープ | ||||
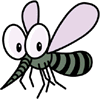 何でも食材にする中華料理のメニューの中には
何でも食材にする中華料理のメニューの中には「蚊の目玉のスープ」などという物もあります。 実はあれは大量に蚊を食べたコウモリの糞の中にある 未消化の蚊の目玉を集めて調理した物だそうです。 美 ? 味 ? し ? い ? | ||||
| 虫の居所が悪い | ||||
|
腹の中にいる虫のいるところが悪いので、不快である。気分が悪い。ということで、八つ当たりしたくなるような不機嫌な状態のことです。
| ||||
| アメンボ | ||||
 
アメのような甘い匂いを出すところから | ||||
| 朝のクモは福が来る、夜のクモは盗人が来る | ||||

朝の蜘蛛(クモ)は福を持ってくるので殺してはいけないが、夜の蜘蛛(クモ)は泥棒が来る前ぶれなのでかならず殺しなさいという言い伝えです。
| ||||
| 千丈の堤も蟻の一穴より | ||||
|
どんな小さな事でも油断すると大変な事になるということです。 | ||||
| 蛍雪(けいせつ) | ||||
|
苦労して勉強することや苦心して学問をすることをいいます。
| ||||
| コンピューター用語の「bug(バグ)」 | ||||
| ||||
| 夜の蝶 | ||||
| ||||
| 蚕(カイコ) | ||||
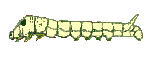
カイコが作る繭(まゆ)から生糸がとれ絹になります。 | ||||
| 恋に焦がれて 鳴く蝉(セミ)よりも 鳴かぬ蛍(ホタル) が身を焦がす | ||||
|
恋心を表に出すものよりも、口に出して言わないものの方が思いは切実であるということです。
| ||||
| モンシロチョウ | ||||
紋が黒いのになぜモンシロチョウ「紋白蝶」という名前なのでしょう。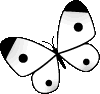
もともとの正式和名は、紋が黒くて白い蝶ということで「モンクロシロチョウ」でした。 ところが名前が長くて覚えにくい、ということで、最初の国定教科書に載せるときに省略して「モンシロチョウ」としてしまったのです。 ですから「モンシロチョウ」は白い紋のある蝶という意味ではなく、紋のある白い蝶と解釈しなければいけないのです。 | ||||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |



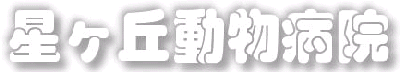


 灯火をめがけて飛んでくる
灯火をめがけて飛んでくる