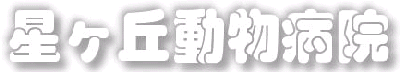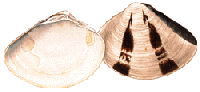|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 蛤女房 | |||
  
   昔々、ある海辺で漁夫の男が漁をしていると、とても大きなハマグリが獲れました。しかしこの大きさまで育つのは大変だったろうと思い、海へ逃がしてやりました。
昔々、ある海辺で漁夫の男が漁をしていると、とても大きなハマグリが獲れました。しかしこの大きさまで育つのは大変だったろうと思い、海へ逃がしてやりました。
しばらく後男のもとに美しい娘が現れ、嫁にしてほしいと言いました。男の妻となった娘はとても美味しいダシのきいた料理を作り、特に味噌汁が絶品でした。 しかし妻は、なぜか料理を作っているところを決して見ないよう、男に堅く約束させたのです。 しかし男は、どうすればこんなうまいダシがとれるのかと好奇心に負け、ついに妻が料理をしているところを覗いてしまいました。何と、妻は鍋の上に跨がって排尿していました。 男は怒って妻を追い出した。妻は海辺で泣いていたが、やがて元の姿を現しました。それはかつて男が命を助けた大ハマグリでした。そしてハマグリは海へと帰っていきました。 | |||
| 塗り箸で海鼠を挟む | |||
|
そこから無意味な骨折りや無駄な努力をいいます。 | |||
| 蟹は食ってもガニ食うな | |||
 いくらカニが美味しくても、エラまで食べてはいけないということです。
いくらカニが美味しくても、エラまで食べてはいけないということです。
ガニとはカニのエラのことで、毒はありませんが寄生虫の恐れがあり、昔の人はこれを食べると中毒を起こすと考えていたようです。 | |||
| いかさま(烏賊様・如何様) | |||
|
| |||
| 内で蛤、外では蜆 (うちではまぐり、そとではしじみ) | |||
|
| |||
| タコの糞で頭に上がる | |||
|
| |||
| 石蟹の穴へ海蟹は入らず | |||
|
| |||
| 畑に蛤 | |||
|
| |||
| 命あれば海月も骨に会う | |||
|
長く生きていると、めったにない幸運にめぐりあうこともあることのたとえ。また、命を粗末にせず、長生きするように心がけよという意味にも使う。骨のないくらげも長生きしていると、骨に出会って骨のあるくらげになるかもしれません。
| |||
| 蛸部屋 | |||
|
戦前の炭鉱で、炭塵で真っ黒になった顔とタコに墨をかけられた顔をかけているようでもあります。 | |||
| 慌てる蟹は穴へ入れぬ | |||
| |||
| 蝦踊れども川を出でず | |||
 エビはどんなにはねても一生川から出られません。
エビはどんなにはねても一生川から出られません。物にはそれぞれ定められた天分があり、運命が定まっていて、能力を超えた働きはできないということです。 | |||
| 海月の行列 | |||
|
| |||
| サザエに金米糖(こんぺいとう) | |||
|
| |||
| イカの手は食うてもその手は食わぬ | |||
|
| |||
| 蛸配 | |||
|
| |||
| 貝を以って海を測る | |||
|
| |||
| 水母(くらげ)の風向かい | |||
| |||
| 茹で蛸のよう | |||
 酔ったり長湯をしたり、また激怒して、ゆでたタコのように顔や体がすっかり赤くなっている様子です。
酔ったり長湯をしたり、また激怒して、ゆでたタコのように顔や体がすっかり赤くなっている様子です。
| |||
| ガニマタ(蟹股) | |||
つま先が外向きに開いていることで、歩き方がカニに似ているようにみえることから、カニ歩きのようだと揶揄した言葉らしいです。
| |||
| 蟹の死ばさみ | |||
|
| |||
| 賃(チン) | |||

「やとう」「金を払って人を使用する・かりる」「報酬の金銭・代価」「給料」の意の漢字。
| |||
| 月夜の蟹 | |||
 カニは月夜には月光を恐れ、エサを捕らないために身が少ない、または、満月や新月に浅瀬で抱卵するカニは簡単に捕獲できるが、産卵に来たので見入りが少ないので、獲っても仕方が無いということから、
見かけ倒しで中身のないことや頭のなかが空っぽで思考力に欠けることをいいます。
カニは月夜には月光を恐れ、エサを捕らないために身が少ない、または、満月や新月に浅瀬で抱卵するカニは簡単に捕獲できるが、産卵に来たので見入りが少ないので、獲っても仕方が無いということから、
見かけ倒しで中身のないことや頭のなかが空っぽで思考力に欠けることをいいます。
| |||
| ひっぱりだこ | |||

人気者という意味の「引っ張りだこ」ですが、これはタコを干すときに引っ張られた形から出たもので、その格好から、方々から引く手あまたである、四方八方から求められ期待される。そういう意味に変わっていって、使われるようになったと思われます。
| |||
| 熨斗(のし) | |||
 水引の右上、紅白の紙を六角形に折った飾りの中から垂れている黄色い紙のこと。
水引の右上、紅白の紙を六角形に折った飾りの中から垂れている黄色い紙のこと。弔事では避ける魚介類や鳥獣肉は、慶事の際には酒に添える縁起の良い贈り物として扱われましたが、その代表がアワビの肉を薄く長く剥ぎ、のして乾燥させた「熨斗鮑(のしあわび)」でした。それが形式化され贈答品の印とされたそうです。 現在では簡略化され、色紙で作った熨斗、その形を印刷した判熨斗、さらには「のし」という字を一筆書きしただけの文字熨斗などいろいろな種類があります。 | |||
| 海老固め(エビがため) | |||
|
プロレスでは相手が仰向けのところを、両足か片足を持ち海老状に、背中方向に極め、股関・膝・踝の3関節の同時に極める技。 | |||
| 平家蟹(へいけがに) | |||
 甲羅の表面が憤怒と苦悶の表情に見えることから、壇之浦の合戦で亡くなった平家の武将の、怨霊が乗り移ったとの伝説から名づけられました。
甲羅の表面が憤怒と苦悶の表情に見えることから、壇之浦の合戦で亡くなった平家の武将の、怨霊が乗り移ったとの伝説から名づけられました。
瀬戸内海沿岸に多く住んでおり、昔は壇ノ浦では網にかかると地元の漁師たちは「平家の怨霊」を偲び、大切に取り扱って神社へ奉納したそうです。 | |||
| 財(ザイ) | |||

「たから」「価値あるものの総称」「はたらき」「材料」の意の漢字。
| |||
| カニ族 | |||
|
登山家のスタイルのことで、大きなリュックサックと 費用を切り詰めた低予算が特徴でした。  当時の大きなリュックサックは横長で、背負ったままでは列車内や出入り口は、カニのように横向きにしか歩けなかったこと、背負った姿そのものがカニを思わせることからこう呼ばれました。
当時の大きなリュックサックは横長で、背負ったままでは列車内や出入り口は、カニのように横向きにしか歩けなかったこと、背負った姿そのものがカニを思わせることからこう呼ばれました。
| |||
| 蟹挟み(かにばさみ) | |||
 柔道の場合、相手の横にまわり込んで、ジャンプしながら相手の両足を前と後ろからはさみつけて相手を後ろに倒す技。
柔道の場合、相手の横にまわり込んで、ジャンプしながら相手の両足を前と後ろからはさみつけて相手を後ろに倒す技。レスリングの場合は、片足をとられた時に、他の足で相手の両足を後ろから払い、倒れた相手の胴を両足ではさみつける技。 | |||
| タコは身を食う | |||
|
タコは空腹になると自分の足まで食うということから、どうしようもなくなって、元手の資本や財産を食い減らすことをいいます。
| |||
| 蟹文字 | |||
| |||
| 蟹の念仏 | |||
|
口の中でぶつぶつとつぶやいていることをいいます。 | |||
| 鱈場蟹(タラバガニ) | |||
 名前は漁場がタラの漁場と重なることに由来しており、カニという名前はついているけどカニではありません。
名前は漁場がタラの漁場と重なることに由来しており、カニという名前はついているけどカニではありません。ズワイガニや毛ガニの脚の数は10本ですが、タラバガニの脚の数は8本で、ヤドカリの仲間なのです。 | |||
| その手は桑名の焼き蛤(ハマグリ) | |||

「食わない」と、焼きハマグリの名物である「桑名」の地名にかけて、「その手は食わない」(その計略には乗らない)という意味の洒落。
| |||
| 蛸(タコ) | |||
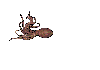
普通「虫へん」は虫や爬虫類にしか使用されないのですが、蛸(タコ)には使われています。 | |||
| 蟹(カニ)は甲羅に似せて穴を掘る | |||
|
蟹は自分の甲羅の大きさに合わせて穴を掘るものだということから、人は自分の力量や身分に応じた言動をするものだということ。 | |||
| 貨(カ) | |||

「たから」「価値あるもの」「品・商品」「たからを送る」の意の漢字。
| |||
| “イカ”はどうして“烏賊”? | |||
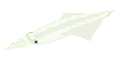
イカはどうして「烏(からす)の賊」と書くのでしょうか? | |||
| 賀(ガ) | |||

「いわう」「よろこぶ」「ものや言葉を贈り祝う」「ねぎらう」の意。
| |||
| ホラ吹き | |||

ホラ吹きの「ほら」は、漢字で「法螺」と書き、法螺貝に細工をした吹奏楽器のことです。
| |||
| ゾウリムシ | |||
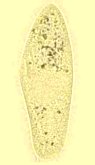
微生物の学習で登場するゾウリムシですが、確かにその姿が草履(ぞうり)に似ているので名前にもなっとくしてしまいますね。しかし草履が存在しない国では何と呼ばれているのでしょうか?
| |||
| 蜃気楼(しんきろう) | |||
 「蜃気楼」は中国人が名付けたされており
「蜃気楼」は中国人が名付けたされており「蜃」は大きなハマグリのことを指します。 昔中国では「蜃気楼」はハマグリが吐き出す「気」が楼やお城を描き出すと信じられていたため、“蜃が吐く気でできる楼”となったのです。 | |||
| 貧(ヒン、まずしい) | |||

「まずしい」「財産が少ない」「学問がとぼしい」「少ない」「足りない」の意の漢字。
| |||
| 「ちゅうちゅうたこかいな」 | |||
|
これは一種の数え歌で、最初のルーツは、平安時代の貴族達のすごろく遊びからで、その最中に2が重なる事を「重二(ちょうに)」と言い「重二重二」と二度続けていっていました。 これが江戸時代になると、遊び人たちは丁半ばくちで2つ振ったサイコロの目が共に2の目を出した場合「重二(ジュウニ)」と言うようにが変化しました。その「ジュウニ」が次第に「チュウニ」へと代わり「ちゅうちゅうたこかいな」で唱われる「ちゅう」に変わったのです。 何故その後に「たこかいな」が付くかというと、「チュウニ=ちゅう」は2が重なる事を意味していた。つまり「2+2=4」と言う事になり、2度言うということから「(2+2)+(2+2)=8」となり、8と言えばタコの足の本数になるので「ちゅう・ちゅう」と来たら「たこかいな」と言うワケなのです。
| |||
| 貸(タイ、かす) | |||

「かす」「ゆるい」「かりる」「金品を一時用立てる」の意の漢字。
貝と代の合字。 | |||
| セピア(sepia) | |||
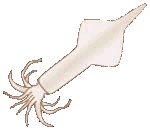 セピアとは黒に近い褐色のこと。
セピアとは黒に近い褐色のこと。セピアは元々、イカの墨から作る暗褐色の絵の具のことで、sepiaの語源はラテン語の「コウイカ」です。 イカ墨で描いた絵や文字は、日光などで色褪せ、薄い褐色に変化します。 この変化した後の色が、写真などで言われる「セピア色」で、イカ墨絵の具の色「セピア」とは異なります。 | |||
| ぐれる | |||
| |||
| 蝸牛(カギュウ)角上(かくじょう)の戦い | |||

カタツムリの角の上のようなせまいところで争うという非常につまらない争いのことをいいます。
| |||
| 蛸足配線(タコあしはいせん) | |||
|
多数の電気器具を接続するため、一つのコンセントから多くのコードを引くこと。 | |||
| 磯の鮑(あわび)の片思い | |||


「片思い」をシャレて言う言葉。 | |||
| ヤカンの蛸(たこ) | |||

ヤカンに入れられた蛸(タコ)のことで、 | |||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |