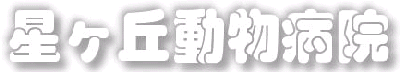|
話を入れ替えた折、削除した過去の分のお話です。
|
| 虎狼は防ぎ易く鼠は防ぎ難し | ||||
 大きな事や非常に大切なことは事前に計画を立てるなどして、慎重に対処するから意外と失敗しないものですが、小さな事には準備もせずに軽く対処することがあるで、かえって失敗しがちである、というたとえです。
大きな事や非常に大切なことは事前に計画を立てるなどして、慎重に対処するから意外と失敗しないものですが、小さな事には準備もせずに軽く対処することがあるで、かえって失敗しがちである、というたとえです。
| ||||
| 虎の子渡し | ||||
 トラが子を3頭生むと、その中には必ずヒョウが1頭いて他の2頭を食べてしまう、といいます。
トラが子を3頭生むと、その中には必ずヒョウが1頭いて他の2頭を食べてしまう、といいます。ある日川を渡らなければならないのに船は一艘しかなく、しかも船には一度に母トラを含めて二匹しか乗れません。 川を渡る際に子をヒョウと2頭だけにしないよう子の運び方に苦慮するという故事から、生計のやりくりに苦しむことのたとえです。 母トラはどのようにして、子供三頭を向こう岸に渡したのでしょうか? 母トラは、最初にヒョウを船に乗せ向こう岸においてきます。そして一頭で戻りトラの子1頭を船に乗せて向こう岸に渡りそのトラの子を残し、ヒョウを連れて帰ります。戻ったところで残りのトラの子を乗せてヒョウは置いてきます。そして最後に母トラのみで戻りヒョウを連れてきます。 | ||||
| 猛虎伏草 | ||||
|
英雄は隠れていても必ず世に現れる、ということです。 | ||||
| 虎伏す野辺、鯨寄る浦 | ||||

 野生のトラが生息する野、クジラが泳ぎ寄ってくる海辺という意味から、人があまり行ったことのない土地や未開な土地のことをいいます。
野生のトラが生息する野、クジラが泳ぎ寄ってくる海辺という意味から、人があまり行ったことのない土地や未開な土地のことをいいます。
| ||||
| 虎狼より漏るが怖い | ||||
 どこにいるか分からないトラやオオカミよりも、自分が今住んでいる家の雨漏りの方が直接被害を受けるぶんだけ恐ろしい、いうことです。
どこにいるか分からないトラやオオカミよりも、自分が今住んでいる家の雨漏りの方が直接被害を受けるぶんだけ恐ろしい、いうことです。
また、トラやオオカミのことより、隠していることが漏れて広まってしまうことや、自分でうっかり口を滑らせて秘密を漏らしてしまうことのほうが恐ろしい、という意味もあります。 | ||||
| 虎を養いて患を残す | ||||
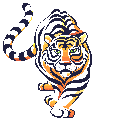 除くべき禍根を絶たずにおくと後になって災いを招くということ。
除くべき禍根を絶たずにおくと後になって災いを招くということ。史記(項羽本紀)より、トラの子を殺さずに育てたために、やがて凶暴な猛虎となって手に負えなくなることからいいます。 | ||||
| 虎は風に毛を振るう | ||||
 トラは吹いてくる風に対してさえも毛を逆立てて、毅然たる気配を示すということで、
トラは吹いてくる風に対してさえも毛を逆立てて、毅然たる気配を示すということで、勇気ある者は事を起こす際には、猛然と奮起することをいいます。 | ||||
| 虎鬚(こしゅ)を編(あ)む | ||||
 虎鬚はトラのヒゲのことです。
虎鬚はトラのヒゲのことです。生きているトラのひげを編むということで、 非常に危険なことをあえてするたとえです。 | ||||
| 之を用いれば即ち虎になり、用いざれば即ち鼠となる | ||||
| ||||
| 虎口(こぐち・ここう) | ||||
 虎口(こぐち):
虎口(こぐち):城やその各郭あるいは陣営などの最も要所にある出入り口のことで、小口とも書きます。単なる出入りだけでなく、 防御と攻撃や出撃の機能を持たせるために、前面に堀を設けたり外に小さな台場を張り出した馬出(うまだし)、土塁で囲んだ方形の空間をはさみこんだ枡形(ますがた)等種々の工夫と施設が加わって発達しました。 虎口(ここう): 恐ろしいトラの口の意味で、非常に危険な場所や危険な状態のことです。 | ||||
| 虎は飢えても死したる肉を食わず | ||||
 トラはたとえ飢えても死んだ動物の肉は食べないという俗信から、潔白な人は、どんなに困窮しても不正なお金や物品は受け付けないということです。
トラはたとえ飢えても死んだ動物の肉は食べないという俗信から、潔白な人は、どんなに困窮しても不正なお金や物品は受け付けないということです。
| ||||
| 口は虎、舌は剣 | ||||
|
| ||||
| 虎に追われた者は虎の絵におずる | ||||
|
| ||||
| 虎嵎(トラぐう)を負う | ||||
|
| ||||
| 虎に翼 | ||||
 トラに翼が生えてくることで誰にも手を付けられなくなること。ただでさえ強い者にさらに何かほかの威力を加えることや、もとから勢いのあるものにより力を加えて一層勢いづかせることをいいます。
日本での「オニに金棒」とおなじ意味で、この「ことわざ」は韓国でよく使われているようです。
トラに翼が生えてくることで誰にも手を付けられなくなること。ただでさえ強い者にさらに何かほかの威力を加えることや、もとから勢いのあるものにより力を加えて一層勢いづかせることをいいます。
日本での「オニに金棒」とおなじ意味で、この「ことわざ」は韓国でよく使われているようです。
| ||||
| 虎を画きて狗に類す | ||||
 雄猛なトラを描こうとして、イヌのようなものになってしまうということ。
雄猛なトラを描こうとして、イヌのようなものになってしまうということ。素質や力量の無い者が、優れた人物の真似をして失敗するいいます。また、目標が大きすぎて失敗することをいうこともあります。 | ||||
| 虎嘯(うそぶ)けば谷風(こくふう)至る | ||||
 谷風は、東風、春風のことで、トラがほえると谷風が起こるということから、立派な君主のもとにはすぐれた臣下が現れるということです。
谷風は、東風、春風のことで、トラがほえると谷風が起こるということから、立派な君主のもとにはすぐれた臣下が現れるということです。
また、英雄がひとたび立てば、天下に風雲がまき起こることをいいます。 | ||||
| 虎尾春氷 | ||||
|
どちらも危ういことですので、非常に危険で、ひやひやすることのたとえです。 | ||||
| 唐土の虎は毛を惜しみ日本の武士は名を惜しむ | ||||
|
| ||||
| 虎の子は山へ放せ | ||||
|
トラは本来山にいるべき動物であるように、物事はむやみに人為を加えず、本来あるべき場所にもどしてやるのが良いということです。
| ||||
| 両虎相闘えば勢いともに生きず | ||||
  二頭の虎が闘えば、両方とも生き残ることはなく、必ずどちらか一方が傷ついて死ぬことになる。
二頭の虎が闘えば、両方とも生き残ることはなく、必ずどちらか一方が傷ついて死ぬことになる。強豪同士が戦えば、必ずどちらか一方、または双方が倒れるということのたとえです。 | ||||
| 口の虎は身を破る | ||||
|
| ||||
| 虎口を脱する | ||||
|
| ||||
| 白虎隊(びゃっこたい) | ||||
|
(白虎は四方をつかさどる天の四神の一つで、西に配します。) | ||||
| 虎は千里の藪に住む | ||||
 トラは千里を往復するほどすぐれた動物なので、住むには広大な土地が必要です。すぐれたものは狭苦しいつまらぬ所にはいないで、広々とした環境にいるべきであるということです。
大望を抱いて郷里を飛び出す青年などの意気をいったものです。
トラは千里を往復するほどすぐれた動物なので、住むには広大な土地が必要です。すぐれたものは狭苦しいつまらぬ所にはいないで、広々とした環境にいるべきであるということです。
大望を抱いて郷里を飛び出す青年などの意気をいったものです。
| ||||
| 琥(コ) | ||||

「トラの形をした玉の器」「(兵を挑発するときに用いる)トラの皮の模様を刻んだ玉製の割符」の意の漢字。
| ||||
| 大人虎変(たいじんこへん) | ||||
|
大人は有徳の人格者のことで、虎変はトラの皮ががらりと生え変わることから、すぐれた賢人が時の推移に従ってみごとに変化・変革をとげること。また、人格者によって、古い制度がりっぱな新しい制度に改められることをいいます。
| ||||
| 虎子地に落ちて牛を食らうの気あり | ||||
|
| ||||
| 虎は死して皮を留め人は死して名を残す | ||||
|
トラが死んで美しい皮を残すように、人間も死んだあとに名誉や功績を残すべきであるということのたとえ。 | ||||
| 虎は千里行って千里帰る | ||||
|
| ||||
| トラを(千里の)野に放つ | ||||
|
猛威ある者を自由にさせて、その威をふるわせておくことです。害になるものや危険なものを取り除かずに野放しにして、あとに大きな災いを残すことのたとえです。
| ||||
| 虎刈り | ||||
|
| ||||
| トラのパンツ | ||||
|
昔の中国では冥府の神「秦山府君」が住むと言われていた山が北東にあったことから、冥府→北東→鬼門といわれています。 | ||||
| 虐(ギャク、しいたげる) | ||||

「むごい目にあわせる」「いじめる」「いためる」「つらくあたる」「そこなう」「きびしい」「わざわい」の意の漢字。
| ||||
| 暴虎馮河(ぼうこひょうが)の勇 | ||||
|
猛々しいトラを素手で討ち果たし、大きな河を徒歩で渡る勇気。 | ||||
| 苛政(かせい)は虎よりも猛(たけ)し | ||||
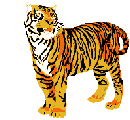 孔子が泰山の麓の墓で婦人が泣いているのに出会い、そのわけを尋ねると、舅も夫も子もトラに食い殺されたと言う。
孔子が泰山の麓の墓で婦人が泣いているのに出会い、そのわけを尋ねると、舅も夫も子もトラに食い殺されたと言う。「それならなぜこの地から出て行かないのか」と孔子が問うと、「それでもこの地にはむごい政治がないから」と答えたという故事。 人民を虐げる苛酷な政治は、人を食い殺すトラよりもむごく恐ろしいということです。 | ||||
| 虎視眈眈(こしたんたん) | ||||
 トラが獲物を狙って鋭い眼でじっと見下ろすようす。
トラが獲物を狙って鋭い眼でじっと見下ろすようす。野望を遂げようとして機会をじっと狙うこと。 | ||||
| 猫でない 証拠に竹を 書いておき | ||||
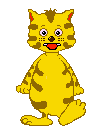 トラを描いたもののネコと間違われないように、
トラを描いたもののネコと間違われないように、トラの絵につきものの竹を描き加えておくこと。 へたくそな絵やその絵描きをあざけった川柳。 | ||||
| 虎の尾を踏む | ||||
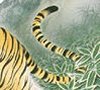
「危うきこと虎の尾を踏むが如し」ともいい、 | ||||
| 三人虎を成す | ||||
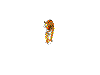
嘘やうわさ等も多くの人が言えば、事実であるかのようになってします事のたとえです。 | ||||
| 虎の巻(トラのまき) | ||||
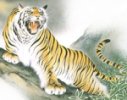
芸事などの秘伝をしるした書や、講義などに用いる種本のこと。また、教科書の内容を簡単に解説した参考書やあんちょこのこと。
| ||||
| 前門の虎、後門の狼 | ||||
| ||||
| 虎の子渡し | ||||
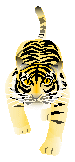
苦しい家計のやり繰り算段の例え。 | ||||
| 虎の子 | ||||
|
虎が特に子を大事にすることから、非常に大切にして手放さない金品や、とっておきのもののことをいいます。 | ||||
| 騎虎の勢い(きこのいきおい) | ||||
|
「騎虎」は虎に乗ること。虎に乗って走り出すと、途中で降りたら虎に食い殺されてしまうので、しかたなく勢いよく走り続けなければいけません。 | ||||
| 張子の虎 | ||||
|
竹でかごのようなものを作り、その上に虎の形になるように紙を貼って仕上げたおもちゃのことです。 | ||||
|
動物に関る言葉のミニ辞典作成に際し、以下を参考にさせていただきました。
三省堂:広辞林、TBSブリタニカ:ブリタニカ国際大百科事典、角川書店:新国語辞典、小学館:新選漢和辞典、大修館:漢語新辞典、 三省堂:デイリーコンサイス英和辞典、川出書房:日本/中国/西洋/故事物語、動物出版:ペット用語辞典、 実業の日本社:大人のウンチク読本、新星出版社:故事ことわざ辞典、学習研究社:故事ことわざ辞典、Canon:国語/和英/英和/漢和/電子辞典、 |